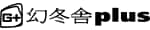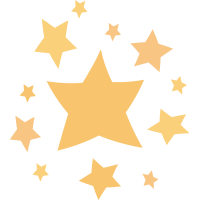約束を破る、遅刻する、だらしない――鈴木大介さんが長年取材してきた貧困の当事者には共通する特徴がありました。ですが、鈴木さんは、2014年に刊行され10万部のベストセラーとなった『最貧困女子』で、そのことをあえて書きませんでした。それはなぜなのか? 鈴木さんの最新刊『貧困と脳「働かない」のではなく「働けない」』から「はじめに」(前半)をお届けします。
* * *
日本には貧困がある。かつてはそのことに疑問の声を投げかける論者もいた。日本に飢えるようなことはない、すべての子どもが学校に通えるような日本に子どもの貧困など存在しないと吐き捨てる為政者もいた。だが、2024年。もはやこの国が格差社会であることも、事実貧困者が存在することも、誰も疑わない。
けれど、貧困者に対する自己責任論は、変わっただろうか?

格差や貧しさが普遍的になる中、その渦中にある者ほど、貧困者を差別し攻撃する。私たちはこんなにも努力してこの苦境に抗っているのに、同じ努力をしないあなたが貧困なのは自己責任だという感情と、論。自らの努力で苦境に立ち向かう者ほど、同じ状況で努力をしない(ように見える)者に対して、辛辣だ。
かつては「頑張れば誰でも豊かになれる」と信じた高齢世代が、どれほど頑張っても結果の出ない時代に暮らす若者に向けて放った自己責任論。いまやそれは、むしろ自助努力の渦中にある若い世代を中心に普遍的な言説となった。
貧困者・弱者への差別と排除は、「あの頃」よりも深刻になっている。
代表作でもある『最貧困女子』(幻冬舎新書)の刊行から、10年経った。『最貧困女子』は、2002年から2013年までに取材を重ねた、自らの貧困状態をセックスワークや売春ワークといった「一般的に不適切とされる自助努力」で何とか生き抜こうとする女性・未成年の少女らのリアルを描いた一冊だ。
決してセンセーショナルな切り口を狙ったわけではなかった。描きたかったのは、この日本社会の裏側にある、理不尽の姿だ。
取材を続けた彼女らの多くは家族資源や教育資源が極めて希薄な、典型的な「世代間を連鎖する貧困」の当事者であり、多くが育児放棄や被虐待の過去を抱えていた。にもかかわらず、何とか生き抜くために「不適切な自助努力」を選択することで、彼女らは本来であれば救済の対象であるにもかかわらず、社会から差別や白眼視される存在になっていた。
彼女らの生きるこの理不尽な状況は、単なる貧困とは違う。彼女らは明らかに社会から不可視化され、統計にもカウントされない。複雑な生い立ちや不適切な自助努力は、公的な福祉と支援の手を一層遠ざける。社会の冷たい視線は彼女らをますます制度から遠ざけ、自助努力へと追い込む。けれど、その自助努力で楽々生き抜いていける者などいない。セックスワークの中でも、店舗などを通さず毎日知らない男に本番行為を提供する売春は数々の危険を伴う底辺中の底辺で、ゴールのない自助努力が、彼女らを取り巻く現実だった。
だからこそ、彼女らを単なる「貧困女子」ではなく、「最」貧困女子というタイトルを用いて描写した。
一方で男性についても同時期、劣悪な生育歴からの起死回生を不適切な自助努力(触法行為・裏稼業)で図らんとするアウトローな少年らと、彼らのその後を取材して描いた。漫画原作を担当し映画化もした『ギャングース』のソース=『ギャングース・ファイル 家のない少年たち』(講談社文庫・2015年)、『振り込め犯罪結社』(宝島社・2013年)、『老人喰い』(ちくま新書・2015年)など一連の著作がそれだ。
彼女ら彼らは、社会通念上好ましくないと思われがちな存在であると同時に、あくまで「救済されるべき時期」に救われなかった存在だった。いかつく面倒くさく、時に近寄りがたいそのパーソナリティの背後には、泣きはらした子どもの顔が透けて見えた。
救うべき時に誰も救わず、自力で這い上がったら社会から白眼視される、かつての子どもたち。そんな理不尽は耐えがたいと思い、著作を重ねた。
だが……。
彼らの生き様を綿密に綴った一方で、敢えて著作に書いてこなかった、いくつもの「なぜ?」があった。
なぜ彼らは、こんなにもだらしないのか。
なぜ、何度も何度も約束の時間を破って遅刻を重ねるのか?
なぜ即座に動かなければ一層状況が悪くなるのが目に見えてわかっている場面で、他人事のようにぼんやりした顔をし、自ら動こうとしないのか?
なぜ熱もないのに寝たまま行政や銀行の窓口稼働時間を逃し、支払いや申請が間に合わずに泣きついてくるのか?
なぜ督促と書かれた封筒を開けもせず、ポストの中に溜めるのか?
なぜ手を差し伸べる支援者に限って激しく嚙みつき、せっかくの縁をぶち壊しにするのか?
取材中、繰り返される「なぜ?」を、何度も封じてきた。
言うまでもなく、それをそのままに書けば、それこそ自己責任論の燃料になるからだ。敢えて解像度を下げて、彼らの困窮のみを伝えるように努めた。
貧しいと言いながら不要な物品にあふれかえる居住環境、明日をも知れぬ経済状況にある者の冷蔵庫にある高級な肉などを文字通り「そのまま」に放映して案の定炎上させるテレビメディアなどに毒づきながら、僕自身の「なぜ?」を封じ、貧困とは「そういうものだ」と自らに言い聞かせた。
その解釈として、『最貧困女子』では、人は金銭的な貧しさに加えて「三つの無縁」と「三つの障害」から貧困に陥るとまえがきに記した。
三つの無縁とは、
- 「家族の無縁」(困窮時に支援をしてくれる親兄弟や親族などの資源がないこと・適切な教育を受ける家庭環境などもなかったこと)
- 「地域の無縁」(困窮時に相談できる友人や相談先などが生活圏内にないこと)
- 「制度の無縁」(生活保護など公的扶助の捕捉率・認知度・制度使用の利便性が極めて低いこと・困窮の当事者が支援制度とそもそも相性が悪いこと)
一方で三つの障害として提言したのは、「精神障害・発達障害・知的障害」だった。
「貧困者は障害者だ」という乱暴な受け止め方をされればとんでもない差別問題になってしまうため、慎重な表現をするように努めたが、貧困の当事者を取材する上で、三つの障害はあまりに普遍的で、密接な因果を感じさせるものだったゆえの提言だった。
実際、初めての著作である『家のない少女たち』(宝島社・2008年)の時点で既に、虐待や貧困を伴う劣悪な生育家庭から緊急避難的に飛び出して売春で自活する少女らの中にはADHDやASDなど発達障害特性を感じさせるパーソナリティの少女らが極めて多いことに言及していたし、取材対象者の中には知的障害がある(療育手帳取得者から、無支援のボーダーケースまでを含む)少女がいたことも報告していた。
2010年に刊行した『出会い系のシングルマザーたち』(朝日新聞出版、後に『最貧困シングルマザー』として文庫化)では、1年少々をかけて取材をした計21名の取材対象者(売春を主な生計として子育てをするシングルマザー)のほぼ全員が精神科に通院中か通院歴があったことに言及している。
「なぜ」をたびたび感じながらも、それが貧困者の実像であり、それが精神を病んだり障害特性がある者の実情なのだと解釈し、彼らに対する自己責任論の燃料になりそうなリアルは徹底して解像度を落として描写し続けた。
そのことをいまは、後悔している。
* * *
続きはぜひ『貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」』でお読みください。
配信: 幻冬舎Plus