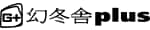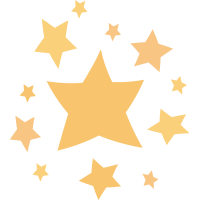吉永小百合さん主演で映画化された『いのちの停車場』のシリーズ3作目『いのちの波止場』。主人公は広瀬すずさんが演じた看護師・麻世。彼女は能登半島の穴水にある病院で、「緩和ケア」について学んでいきます。モルヒネ、ICD、胃瘻……。医療スタッフと患者、その家族たちのリアルで切実な問題を本文よりご紹介します。
* * *
「うちの体は不死身になったさかい」――ICDを胸に入れた、子宮体癌ステージIVの海女さん
第二章 海女のお日様
83歳の照枝はつい最近まで現役の海女だった。末期癌患者だが、ICDを胸に入れているため「自分は不死身だ」と明るく笑う。照枝を愛する家族は、医師に勧められてもICDを停止することにどうしても抵抗があり……。
*
〈私は不死身だから大丈夫〉=緩和ケア病棟、ICD装着中の癌患者の述懐
まぎれもない。スライドに映し出されたコメントは、照枝さんの口癖だ。
「実践的な症例の検討を進めましょう」と北島先生は言い、「死の淵にある癌患者に対して、ICDを停止させないままでいるとどうなるか?」と問いかけた。
その質問に誰も答えられない。
いや、最後列で低い声が上がった。なんと、発言の主は仙川先生だった。
「……体は静かに死に向かっているのに、心臓や周辺の筋肉だけがビクンと反応する。ICDが引き起こす除細動は大変な苦痛をもたらします。さらにそれが繰り返し起きたとすれば、苦しみは耐えがたいものになるでしょう。やがて心臓の、そして全身の細胞が反応しなくなって、ようやくICDが作動しても反応を起こさない体になる」
亡くなりかけている高齢者に、意味を失った暴力的な心臓マッサージをするのと同じことだ。
「実にリアルなご説明をくださり、ありがとうございます。今お答えいただいたように、末期癌の患者が苦痛のない穏やかな最期を迎えるには、ICDが邪魔になるタイミングがどこかで来てしまう。それゆえに、適切な時期にICDを停止するのが望ましいのです」そこまで言って、北島先生は一人うなずいた。
「ICDをつけたままでいると、患者はいわば『ポックリ死』できなくなる。ICDによる電気ショックは、胸を蹴り込まれたような痛みです。脳の機能低下が著しい患者であれば、ICDが作動しても患者本人はすでに苦痛を感じない状態かもしれない。しかし、その痛々しい状況を見せられる家族のショックも無視できないでしょう」
救急治療室での電気ショックとは違い、終末期医療の場では家族が見守る前で、まさに目の前でICDが作動してしまう。穏やかな死を迎えるべき時間に──。
では、どうすればICDを止められるのか? 北島先生の説明によると、患者の胸を開いて機器を取り除くといった大掛かりな手術は不要だ。作動停止のプログラミングをするか、マグネットを体の上から当てるだけでICDの動きを止められるという。
「一番難しいのは、どの時点で停止の決定をするかです。本来であれば、ICDを植え込む手術を受ける時点で、出口戦略についても循環器の専門医、患者本人と家族がしっかり議論をしておかなければならない。ところが現状ではそれができていない。ならば、目の前に患者の死が迫る喫緊のケースについては、家族にICD停止の必要性や適切なタイミングをできるだけ分かりやすい言葉で伝えることで……」
北島先生の説明が続く。前の晩に仙川先生と話をしていたおかげで、今日のレクチャーは頭に入って来やすかった。北島先生は怖そうに見えるけれど、実は患者さんの死にひたすら真剣なだけで、心根はどこまでも優しい。この日、私は強くそう思った。
配信: 幻冬舎Plus