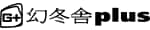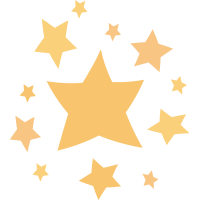乗り物で移動するだけが旅ではないと思っている。
三年前まで、夕方、非日常の旅をしていた。近所のジャズバーである。
当時、隣町にコワーキングスペースを借り、自転車で通っていた。主の自宅の一部をコワーキングにしていることから、18時でクローズする。
朝から仕事をしていると、その頃にはたいてい電池が切れかける。18時きっかりに私はノートパソコンの入ったバッグを荷台に乗せ、まずは帰る道すがらにあるコーヒーチェーン店へ。1時間ほど細々した仕事を片付ける。メールの返信や原稿の調整など、あまり頭を使わなくていい作業をやる。
19時過ぎ。坂を下ったところにあるバーへ向かう。雑居ビルの上階にあり、看板もわかりにくい。ジャズには全く明るくないが。たまたま仕事関係の人に連れて行ってもらい、二度目からひとりで通うようになった。
ぶ厚い鉄の扉。黒光りする木のカウンター。ひと抱えもある大きなスピーカー。
その時間帯はまだ、バーテンダーひとりしかいない。私とは逆に、さあこれから頑張るぞという密やかな闘志が、ボトルを磨き、氷を作る彼の手先、肩先から伝わる。夜深い時間と違い、会話もゆっくりできる。
賑やかに人が交差するのはもう少し先だ。戦い前の静寂な空間は、掃き清められた禅寺のようにどこか清々しい。
いつも、一杯目はジンリッキーと決めている。炭酸の泡をつぶさぬようそっとステアして差し出されたそれは、不思議と毎回味が微妙に変わる。
尋ねると、「お客様の疲れ具合やその前に食べたもの、天気などに合わせて、ライムの絞り加減を変えたり、ジンの種類を替えています」とのことだった。
ジュニパーベリーのほのかな苦味とライムの爽やかな香りが炭酸をまとって、今日一日の疲れを流しさってくれるよう。だから最初の一杯はどうしてもこれになってしまう。
週一、二回、そんなふうにして、コワーキングの帰りにバーで一、二杯飲んでから帰宅し、夕食を作り始めるルーティンが続いた。
私はその後引っ越し、自宅に仕事部屋を作ったことから、隣町のコワーキングに通うことがなくなった。
ほどなくして店はライブ中心になり、夕方の非日常の旅はなんとなく終わった。そうなんだ。バーは、私にとって母でも妻でも筆名の大平でもなくなる非日常、刹那の旅だった。行く前はヨレヨレで、帰るときは心の洗濯が終わっている。おいしい酒、心地よい音楽で満たされ、身も心も開放される。旅と同じだ。
あるいは夜、友達や仕事仲間と都心で飲んだあと、家に帰る前にその店に寄るのも好きだった。ドアの中からライブの音が聴こえなかったら、そっと重い扉を押す。
「あ、かずえさん、こんばんは」と、いつもの顔がカウンターに並んでいる。けれど互いに名字も肩書も住んでいる場所も知らない。だから下の名も、漢字じゃなくひらがなのやわらかな響きで耳に届く。
みなが、何者でもない身軽でニュートラルな自分になる。知らないので上司の悪口も、会社や近所の噂話も出ない。
店以外共通の話題がなさそうなのに、いつまでも話していられる。音楽が好き、お酒が好き、ここが好き。それだけで、大人は誰も傷つけ合わずなごやかに、いつまでも語り合うことができるのだと、この店で知った。
今は越した先の近所でそういう店を見つけ、通っている。
家と外の社会のすきまに、そんな小さな旅先があると、みんなぐっと生きやすくなるのではと思う。◯◯社の☓☓さんではない、フラットな自分になれるサードスペースが。
昨夜は隣に座った女性と、食べたいつまみがあるがひと皿は無理ということで意見が一致し、皿もお代も分け合った。あとから、また女性のひとり客が。少し前にオリンピックに出たことがあるという。カウンターの客たちは、競技の苦労話に興味津々で耳を傾けるがやっぱり、下の名前しか聞かない。いいいい、それで。
だって旅先で素性を聞くのは野暮だもの。

(1杯目はジンリッキー。ライムの潰し方で味がガラリと変わる)

(夕方行くときの2杯めはカクテル。深夜の締めはシングルモルトウイスキーに)
配信: 幻冬舎Plus