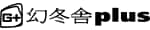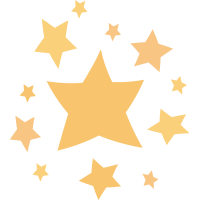ランチも欲張りにハーフ(半身)ハーフ(半身)
全身全霊は思考停止だと思うから
読書量が大幅に減った嘆きを以前ここで書いた。
2023年に読んだ本が212冊に減ってわかる「人生」と「自分」の折り合い
年間212冊という数字が、よその人からすればクレイジーに見えるだろうことは理解している。仕事として本を読む人やよほどの有閑人でなければ、数百冊規模を読むことはなかなかないのだろう。フルタイムで働く現役世代会社員ならなおさら……。
それでも私にとって212冊はミゼラブルな数字で、当時は落ち込んだ。「私って何のために生きてるんだろう」「なんでこんなに忙しいんだろう」と自問自答もした。
そして思い出したのが、上野千鶴子さんの「半身で働く」という言葉。
今年大ヒットした『なぜ働いていると本が読めなくなるのか 』(三宅香帆/集英社新書)でもこの上野さんの言葉が引かれ、「全身全霊で働くことを礼賛するのをやめ、半身で働こう」というメッセージが強く打ち出されている。
思い返せば、私は「全身全霊」がとにかく苦手。一つのことに打ち込んだり、誰かと特別親密な関係になったりする経験は薄く、「中高は野球一筋でした!」「子どもの頃から絵を描くのが好きで…」「幼馴染と今でも親友で」「初恋の人とゴールイン」などのエピソードとは無縁。勉強も、会社の仕事も人間関係も、いつもほどよく適当に。迷惑をかけず、目立ちもせず、なレベルをそこそこのリソース投入で叶えるという、小器用に生きるタイプの人間だ。
注意力も散漫だし、根性も体力も足りないし。冷静な自己認識のもと、選択的にぬるい生き方をしてきたのに、ここ数年は知らず知らず仕事にだいぶ「全身全霊」してしまっていたようだ。
もちろん、これはこれで良い面もあった。喜怒哀楽多めのいろいろな経験をした。スキルもついた。スキルがついたら信用がついてきた。信用がついたら影響力がついてきた。おかげで社会で生きやすくなった。
それでも、2024年はもっと本を読もうと思った春のはじめ。そして12月初頭の今、すでに昨年比1.5倍はクリアしている。ああ、自分が還ってきた感じ。
これには面白い発見もあった。
意識的に読書量を増やそうとしたら、面倒くさいことがいろいろ起きた。会社での振る舞いも、副業認定をとることも、家庭の雑事あれこれも、プライベートの社交も……、ぜんぶ考えて調整しないと、読書時間が確保できない。そのことで、これまで気にすることがなかったようなモヤモヤが生まれた。あれこれポカミスをしたり、周囲からの見られ方が気になったり、チクチク言葉を浴びたり。
一言でいえば、「いずい」のだ。1年前に比べたらびっくりするほど充実した生活なのに、超いずい。
「いずい」は仙台弁で、居心地が悪い・なんだか不快・気まずいという意味。夏の終わりくらいに、「仕事でも評価されて、文筆業も順調で副業認定ももらって、本も読めて、友だちも増えた。なのになんでこんなにモヤモヤするの?」と考えていたときに、ふっと浮かんだ言葉が「いずい」だった。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の三宅さんがよく「全身全霊で働くとはある意味では思考停止」と発言しているが、ぶっちゃけ私もそう思う。去年の私は思考停止で全身全霊をやっていて、身体はしんどかったけれどいずくはなかった。
半身で生きる(働く)ことは「いっぱい頑張らなくていいから楽」ではない。いろんなものを抱えて同時進行しながら生きるのはかなりストレスフルだということを、私は2024年に学んだ気がする。
読書のために半身を心がけたということが一番の原因だが、読書それ自体も「いずい」を産み出す行為だと思う。
時間がないと、読みやすい本・すぐに必要な本を優先的に読むことになり、自然とバラエティが狭まる。読書量を増やして自分の“境界外”の本まで手を伸ばすようになると、今の自分にとって耳が痛い本・未知の世界を教えてくれる本にもリーチできる。それは発見や学びを得られる読書だが、同時に自分に「いずい」ももたらすのだ。
そういう意味で、2024年は改めて読書の効能を体感した1年だったかもしれない。クリスマスに向けて甥たちに渡す絵本を選びながら、「本の幼虫」だった自分の子ども時代を思い出す本たちを三冊選んだ。
『本を読むひと 』(アリス・フェルネ著、デュランテクスト冽子訳/新潮クレストブックス)

アニタは断固として言う。さあ読もうよ、と。泣かないでいいよ。だってあたしたちのこと見つけにきてくれるんでしょ、とメラニーは言う。――『本を読むひと』より
パリ郊外の荒れ地に住むジプシーの大家族。アンジェリーナばあさんと5人の息子、4人の嫁、そして8人の孫がキャンピングカーで暮らしているところに、図書館員のエステールが毎週通ってくる。エステールは何冊も本を抱えて荒れ地を訪れ、子どもたちに読み聞かせる。あっという間に物語の世界にとりつかれた子どもたち、戸惑いと好奇心、攻撃性をないまぜにしながらそれを見守る大人たち。愛と自尊心、そして教育。ジプシーたちとエステールが交換していく感情が、うずまくように詰まった一冊。
『パトリックと本を読む 絶望から立ち上がるための読書会 』(ミシェル・クオ著、神田由布子訳/白水社)

本を読めば、たとえつかのまだろうと、人は予測を超えた存在になれる。それが読書の力だ。――『パトリックと本を読む 絶望から立ち上がるための読書会』より
著者のミシェルはハーバード大学を卒業後、ロースクールに進学する前にアメリカの貧しい地域で教師のボランティアに従事。教育レベルが低く、荒れた生徒ばかりの学校で、早々に理想は崩れ去り悪戦苦闘するミシェル。読書と詩作を通じて子どもたちと少しずつ距離を縮めるが、弁護士になるために学校を離れたミシェルのもとに、優秀だった元教え子が殺人により収監されたという知らせが――。二人だけの読書会によって彼の更生に寄り添おうとするミシェルの挑戦を描くノンフィクション。
『生きるための図書館―一人ひとりのために 』(竹内悊/岩波新書)

としょかんのちかい
(一)みんながよみたいほんをよめるようにじゅんびします。
(二)みんながしらべたいことを、本やしりょうでおうえんします。
(三)だれがどんなほんをよんでいるか、ひみつをまもります。
――『生きるための図書館―一人ひとりのために』より
図書館は、人と本を繋ぐ場所。60年以上に渡って図書館の仕事に携わり続けた竹内さんが、公共図書館・学校図書館・家庭文庫などさまざまな図書館の変遷・あり方を語る一冊。特に子どもたちにとって読書がどれほど大切か、彼らのために図書館が果たす役割は……。未来に向けた竹内さんの厳しくもあたたかいまなざしは、まるで図書館の守り神のよう。
配信: 幻冬舎Plus
関連記事: