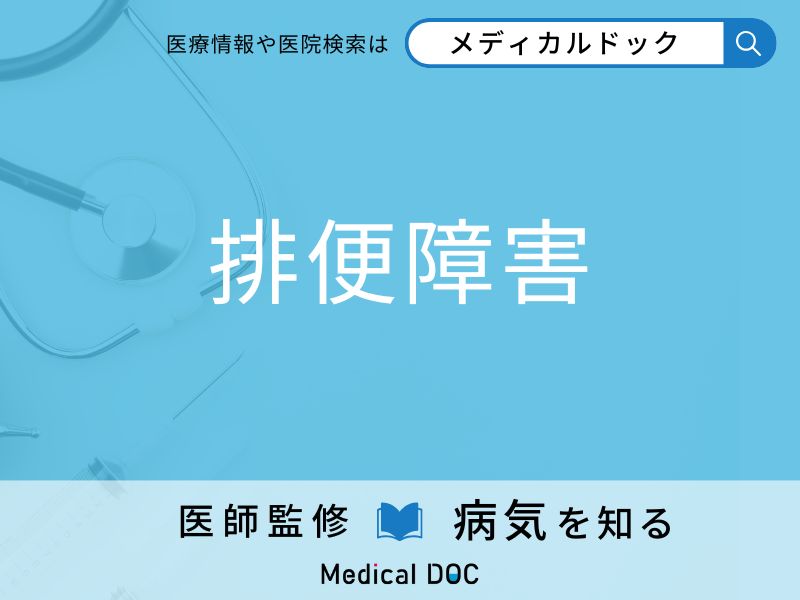監修医師:
岡本 彩那(淀川キリスト教病院)
兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年間研修 / 兵庫医科大学救命センターで3年半三次救命に従事、近大病院消化器内科にて勤務 /その後、現在は淀川キリスト教病院消化器内科に勤務 / 専門は消化器内科胆膵分野
排便障害の概要
排便障害とは、便秘になって便が出にくくなったり、便失禁により便が漏れたりするなど排便に関する障害が生じている状態です。便秘や便失禁のほかに、排便時に強い痛みを感じたり、排便後にすっきりしなかったりすることも挙げられます。
厚生労働省の「2022(令和4)年国民生活基礎調査」によると、便秘に悩んでいる人は438万9,000人です。また、便失禁の症状がある人は500万人いると推測されており、排便障害に悩んでいる人は珍しくありません。
排便障害は、一時的なものから慢性的なものまであります。特に、高齢者や妊婦の人は排便障害を起こすリスクが高いとされています。これは、お腹にうまく力を入れにくかったり、お腹が圧迫されたり、運動不足になりやすかったりするためです。
排便障害の症状が続くと、栄養状態の悪化や体調不良、さらには社会的なストレスや心理的な負担につながることがあります。そのため、症状がみられた場合は、できるだけ早く医療機関で相談することが推奨されます。

排便障害の原因
排便障害の原因はさまざまです。具体的には過敏性腸症候群や大腸がん、直腸瘤、痔核などの消化器の病気が原因となり症状が引き起こされます。
ほかにも、食事の偏りや運動不足、ストレスの蓄積などの生活習慣が排便障害の原因として挙げられます。食生活により食物繊維が不足した場合は腸の働きが低下し、便秘が生じやすくなります。水分摂取が足りないと便が硬くなり、排便が難しくなることもあります。ストレスが溜まると、自律神経の乱れが生じて便秘や下痢を引き起こすことがあります。
さらに、薬の副作用も排便障害の一因です。特に、抗うつ薬や鎮痛薬などの薬は、副作用として便秘や下痢などの排便障害が現れることもあるため、薬の服用中に排便に関わる異常がみられる場合には注意が必要です。
排便障害の症状が改善しない場合は、医師に相談して適切な治療を受けることが重要です。また、日常生活の中で、食事面に気をつけたり運動を取り入れたりするなどの対策を講じることも大切です。
配信: Medical DOC