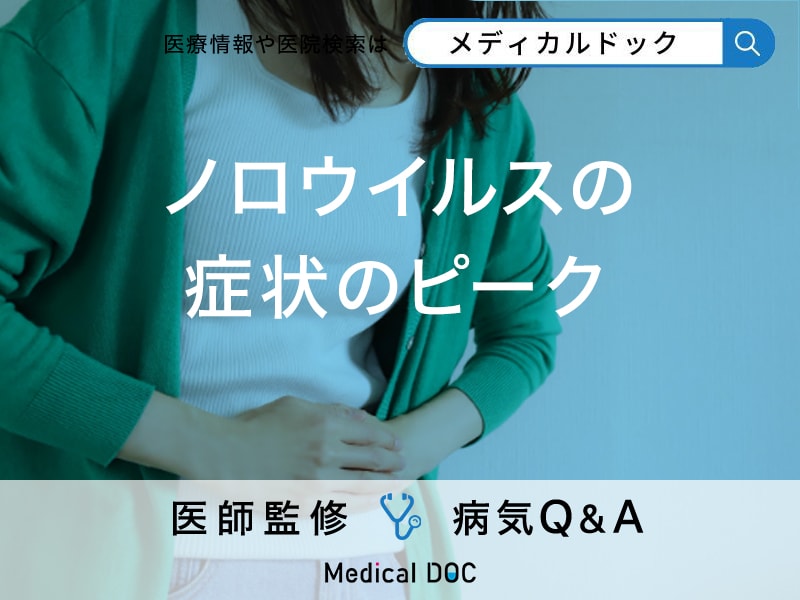冬の時期になるとさまざまな感染症の流行が気になる方は少なくないでしょう。流行する感染症のひとつにノロウイルスによる感染性胃腸炎があります。
ノロウイルスは乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層で嘔吐や下痢の症状が起こります。感染力が高く、家庭内や学校などで集団感染を引き起こすことがあるので注意が必要です。
ここではノロウイルスの感染経路・症状・治療方法・予防方法を詳しく解説します。
ノロウイルスの感染予防や感染してしまったときの対応の参考になれば幸いです。
≫「ノロウイルスの主な5つの症状」はご存知ですか?自宅での対処法も解説!

監修医師:
中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター)
1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎の感染経路や流行時期

ノロウイルスとはどのようなウイルスですか?
ノロウイルスとは、手指や食品を介して感染して人の腸管で増殖するウイルスです。乾燥や熱にも強いうえに自然環境下でも長期間生存が可能で 感染力がとてもに強いので少量のウイルス(10〜100個)でも感染・発症します。乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層に感染して、下痢や嘔吐を引き起こす感染症です。通常は軽症ですみますが、乳幼児や高齢者は脱水や吐物が喉に詰まるリスクが高いため注意が必要です。ノロウイルスは長期免疫が成立しないので、何度でもかかるのが特徴です。
感染経路を教えてください。
ノロウイルスの感染経路は、ほとんどが経口感染です。主な感染経路は以下のとおりです。
感染した人の便や嘔吐物で汚染した手指を介してノロウイルスがお口に入った場合
便や嘔吐物が乾燥して細かい塵となって舞い上がって一緒にウイルスを吸いこんだ場合
感染した人が十分に手を洗わず調理した食品を食べた場合
ノロウイルスに汚染されたカキやシジミなどの二枚貝を、生または不十分な加熱処理で食べた場合
このように感染経路は多岐に渡るので、感染拡大しやすく制御が困難になってしまいます。
流行しやすい時期を教えてください。
ノロウイルスは一年を通して発生していて、特に流行する時期は冬季です。11月から増えはじめて12月〜2月にピークを迎える傾向があります。ノロウイルスは低温・乾燥した環境では感染力が高くなり、生存期間も長くなります。また、夏場ほど水分摂取を積極的にしなくなるので、粘膜が乾燥してウイルスが付着しやすくなるでしょう。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎の初期症状やピーク時の症状

ノロウイルスによる感染性胃腸炎の初期症状を教えてください。
ノロウイルスに感染してから24〜48時間で発症します。突然の激しい吐き気や嘔吐が特徴ですが、初期には以下の症状が現れる場合があります。
寒気
胃がムカムカする
鼻水やくしゃみ
微熱
このように初期症状があったとしても風邪症状と似ているので、嘔吐や下痢の前にノロウイルスに感染したと気付くのは難しいです。お腹が張ったり胃がムカムカするなどお腹に症状があるときは、感染性胃腸炎を疑って手洗いや消毒などの対策をするとよいでしょう。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎のピーク時の症状を教えてください。
ノロウイルスに感染してから潜伏期間が1〜2日間あります。症状のピークは発症後1〜2日間です。ピークの期間は嘔吐・下痢・腹痛の症状がひどく、発熱がみられる場合もあります。嘔吐や下痢の回数が多いと焦りますが、嘔吐や下痢はウイルスを外に排出するために必要なことなので、落ち着いて安静に過ごしましょう。食欲が低下して食事が摂れないときがあっても、脱水にならないように水分補給をするように気をつけましょう。症状のピーク時は、1日に何回も下痢や嘔吐を繰り返すため、特に乳幼児や高齢者は脱水を起こす可能性が高くなります。尿量の減少やお口や喉の乾きなどの脱水症状に注意が必要です。
症状は何日くらい続きますか?
ノロウイルスによる感染性胃腸炎を発症してから1〜3日で下痢や嘔吐などの症状は治り、食欲が出てくるでしょう。発熱や腹痛などの症状も同じように回復してきます。症状が辛いと薬を飲んで早く治したいと考える方は少なくないでしょう。しかし、下痢止めや抗菌薬を飲むとウイルスを早く体外に出すことができなくなるので、症状が長引いてしまう恐れがあります。薬は自己判断で飲まずに、受診して医師の指示に従うようにしましょう。症状が治っても1〜4週間は便の中にウイルスが含まれていることがあるので、トイレで二次感染の可能性があります。症状が治ってからも手洗いや消毒などの対策が必要です。
配信: Medical DOC