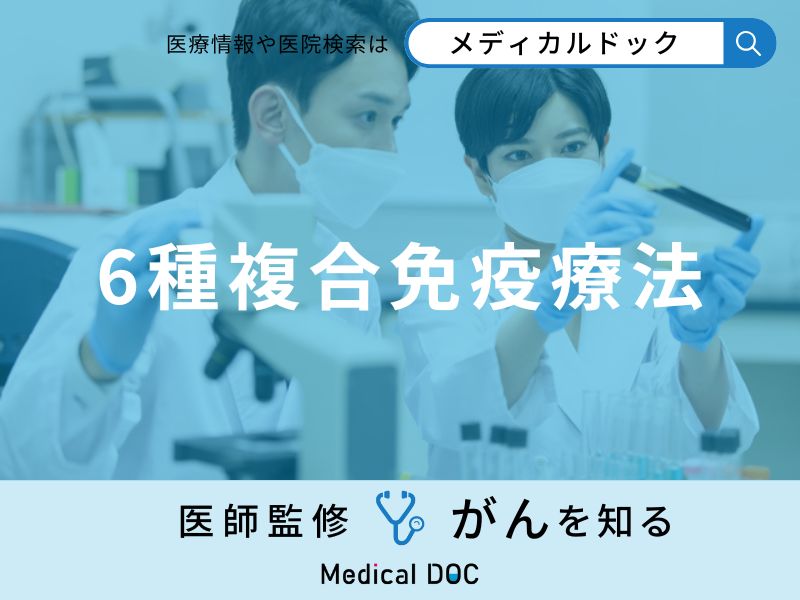6種複合免疫療法とは?Medical DOC監修医6種複合免疫療法で治療できる疾患・メリット・デメリット・費用などを解説します。
≫「抗がん剤を使わない場合の余命」はご存知ですか?医師が徹底解説!

監修医師:
山口 健(医師)
岡山大学医学部卒業。市中院勤務を経て、自由診療クリニックの院長に就任。その後、経営母体の理事長補佐も兼任し、全国40以上のクリニックのマネジメントも行う。自らの法人も立ち上げ、医療コンサル、企業コンサル、医療ライティングなど幅広く活動している。日本美容皮膚科学会員。
「6種複合免疫療法」とは?
免疫療法とは、免疫系ががんと闘うがん治療法の一つです。
免疫チェックポイント阻害薬や、T細胞移植療法、モノクローナル抗体、がん治療ワクチン、免疫系モジュレーターなどがあります。
6種複合免疫療法とは、がんや自己免疫疾患に対して複数の免疫療法を組み合わせるアプローチのことです。標準治療ではなく、補完医療として提供されることが多いです。T細胞移植療法の一種と考えらえますが、一部その他の免疫細胞を組み合わせている点で独自のものと言えます。
6種複合免疫療法では、ヘルパーT細胞、NK細胞、NKT細胞、キラーT細胞、γδT細胞、樹状細胞の6種類の免疫細胞を用います。
6種複合免疫療法は現在一部の医療機関で行われており、標準的な医学用語ではないことは注意しておきましょう。
方法としては、まず患者本人の血液を少量採取します。そして、厚生労働省の許可を受けた施設で細胞培養を行います。その後、6種の免疫細胞を取り出し、活性化・増殖させて投与します。
なお、現時点で医学的なエビデンスのある免疫療法として、免疫チェックポイント阻害薬が挙げられます。
がん細胞は、自分が免疫細胞から攻撃されないように、免疫細胞から逃れるような機構を持っています。
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫から逃れる仕組みを解除し、免疫細胞(特にT細胞)ががんを攻撃できるようにする治療法です。すると、抗原提示細胞や腫瘍細胞に発現するリガンドからの免疫抑制のシグナル(ブレーキ)が入らないようになります。その結果、T細胞の活性化を持続させてがんを攻撃させる薬剤です。
今回の記事では、この6種複合免疫療法を含めた免疫療法について解説します。
6種複合免疫療法で治療できる疾患
6種複合免疫療法は、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんの治療に対応しています。
また、標準治療後に体に残ったがん細胞の抑制、再発・転移の予防にも用いられるとされています。
ここでは、免疫療法の一つである、免疫チェックポイント阻害薬において、保険適用の承認が下りている疾患についてもご紹介しましょう。
メラノーマ(悪性黒色腫)
メラノーマ(悪性黒色腫)は、皮膚にできる悪性腫瘍です。メラニンという色素を作る、メラノサイトががん化したものです。
手術での治療が難しいメラノーマに対しては、免疫チェックポイント阻害薬である PD-1阻害薬や、CTLA-4阻害薬が用いられます。
患者の遺伝子変異や体力などに応じ、これらの免疫チェックポイント阻害薬と、低分子性分子標的薬などを組み合わせて治療を行います。
非小細胞肺がん
肺がんは、肺を構成する肺胞や気管支の細胞ががん化したものです。
組織のタイプによって大きく小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分けられます。
非小細胞肺がんに対しては、手術や化学療法が用いられます。免疫チェックポイント阻害薬は手術ができない進行した肺がんに対して適応があります。
肺がん遺伝子検査とPD-L1検査の結果に基づき、免疫チェックポイント阻害薬の使用が検討されます。
肺がん患者の中には、免疫チェックポイント阻害薬の効果が高いことが期待できるタイプの方がいます。その方に対しては、免疫チェックポイント阻害薬単独、または細胞障害性抗がん薬を併用した治療を検討します。
胃がん
胃がんは、胃の粘膜の細胞ががん化したものです。
がんの深さや、リンパ節や他の臓器への転移の有無によって治療法が決まります。
がんが進行しており手術が行えない場合や、治療後の再発・転移が見られた際には化学療法が選択されます。免疫チェックポイント阻害薬は、HER-2陰性の方が初めて薬物療法をする際に抗がん剤と併用されることがあります。また、一度も免疫チェックポイント阻害薬を使ったことがない方の、何回目かの薬物療法の薬として選択されることもあります。特定のタイプの胃がんに対しては、免疫チェックポイント阻害剤の一つである抗PD‒1抗体ペムブロリズマブの有効性が高いとされています。
配信: Medical DOC