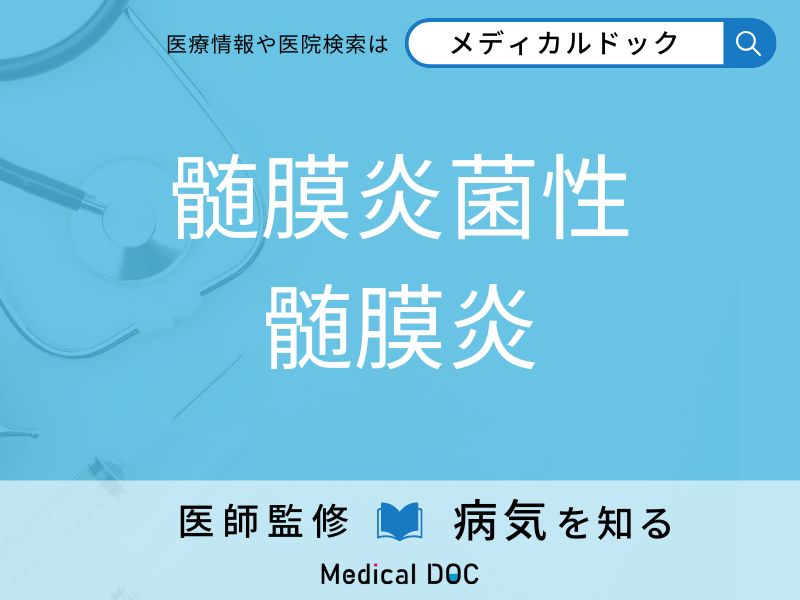監修医師:
吉川 博昭(医師)
医学博士。日本ペインクリニック学会専門医、日本麻酔科学会専門医・指導医。研究分野は、整形外科疾患の痛みに関する予防器具の開発・監修、産業医学とメンタルヘルス、痛みに関する診療全般。
髄膜炎菌性髄膜炎の概要
髄膜炎菌性髄膜炎とは「髄膜炎菌」という細菌が髄膜に感染する疾患です。感染症法では5類感染症に指定されており、診断した医師による届出が義務付けられています。
髄膜は脳と頭蓋骨の間に位置する膜で、脳を保護する役割があります。外側から「硬膜」「くも膜」「軟膜」の3層で構成され、くも膜と軟膜の間には栄養の豊富な脳脊髄液が流れています。
髄膜炎は原因によって、細菌性、ウイルス性、真菌性、原虫性にわかれます。このうち、髄膜炎菌性髄膜炎などの細菌性髄膜炎は重症度が高い傾向にあります。
髄膜炎菌性髄膜炎を発症すると、血液中に骨膜炎菌が広がり、頭痛や高熱、吐き気、精神症状などの症状が現れます。重症の場合には症状が急激に進行し「敗血症」やショック状態をきたして死に至るケースもあります。
髄膜炎菌性髄膜炎の死亡率は10〜15%と高く、無治療の場合には50%にも上るといわれています。救命率を上げるためには、早期の診断と適切な治療を受ける必要があります。
また、予防法として髄膜炎菌に対するワクチンがあるため、流行地域へ渡航する予定がある場合にはワクチン接種について検討することも重要です。
国内では終戦前後に4000件以上の発症報告があったものの、戦後は激減し1990年以降の年間発症数は1桁〜2桁台にとどまっています。近年では、2011年に宮崎県の学生寮での集団感染や2015年におこなわれた山口県でのイベントでの集団感染、2017年に神奈川県の全寮制学校での集団感染事例が報告されています。
出典:
NIID国立感染症研究所「骨膜炎菌性髄膜炎とは」
厚生労働省検疫所FORTH 「疾患別解説骨膜炎菌性髄膜炎」
一般社団法人日本感染症学会「29侵襲性髄膜炎菌感染症」

髄膜炎菌性髄膜炎の原因
髄膜炎菌性髄膜炎は、脳を覆う髄膜に髄膜炎菌という細菌が感染することが原因です。
髄膜炎菌はアフリカ大陸のセネガルからエチオピア・スーダンにかけて広く生息しており、特に12月から6月にかけて流行します。髄膜炎菌の多い地域は地図上で帯状に確認されることから、このような地域は「髄膜炎ベルト地帯」と呼ばれています。
戦後、国内での発症数は激減したものの、散発的に集団感染の事例が報告されています。
髄膜炎菌は、流行地域で人の鼻やのどの粘膜に定着しています。髄膜炎菌が含まれる鼻水や痰などの分泌物に触れたり、咳などのしぶきを吸い込んだりすることで、体内に侵入します。
体内に侵入した髄膜炎菌が鼻やのどの粘膜から血液中に侵入し、髄膜まで到達すると髄膜炎菌性髄膜炎を発症します。
配信: Medical DOC