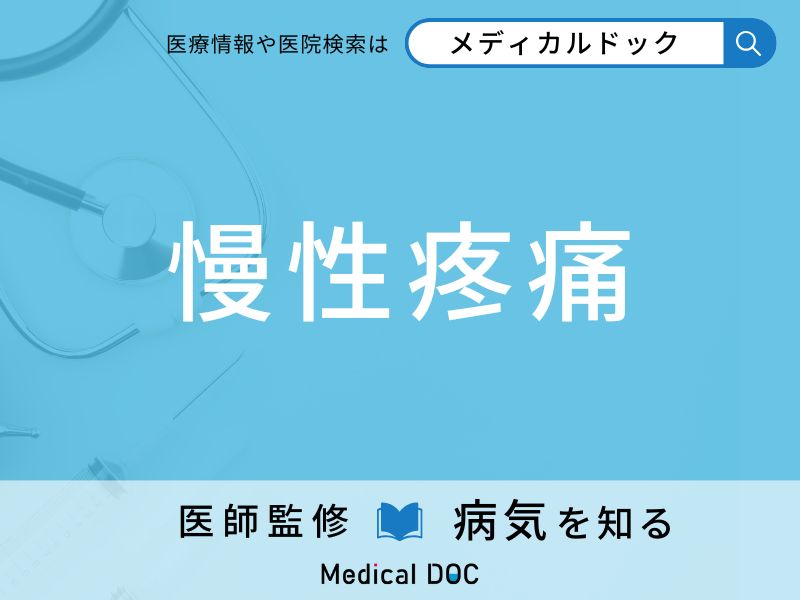監修医師:
大坂 貴史(医師)
京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学大学院医学研究科修了。現在は綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・糖尿病・代謝内科学講座 客員講師を務める。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医。
慢性疼痛の概要
慢性疼痛とは、治癒に要すると予測される時間を超えて持続する痛み、あるいは進行性の非がん性疾患に関連する痛みを指します。ケガや病気が治った後も痛みが続くことが特徴であり、明確な原因が特定できないことも少なくありません。慢性疼痛は、腰痛や関節痛、神経痛などさまざまな部位に発生し、日常生活に支障をきたすことがあります。痛みの強さや症状は個人差が大きく、体の一部分に痛みを感じる人もいれば、広範囲にわたって痛みが広がる人もいます。
慢性疼痛は、単なる体の不調ではなく、長期にわたることで精神的なストレスや抑うつ、不安などの心理的な影響を引き起こすこともあります。そのため、単に痛みを抑えるだけではなく、生活全体の質を向上させる治療が求められます。痛みが続くことで仕事や家事ができなくなったり、外出を避けるようになったりすることもあり、社会的な影響も無視できません。
慢性疼痛は多くの人が経験する症状であり、高齢者だけでなく、若い世代でも発症することがあります。特に、ストレスや姿勢の悪さ、長時間のデスクワークなどが関係している場合もあり、痛みの原因を正しく理解し、適切に対処することが重要です。
慢性疼痛の原因
慢性疼痛の原因は多岐にわたりますが、大きく分けて「炎症による痛み」「神経の異常による痛み」「心因的な影響による痛み」の3つが考えられます。まず、炎症による痛みは、関節リウマチや変形性関節症などの疾患によるものです。これらの疾患では、関節や筋肉に炎症が起こり、その結果として痛みが長期間続くことがあります。特に、関節の摩耗や軟骨の劣化が進むと、痛みが慢性化しやすくなります。
次に、神経の異常による痛みは、神経障害性疼痛とも呼ばれ、神経の損傷や圧迫が原因で発生します。代表的なものに、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛、帯状疱疹後神経痛などがあります。このタイプの痛みは、ビリビリとしたしびれを伴うことが多く、通常の鎮痛薬では効果が得られにくいことが特徴です。また、糖尿病による神経障害も慢性疼痛の一因となることがあります。
さらに、心因的な影響による痛みも重要です。強いストレスや不安、抑うつ状態が続くことで、脳が痛みを感じやすくなり、本来は問題のない部位にも痛みを覚えることがあります。このようなケースでは、身体的な治療だけでなく、精神的なケアも必要になります。特に、仕事や人間関係のストレスが影響している場合、生活習慣の改善やリラクゼーション法を取り入れることが有効です。
配信: Medical DOC