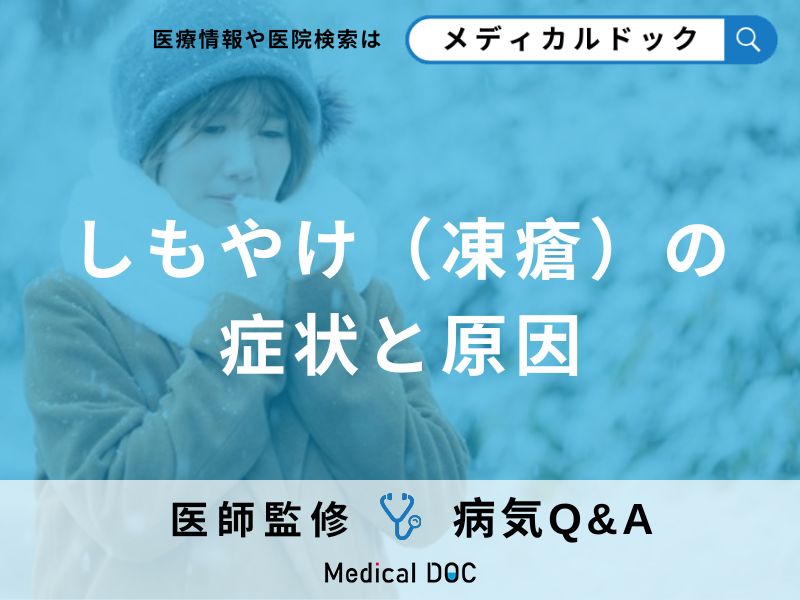・手足の先が赤くなって腫れている
・寒いところから急に暖かい場所へ入ると足先がむずがゆい
・鼻先や頬がよく赤くなる
寒暖差が激しい季節に上記のような症状を感じたら、それはしもやけ(凍瘡)かもしれません。
この記事ではしもやけ(凍瘡)を発症する原因や体質、しもやけ(凍瘡)に似た症状など解説しています。
※この記事はMedical DOCにて『「しもやけ(凍瘡)」が重症化するとどうなるかご存知ですか?対処法も解説!』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師:
竹内 想(名古屋大学医学部附属病院)
名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院にて内科・救急・在宅診療など含めた診療経験を積む。専門領域は専門は皮膚・美容皮膚、一般内科・形成外科・美容外科にも知見。
しもやけ(凍瘡)の症状と原因

しもやけ(凍瘡)はどのような症状がみられますか?
しもやけ(凍瘡)の主な症状は、皮膚の赤みや腫れ・水ぶくれ・かゆみです。ひどくなると水ぶくれが破れて潰瘍ができることもあります。
発生しやすい場所は血行が悪くなりやすい体の末端部分で、手足の指先・耳たぶ・鼻先・頬に多くみられることが特徴です。
皮膚に発生する腫れのタイプは2種類に分類されます。ひとつめは患部全体が赤紫色に腫れる樽柿型(T型)です。ふたつめが、小指の先くらいの大きさに赤みが現れたり小さく盛り上がった状態(丘疹)ができたりする多形紅斑型です。
樽柿型は子どもに多くみられ、多形紅斑型は大人に多くみられる症状となっています。入浴や就寝の際に患部が温まり血流が良くなるとかゆみが強くなることも特徴のひとつです。
原因を教えてください。
しもやけ(凍瘡)の発症は、寒暖差によって血行が悪くなることが主な原因です。
人間は寒さを感じたとき、脳が血管を縮めて血流を減らすよう司令を出します。 そうして皮膚の表面温度を外気に合わせて低く保ち、体内の熱を外に逃さないようにしているのです。逆に暑くなると、脳は血管を広げて血流を増やす司令を出します。それにより皮膚の表面温度を上げたり、汗をかいて熱を放出しやすくしたりしているのです。
寒さと暖かさの刺激が繰り返されると血管の収縮や拡張も繰り返されることになり、血液循環に障害が発生します。これが、しもやけ(凍瘡)の原因で、気温が4〜5度かつ1日の寒暖差が10度前後になると発症しやすいとされています。
真冬よりも初冬や初春に多く発症することが特徴です。また靴下や手袋の中でかいた汗が蒸れて皮膚の表面温度が下がり、発症を誘因します。
しもやけ(凍瘡)になりやすいのは体質でしょうか?
同じ環境にいてもしもやけ(凍瘡)になりやすい人となりにくい人がいます。これは寒気にさらされることによる血流障害の程度と、その回復スピードには遺伝的な差があるためだと考えられているからです。
遺伝的な要因があるということは、体質的になりやすい人がいるということです。体質の他にも、栄養状態や内分泌的な異常も発症の一因を担っていると考えられています。
しもやけ(凍瘡)に似た症状が現れる病気はありますか?
しもやけ(凍瘡)に似た症状が現れる病気として、主に以下の4つが挙げられます。
膠原病(全身性エリテマトーデス・凍瘡状狼瘡)
原発性レイノー症候群
続発性レイノー症候群
シェーグレン症候群
しもやけ(凍瘡)のような症状の他に、なんとなく体がだるい・微熱が出る・関節の痛みを感じる・目が乾く・喉が渇く・唾液が出にくい・暖かくなっても治らないなどの症状を感じることがあれば、一度病院で診察を受けることをおすすめします。
編集部まとめ

子どもに多いしもやけ(凍瘡)ですが、大人になっても繰り返す人もいます。
特にブーツをよく履く人や水仕事の多い人などは、発症のリスクが高まりやすいので注意が必要です。
またこの疾患は予防することがとても大切です。手足や耳といった体の末端部分の保温を積極的に行うなど、普段から発症しないように気を配った生活を送るようにしてください。
しもやけ(凍瘡)は発症しないことがなによりですが、もし発症してしまったらマッサージをしたり塗り薬を使用したりして早期の改善を目指しましょう。
腫れやかゆみが強くて辛い・なかなか治らない・暖かくなったのに症状の改善が見られないといったケースでは、皮膚科を受診することも大切です。
しもやけ(凍瘡)を上手に予防して、快適な冬をお過ごしください。
参考文献
ひふの病気(日本臨床皮膚科医会)
配信: Medical DOC
関連記事: