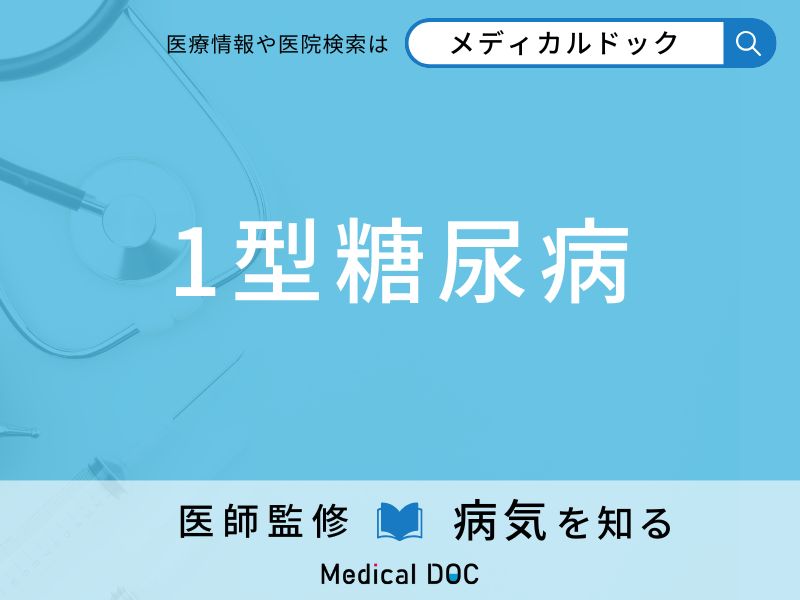監修医師:
大坂 貴史(医師)
京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学大学院医学研究科修了。現在は綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・糖尿病・代謝内科学講座 客員講師を務める。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医。
1型糖尿病の概要
1型糖尿病は、膵臓でインスリンを分泌するβ細胞が自己免疫の異常によって破壊されることで、インスリンがほとんど、または全く分泌されなくなる病気です。インスリンは血糖値を調節するホルモンであり、その不足によって血糖値が高くなり、糖尿病の症状が現れます。
1型糖尿病は一般的に若い年齢、特に子どもや青年期に発症することが多いですが、大人でも発症することがあります。生活習慣や肥満とはあまり関係がなく、根本的な原因としては免疫系の異常などが指摘されています。
現在、1型糖尿病の完治は難しく、患者は日常的にインスリン注射などの治療を行いながら、血糖値を管理する必要があります。適切な血糖値を維持することで、長期間にわたって健康な生活を維持することが可能となっています。
1型糖尿病の原因
1型糖尿病の原因は、主に自己免疫疾患としての性質を持っています。体の免疫システムが誤って膵臓のβ細胞を攻撃し、破壊してしまうことで、インスリンの分泌が停止します。正確なメカニズムは完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。
遺伝的要因
1型糖尿病には遺伝的な要素が関係していることが知られています。特に海外では家族に1型糖尿病を持つ人がいる場合、そのリスクが高まります。しかし、1型糖尿病は遺伝のみで発症するものではなく、環境要因や他の要素も影響を与えます。
自己免疫反応
1型糖尿病は自己免疫疾患の一つです。自己免疫反応とは、体の免疫システムが自己の細胞を攻撃してしまう現象であり、この場合はインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が標的となります。この免疫反応の引き金は不明ですが、ウイルス感染や特定の環境要因が関与している可能性があります。
環境要因
ウイルス感染が1型糖尿病の発症に関与している可能性が示唆されています。特定のウイルス感染が免疫系を刺激し、自己免疫反応を引き起こすことで、膵臓のβ細胞が破壊されることがあります。また、海外の報告では特定の食事や栄養不足、環境の変化も発症に影響するとされています。
配信: Medical DOC