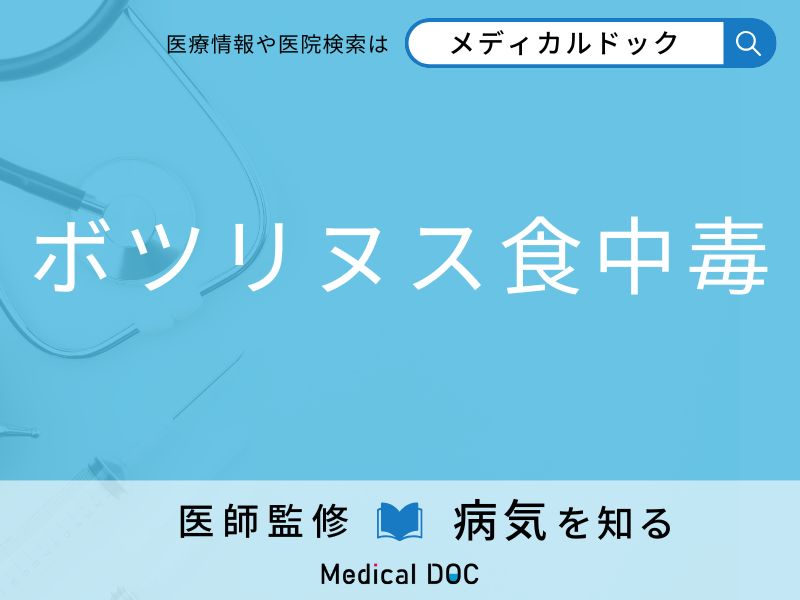監修医師:
居倉 宏樹(医師)
浜松医科大学卒業。初期研修を終了後に呼吸器内科を専攻し関東の急性期病院で臨床経験を積み上げる。現在は地域の2次救急指定総合病院で呼吸器専門医、総合内科専門医・指導医として勤務。感染症や気管支喘息、COPD、睡眠時無呼吸症候群をはじめとする呼吸器疾患全般を専門としながら一般内科疾患の診療に取り組み、正しい医療に関する発信にも力を入れる。診療科目
は呼吸器内科、アレルギー、感染症、一般内科。日本呼吸器学会 呼吸器専門医、日本内科学会認定内科医、日本内科学会 総合内科専門医・指導医、肺がんCT検診認定医師。
ボツリヌス食中毒の概要
ボツリヌス食中毒とは、ボツリヌス菌が作り出したボツリヌス毒素を含む食品を摂取することで発症する病気のことです。ボツリヌス毒素は「最強の自然毒素」ともいわれるほど、強い毒性を持っています。
ボツリヌス毒素は、神経伝達物質であるアセチルコリンの放出を邪魔します。そのため神経と筋肉の伝達が阻害され、筋肉が収縮できず身体に麻痺が生じるのです。
ボツリヌス菌芽胞(※)は土壌や海、湖、川などに広く生息しており、野菜や果物、肉、魚などの食品を常に汚染する可能性があります。このようなボツリヌス菌の芽胞(※)は熱や乾燥、消毒に強い性質を持っています。
(※)芽胞(がほう)とは、細菌の繁殖に適さない環境になったとき形成される耐久性の高い細胞のこと
ボツリヌス菌は低酸素状態になると繁殖し、毒素を作り出す「偏性嫌気性(へんせいけんきせい)」の細菌で、A~G型が知られています。
ボツリヌス菌が原因で発症する病気にはボツリヌス食中毒(食餌性ボツリヌス症)のほか、3つの病態があります。
乳児ボツリヌス症
生後1年未満の乳児がボツリヌス菌芽胞を摂取した場合に発症する(原因食品はハチミツが多いです)
創傷ボツリヌス症
傷口からボツリヌス菌芽胞が侵入し、神経毒素が産生された場合に発症するした場合に発症する
成人腸管定着ボツリヌス症
1歳以上の小児や成人がボツリヌス菌芽胞を摂取した場合に発症する(消化器の異常や、抗菌薬使用などによる腸内細菌業の異常が認められることが多い)
ボツリヌス食中毒の原因
ボツリヌス食中毒の原因となりうるものは、缶詰のように「酸素のない密閉された状態の食品」です。
日本で起こったボツリヌス食中毒の事例として有名なものは、下記のとおりです。
真空パック詰の食品:カラシレンコン、ハヤシライスの具、あずきばっとう(※)
缶詰の食品:里芋
瓶詰の食品:グリーンオリーブ
特に自家製の缶詰や瓶詰食品が最も頻度が高いです。
(※)あずきばっとうとは、岩手県の郷土料理で甘さ控えめの小豆汁にうどんが入ったもの
また北海道や東北地方の特産品である「いずし」を原因としたボツリヌス食中毒も報告されています。なお、いずしとは魚と野菜を米麹に漬けて発酵させたものです。近年は家庭で作る機会が減ったため、いずしによるボツリヌス食中毒はほとんどなくなりました。
ボツリヌス食中毒の中には、原因食品が特定できないケースも多いようです。そのため主に加工食品に由来する食中毒といえど、患者の発生が1件のみのことも少なくありません。
配信: Medical DOC