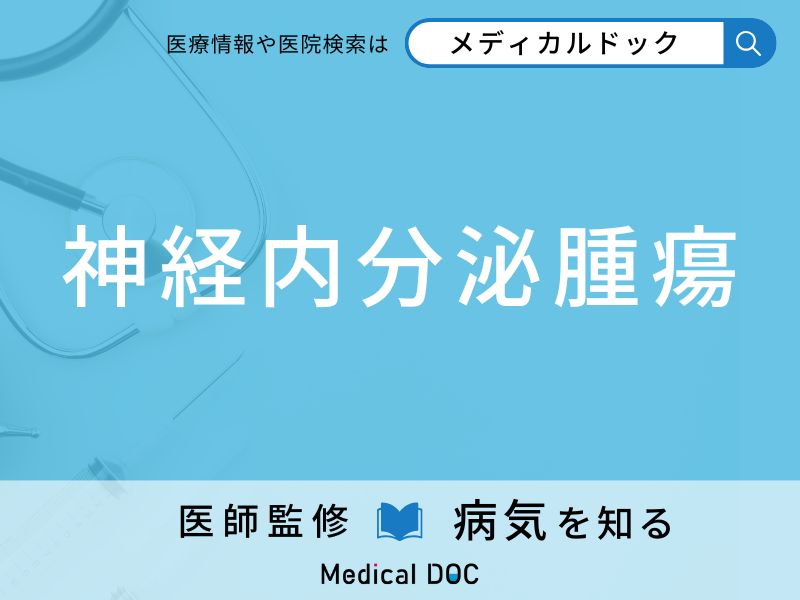監修医師:
大坂 貴史(医師)
京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学大学院医学研究科修了。現在は綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・糖尿病・代謝内科学講座 客員講師を務める。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医。
神経内分泌腫瘍の概要
神経内分泌腫瘍(NET)は、全身に存在する神経内分泌細胞を発生母体とする腫瘍性疾患の総称です。消化器領域に約6割、呼吸器領域に約3割が発生します (参考文献 1) 。腫瘍から分泌されるホルモンによる症状が目立つ「機能性」のものは特徴的な症状から気づかれることも多いですが、非機能性の場合には検診や他の検査で偶然見つかることも少なくありません。
血液・尿検査や、画像診断、病理診断で腫瘍の悪性度や進行度を判断し、根治手術が可能であれば切除による治癒を目指しますが、進行例では集学的治療を行い疾患のコントロールを目指します (参考文献 2, 3) 。
神経内分泌腫瘍の原因
神経内分泌細胞は、ホルモンや神経伝達物質といった体の働きを調節する物質を作る細胞です。これらの細胞は、膵臓や消化管、肺、副腎などの臓器に幅広く存在します。何らかのきっかけで、これらの細胞が無秩序に増殖するようになると神経内分泌腫瘍になります。神経内分泌細胞は全身に存在するため、様々な部位に神経内分泌腫瘍ができることがありますが、消化器に発生するものが全体の 60%、他には肺や気管支といった呼吸器にできるものが 30% を占めています (参考文献 1) 。
神経内分泌腫瘍は2000年あたりまで「カルチノイド」と呼ばれていました。カルチノイドは「がんもどき」という意味ですが、カルチノイドと分類されていた腫瘍でも遠隔転移をする例が少なくなく、「がんもどき」だと誤ったイメージを持ちかねないということで神経内分泌腫瘍と名前が変わった経緯があります (参考文献 1) 。
配信: Medical DOC