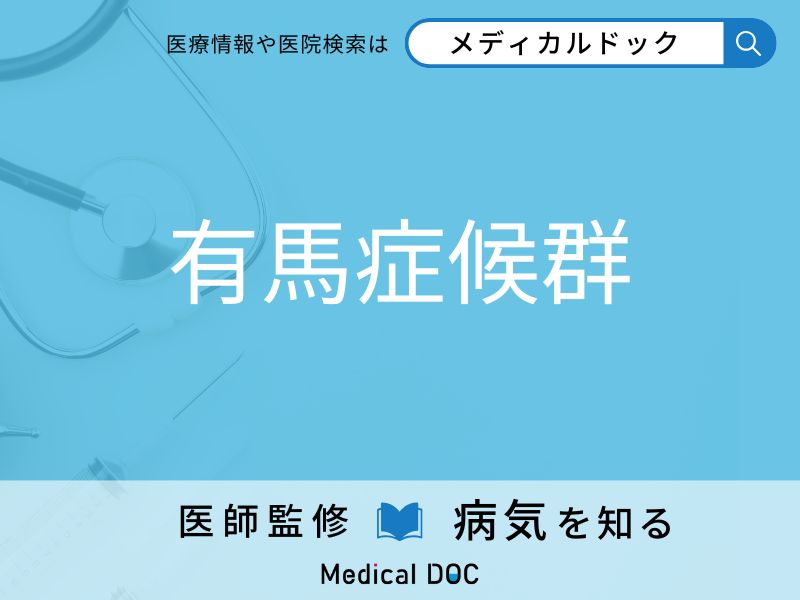監修医師:
本多 洋介(Myクリニック本多内科医院)
群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。
有馬症候群の概要
有馬症候群は、1971年に有馬正高によって報告された極めてまれな遺伝性疾患です。
日本では約10人程度の患者がいると推定されており「CEP290」という遺伝子の変異が原因であるとされていますが、具体的な発症メカニズムは未だ解明されていません。
出典:難病情報センター「神経系分野|有馬症候群(平成23年度)」
有馬症候群の特徴は、乳児期早期から現れる重度の精神運動発達遅滞、網膜欠損による視覚障害、のう胞腎(腎臓にのう胞ができる症状)、眼瞼下垂(上まぶたが垂れ下がる症状)、小脳虫部(小脳の中心部)の欠損、脳幹の形成異常です。
これらの症状は患者の生活に重大な影響をおよぼし、適切な治療がおこなわれない場合、多くは腎不全により小児期までに死亡します。
画像検査や尿検査などによって、上述した症状や所見を確認することで有馬症候群の可能性が疑われます。
現在のところ根本的な治療法は確立されておらず、対症療法が中心となります。
特に腎機能障害に対する早期の対応が重要で、状況によっては透析や腎臓移植が必要となることもあります。
また、精神運動発達遅滞に対しては、早期からの理学療法を中心とした療育が重要な役割を果たします。
近年では、適切な治療と管理により成人まで生存する例も報告されており、患者の生活の質向上に向けた取り組みが続けられています。

有馬症候群の原因
有馬症候群は、CEP290遺伝子の変異によって引き起こされます。
遺伝子の変異が症状を引き起こす具体的なメカニズムについては、現在も完全に解明されていません。
しかし、遺伝子の変異が細胞表面の繊毛の形成や機能に障害を与え、それがさまざまな臓器の発達や機能に影響をおよぼしている可能性が指摘されています。
配信: Medical DOC