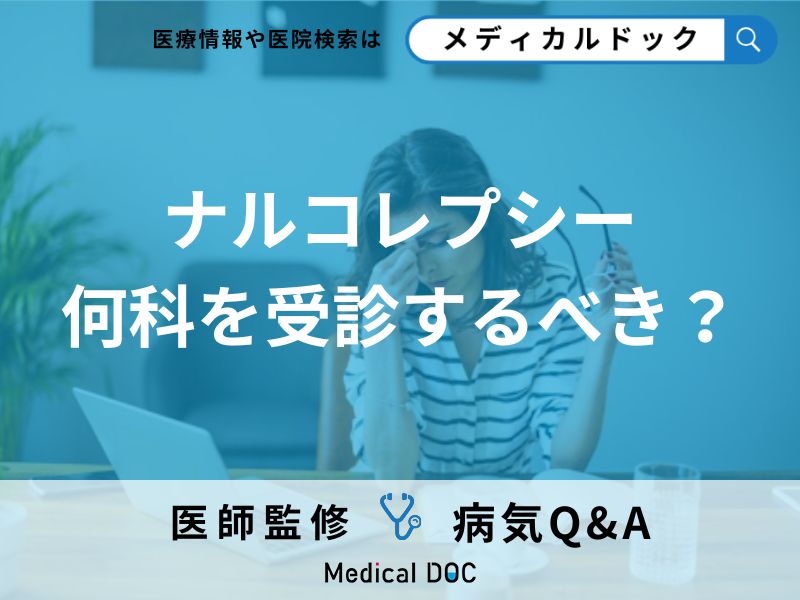日中の過度な眠気や、感情が高ぶったときに身体が急に脱力してしまう症状は、ナルコレプシーかもしれません。ナルコレプシーは、睡眠と覚醒のメカニズムがうまく機能せず、日常生活に支障をきたす睡眠障害の一つです。
本記事ではナルコレプシーは何科を受診するべきかについて以下の点を中心にご紹介します。
ナルコレプシーについて
ナルコレプシーと似ている病気
ナルコレプシーが疑われる場合に受診する診療科
ナルコレプシーは何科を受診するべきかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
≫「ナルコレプシーの症状」はご存知ですか?発症しやすい年齢層も解説!【医師監修】

監修医師:
日浦 悠斗(医師)
福井大学医学部卒業。血清蛋白質と精神疾患の関係について研究をおこなう。日本精神科学会専門医。
ナルコレプシーとは

ナルコレプシーはどのような病気ですか?
ナルコレプシーは、睡眠調節障害を特徴とする慢性的な神経疾患で、居眠り病とも呼ばれます。
思春期から30代までに発症する傾向があり、男女差はありません。日本では、約600人に1人の割合で発症するとされています。
ナルコレプシーには1型と2型の2種類があります。
1型ナルコレプシーでは、強い眠気に加えて、感情の高ぶりによって突然筋力が抜ける情動脱力発作が起こります。
一方、2型ナルコレプシーでは、脱力発作は見られませんが、強い眠気に悩まされます。
ナルコレプシーの原因を教えてください
ナルコレプシーの正確な原因はまだ解明されていませんが、脳内の覚醒を調節するオレキシンという物質の欠乏が大きく関与していると考えられています。
オレキシンは、私たちの脳を覚醒した状態に保つ役割を果たしますが、ナルコレプシーの患者さんではこの物質を作る神経細胞に異常があり、髄液中のオレキシン濃度が低くなっています。
また、遺伝的な要因に加え、ストレスやウイルス感染、頭部外傷、大出血、手術、睡眠不足などの外的要因が発症の引き金になることがあります。
なかには、大きな身体的・精神的ストレスがかかった直後に発症するケースもあるようです。
ナルコレプシーの症状を教えてください
ナルコレプシーの主な症状は以下が挙げられます。
・日中の過度の眠気:
会議やデスクワーク中だけでなく、散歩や会話の最中でも突然眠気が襲います
・睡眠発作:
短時間(約5〜15分)の居眠りで、目覚めた直後はスッキリしますが、すぐにまた眠くなることが特徴です
・情動脱力発作(1型):
笑う・驚く・怒るといった強い感情の変化により、突然身体の力が抜けます
・睡眠麻痺(金縛り):
眠りにつく際に全身の脱力が起こり、一時的に体を動かせなくなることがあります
・入眠時幻覚:
眠りに入る際に、実際には存在しないものが見えたり、音が聞こえたりすることがあります
・夜間の睡眠障害:
頻繁な覚醒や、鮮明で恐ろしい夢を見ることが多く、睡眠の質が低下します
これらの症状はすべての患者さんに現れるわけではありませんが、日中の過度の眠気はほぼすべての患者さんに共通する症状です。
ナルコレプシーを疑ったとき

ナルコレプシーが疑われる場合は何科を受診すればよいですか?
まずはかかりつけ医に相談し、適切な診療科を紹介してもらいましょう。脳神経内科、精神科、心療内科、または睡眠外来の受診をおすすめします。
情動脱力発作がある場合は、てんかんなどの神経疾患との鑑別が必要になるため、より詳しい検査が求められます。また、うつ病や認知症による眠気の可能性もあるため、症状に応じた診察が必要です。
ナルコレプシーの診断には反復睡眠潜時検査(MSLT)が必要ですが、国内では実施できる医療機関が限られています。そのため、日本睡眠学会の専門医療機関(A型)のクリニックや病院への紹介を受けることが望ましいでしょう。
ナルコレプシーは遺伝しますか?
ナルコレプシーは、遺伝性の疾患ではないと考えられています。近親者にナルコレプシーの患者さんがいる場合でも、必ずしも発症するわけではありません。
ただし、ナルコレプシーの患者さんには特定の遺伝的要素が見られるとされています。
例えば、日本人のナルコレプシー患者さんの多くは、HLA(ヒト白血球抗原)遺伝子のDR2が陽性となるケースが多いようです。
また、DR15やDR1の陽性率も高い傾向にあります。
しかし、これらの遺伝的要素を持っていたとしても、必ずナルコレプシーを発症するわけではなく、ウイルス感染やストレスなどの環境要因が発症に影響すると考えられています。
ナルコレプシーと間違いやすい病気を教えてください
ナルコレプシーは、以下の病気と間違われやすいので注意が必要です。
・特発性過眠症
ナルコレプシーと同様に日中の眠気が強く現れますが、情動脱力発作や入眠時幻覚がない点が異なります。
また、短時間の仮眠では眠気が解消されないのも特徴です。
・睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に呼吸が止まることで、夜間の睡眠が浅くなり、日中の過度な眠気を引き起こします。中年以降に発症しやすい傾向があります。
・概日リズム睡眠障害
体内時計が環境の昼夜サイクルと合わないために、昼間に強い眠気を感じることがあります。
・むずむず脚症候群
夜間に脚の不快感で睡眠が妨げられ、結果として日中の眠気が強くなることがあります。
・起立性調節障害(OD)
血流調節の問題により、朝に強い眠気を感じやすくなります。思春期に多くみられるとされている疾患です。
・うつ病
うつ病の症状として日中の眠気が現れることがあります。また、不眠による影響で日中に眠気を感じる場合もあります。
配信: Medical DOC