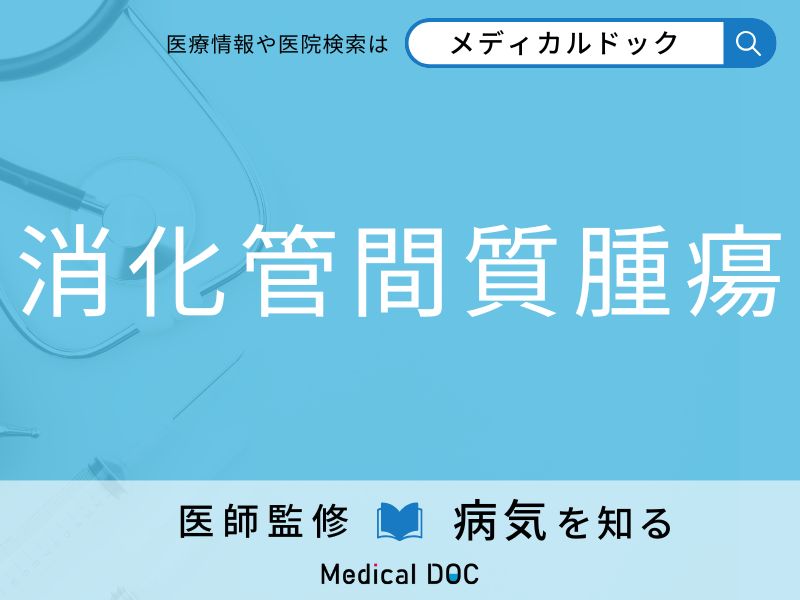監修医師:
大越 香江(医師)
京都大学医学部卒業。大学病院での勤務を経て、一般病院にて大腸がん手術を中心とした消化器外科および一般外科の診療に従事。また、院内感染対策やワクチン関連業務にも取り組み、医療の安全と公衆衛生の向上に寄与してきた。女性消化器外科医の先駆者として、診療や研究に尽力している。消化器疾患の診療に関する研究に加え、医師の働き方や女性医師の職場環境の改善に向けた研究も行い、多数の論文を執筆している。日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医。
消化管間質腫瘍の概要
消化管間質腫瘍(Gastrointestinal Stromal Tumor;GIST)は、胃や小腸などの消化管壁に発生する悪性腫瘍の一種であり、「肉腫」に分類されます。
この腫瘍は消化管のペースメーカー細胞「カハール介在細胞」から発生するもので、粘膜から発生する胃がんや大腸がんとは異なる性質を持ちます。GISTは粘膜下に腫瘤を形成し、腫瘤が粘膜を下から押し上げるような形で発生します。
発生部位は胃が最も多く、全体の60~70%を占め、次いで小腸、大腸の順で発生します。食道での発生は稀です。
GISTの発症率は年間10万人あたり1~2人程度とされる稀な疾患であり、手術症例では胃がんや大腸がんの100例に対して1~2例程度と報告されています。性別による発症率の差はなく、ほとんどの年齢層で見られるものの、中高年、特に60歳代に好発します。
GISTは消化管壁に発生する腫瘍ですが、粘膜下に形成される良性の腫瘍として平滑筋腫や神経鞘腫、悪性の平滑筋肉腫などがあります。このため、診断には注意が必要です。
消化管間質腫瘍の原因
GIST(消化管間質腫瘍)は、腫瘍細胞の細胞膜に存在するKITまたはPDGFRαという蛋白の異常が主な原因で発生するとされています。この蛋白は通常、特定の物質から刺激を受けたときにのみ細胞増殖を促す役割を果たします。しかし、異常が生じると、常に増殖の合図を出し続けるようになり、その結果、細胞が制御不能に増殖して腫瘍が形成されます。この状態を放置すると、腫瘍はさらに大きく成長し、周囲の組織や臓器に影響を及ぼす可能性があります。
GIST 症例の多くはc‒kit, PDGFRA 遺伝子の体細胞変異により単発するのですが、家族性、症候性にGIST が多発することもあります。例えば、c‒kit 遺伝子の生殖細胞レベルでの変異を原因とする多発性GIST 家系や神経線維種NF1型の患者さんの一部にGIST を合併することが報告されています。
配信: Medical DOC