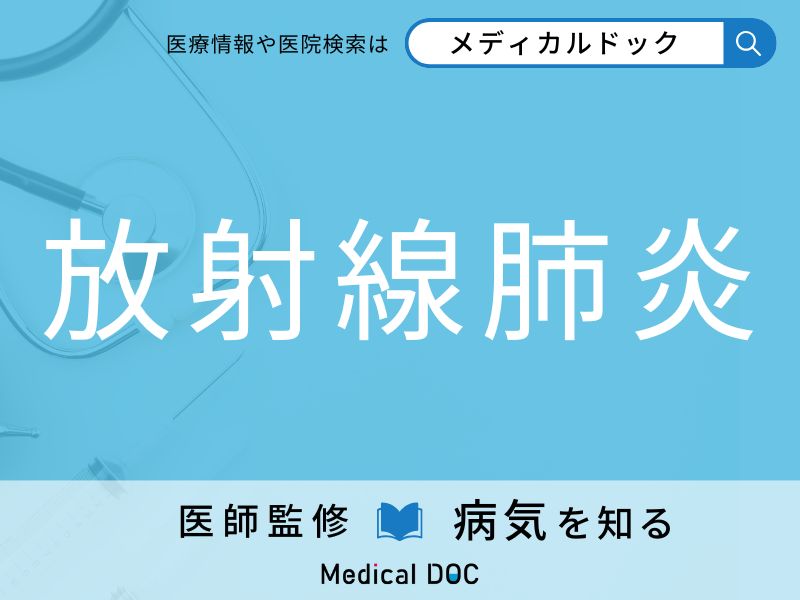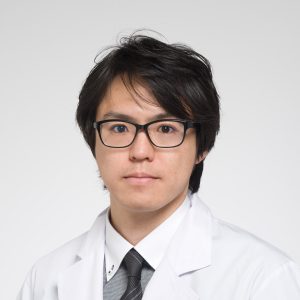
監修医師:
林 良典(医師)
名古屋市立大学卒業。東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科を経て現職。診療科目は総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科。医学博士。公認心理師。日本専門医機構総合診療特任指導医、日本老年医学会老年科専門医、禁煙サポーター。
放射線肺炎の概要
放射線肺炎(radiation pneumonitis)は、放射線治療後に発生する、肺に炎症が生じる疾患で、放射線が肺の正常な組織を損傷することによって引き起こされます。
この疾患は、肺が放射線治療の対象範囲に含まれる患者さんにみられる副作用であり、主に乳がん、肺がん、食道がんなど胸部の治療を受けた患者さんに生じることがあります。
放射線肺炎は、治療終了後4〜12週間の間に発症することが多く、多くの場合は軽症で、軽症の場合は経過観察で改善しますが、重症化する兆候がある場合は早期に適切に対応する必要があります。重症化すると入院が必要になったり、慢性的な肺線維症へ進行し、在宅酸素が必要になったりするなど、生活への影響が大きくなる可能性があります。この病気は放射線治療の有用性やその後の治療の機会を損なう大きな要因となり得るため、適切な治療を受けることが重要です。
放射線肺炎の原因
放射線肺炎の主な原因は、放射線が肺の正常な組織に与える損傷です。この影響は細胞レベルでの炎症反応を誘発し、最終的に肺組織に障害を引き起こします。具体的には以下のような原因が考えられています。
放射線による直接損傷
放射線はDNAに直接損傷を与え、細胞死を誘発します。正常な肺細胞もこの影響を受け、正常な組織に戻っていきますが、この修復過程で炎症が起こります。
免疫応答の活性化
放射線による損傷に反応して、サイトカインやケモカイン(炎症性物質)が放出され、炎症が拡大します。これにより、肺組織が浮腫や線維化を起こす可能性があります。これは肺炎を起こすばかりでなく、がんに対する免疫も活性化するとされています。これを応用して放射線治療後にデュルバルマブと呼ばれる免疫療法を行うことで治療成績が改善することが明らかになっています。
線量依存性の影響
放射線の総線量、1回あたりの線量、照射範囲が広いほどリスクが高まります。また、正常な肺組織が照射範囲に多く含まれる場合、発症率が上がります。
併用治療の影響
化学療法と放射線療法を併用する場合、放射線による損傷が増幅されることがあります。特に特定の抗がん剤(例:タキサン系薬剤)が肺に与える毒性は注目されています。
配信: Medical DOC