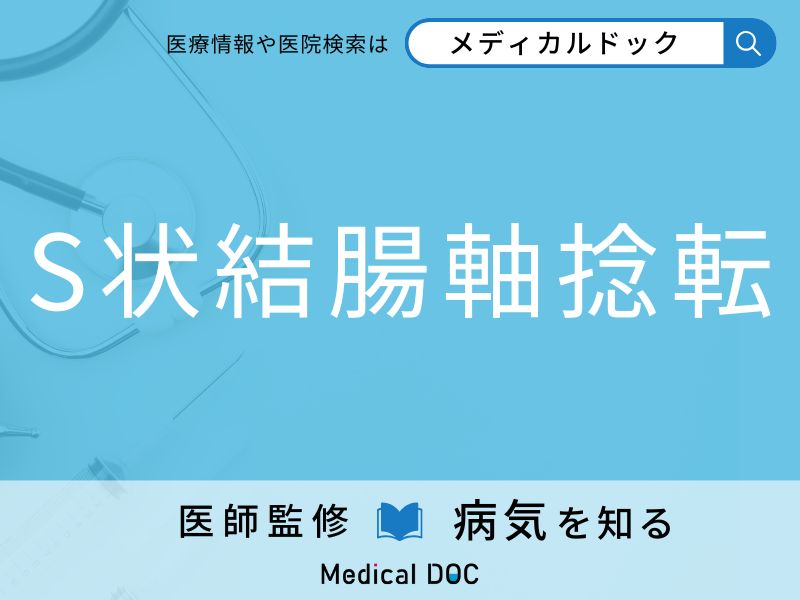監修医師:
大越 香江(医師)
京都大学医学部卒業。大学病院での勤務を経て、一般病院にて大腸がん手術を中心とした消化器外科および一般外科の診療に従事。また、院内感染対策やワクチン関連業務にも取り組み、医療の安全と公衆衛生の向上に寄与してきた。女性消化器外科医の先駆者として、診療や研究に尽力している。消化器疾患の診療に関する研究に加え、医師の働き方や女性医師の職場環境の改善に向けた研究も行い、多数の論文を執筆している。日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医。
S状結腸軸捻転の概要
結腸軸捻転症は結腸がねじれてしまうことで、結腸が物理的に閉塞した状態です(機械的腸閉塞)。主にS状結腸で発生し、これをS状結腸捻転と呼びます。発症率は機械的腸閉塞の3.7~8.7%とされ、患者さんの30~47%が70歳以上の高齢者です。
本症の基本的な病態は腸閉塞であり、血流障害を伴わない場合もありますが、絞扼性腸閉塞を引き起こす場合も少なくありません。主訴としては腹部膨満が最も多く、腹痛や嘔吐を伴うこともあります。
血流障害がない場合の治療は、大腸内視鏡による腸管ガス吸引と整復術が第一選択となります。しかし、再発率が高く(30~90%)、待機的なS状結腸切除術が推奨されます。一方で、内視鏡的整復が不可能な場合や絞扼性腸閉塞、腸管壊死、敗血症、穿孔、腹膜炎が疑われる場合には、腸管切除を含む緊急手術が必要です。治療の際には腸管虚血や穿孔のリスクを常に評価し、手術適応を考慮しながら治療方針を決定することが重要です。
本疾患は、迅速な診断と早急な治療方針の判断が求められる救急疾患です。日本では高齢化が進んでいるため、今後も増加が予想される疾患の一つといえます。内視鏡による捻転解除術が治療の主軸となりますが、強い挿入や無理な捻転を避けるなど、安全な手技が求められます。
S状結腸軸捻転の原因
S状結腸は後腹膜に固定されておらず、腸管が自由に動きやすい構造をしています。そのため、ほかの部位の結腸に比べて捻転が起こりやすい特徴があります。特にS状結腸では、腸管がループ状にたわみやすく、この「たるみ」がある状態を「係蹄が緩い」と表現します。このように腸管がたわんだ状態だと、腸管の一部が回転しやすくなり、捻転のリスクが高まります。
さらに、S状結腸が長すぎる(過長)場合や、便秘による腸管の拡張、腸の筋肉の緊張が低下することも捻転を引き起こしやすい要因となります。高齢男性、脳血管障害や精神神経疾患を持つ人、長期臥床している人、向精神薬や抗痙攣薬、大腸刺激性下剤などを使用している人も、この疾患のリスクが高いとされています。便意や痛みを感じにくいことから精神疾患の患者さんにも多くみられるようです。精神疾患以外で合併する頻度の高い病気としては、パーキンソン病などの神経疾患、巨大結腸症の原因となる病気、脳疾患、脊髄の損傷などが挙げられます。そのほか、手術治療後の臓器の癒着や妊娠が原因となって生じる場合もあります。
これらの要因を持つ場合、S状結腸軸捻転症の発症に注意が必要です。
配信: Medical DOC