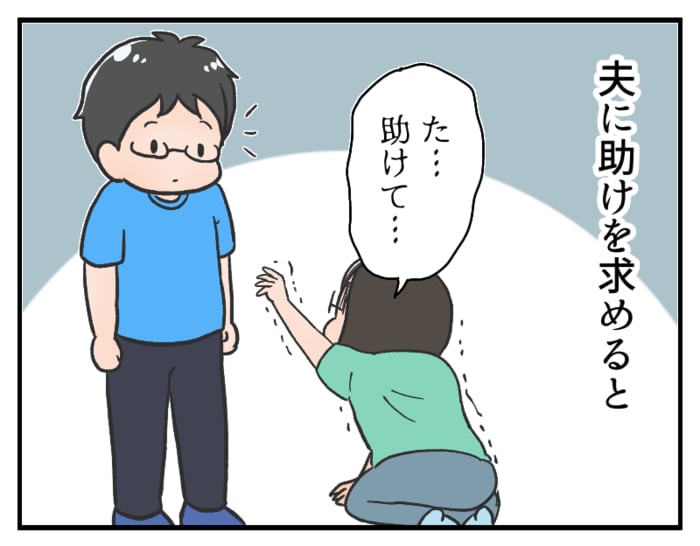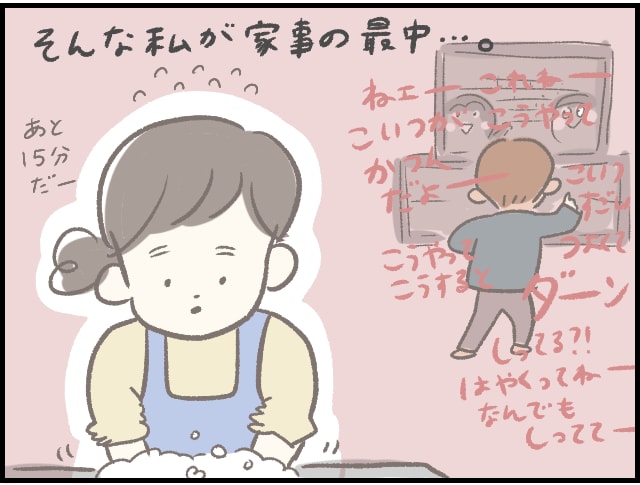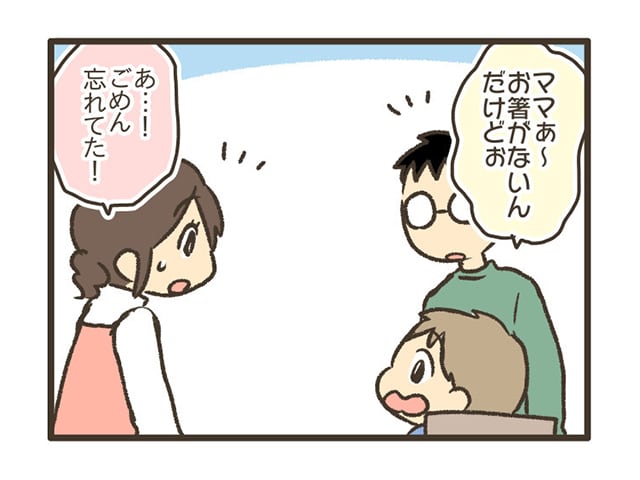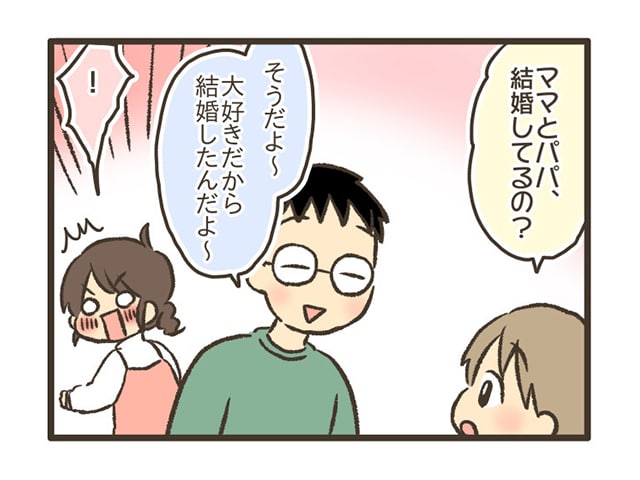この春小6になる長女はこの春休み、オーストラリアの親戚の元で過ごしていた。
約10日間の滞在は長女にとっても、私たち夫婦にとってもそれは刺激的な時間だった。
長女にとって、オーストラリアへ行くのは1年前からの念願で、現地で暮らす夫の姉一家と自らコンタクトをとり、今か今かと時期を計っていた。
夫の母が帯同してくれることになり、胸をぱんぱんに膨らませて旅立ったのが春休みの初めのころ。
長女がいない隙間を持て余して落ち着かない最初の夜を過ごす我々の元には、「さみしい」「眠れない」と泣き言が送られてきていた。
ああ!抱きしめたい。
2歳だったあの頃みたいに抱っこして添い寝してあげたい。
小さかった長女の柔らかさを思い出して、胸がぎゅっとなる。
ところが、そんな夜も最初の2日間だけで、そこから少しずつ長女からの連絡は減り、代わりにあちらのご家族から楽しそうな長女の様子が送られてくるようになった。
ああよかった、と思うと同時にとんでもなくもてなされている長女の様子に目を見張る。
長女が、めちゃくちゃに可愛がられている。
夫の姉からは「天使!!!!毎日、癒されてる!!!」とメッセージが届き、姪っ子たちからはご馳走を前にした長女の写真が毎食のように送られてきた。
夫の姉夫婦は現地で評判の飲食店を経営しており、食べることにも作ることにも大変精通しているのだ。
大きなお皿の真ん中にソテーされたなにかがちょこんと乗っていて、横にスラーっと乳白色のソースが弧を描いている。
そんな写真がいくらでも届く。
こんなの結婚式でしか食べたことがないですよ、というお料理が毎日、いや毎食長女の前に運ばれていた。
これは……??
プリンセス??
王族???
国賓??????
お母さん、その三段重ねになったお皿に小さなケーキやサンドイッチが乗ったやつ、テレビか絵本でしか見たことがないですよ。
こんなありがたいことってあるんだろうか。
辺鄙な片田舎に暮らす小学生がこんな贅沢をしているという事実、完全に漫画であるよ。
突然なんらかの事情で都会にぽつんと放り出されて目くるめく世界に目を白黒させる、あれじゃないか。
ちっぽけだった毎日ががらりと変わる、あれじゃないか。
恵まれすぎていて、毎日スマホの画面を拝むような気持ちで見つめていた。
きらびやかなご馳走の写真を見るたびに、「こんな世界があるのか」と信じられない気持ちになった。
寂しかった旅の始まりはあっという間に「おいしい」に塗り替えられ、送られてくる写真の中の長女は弾ける笑顔に変わっていった。
今回ほど、長女が食いしん坊でよかったと思ったことはない。
そう、長女は極度の食いしん坊なのだ。
あれは長女がまだ3歳だった頃。
テレビの録画リストを器用に操作してなにかを探していた。
聞けばつたない言葉で「桃みたいなのを食べてるやつ」と言う。
心当たりがないなりにあれこれと探しに探して、ようやく見つけたのはいつか録画した海外アニメのおまけコーナーだった。
異国の子どもがプラムのようなものをかじるほんの5秒ほどのシーンを見つけるや
「これ!」
長女は歓喜した。
以降そのシーンを何度も繰り返して観ては
「これはなんなの?」
「固いの?」
「甘いの?」
「食べてみたい。どうしたら食べられる?」
長女は疑問を口にし、私は「外国の果物だなんだろうねぇ」、「そういえば外国の桃は固いって聞いたことがあるよ」などと、その場その場で知っていることをなんとなく答えたり、「そうだね、食べてみたいね」と共感したりした。
そのしばらく後、長女のハートを鷲掴みにしたのはサボテンだった。
鑑賞することでしかその存在を知らないサボテン。
これまた海外のとある映画のワンシーンで、サバンナで暮らす少年がサボテンの実をもいで妹に差し出し、妹は美味しそうに汁を滴らせてサボテンを食べるというもの。
こちらもまた、長女は何度も巻き戻してはそのシーンに釘付けになった。
そしてその後、何度も「サボテンを食べてみたい」と言った。
そんなふうに、長女が食べたがったまだ見ぬものは数知れない。
あるときは豚足を食べたいと言い、またあるときはザクロを食べたいと言った。
最近では本で見たらしいグミの実を食べたがっている。
蜜が甘いといわれる花なんてもちろんすぐ口に入れるし、香りのいい草を見つければお茶にできないかと調べている。
彼女の旅を支えたのは間違いなく、食欲だった。
食べる楽しみがあれば旅は楽しい、ということをしみじみと思った。
食の知識が豊富な夫の姉一家にとって、長女はまさに食べさせ甲斐のある客人であり、シェフである義姉の夫は毎日夕食の時間に腕を振るうのを楽しみにしてくれていたそうだ。
夫の姉一家による極太のホスピタリティにより、長女は美味しい旅を隅々まで堪能した。
ほんとうになんの曇りもない、充実した10日間だった。
帰国した長女はなんだか少ししゃんとして、気のせいではなく自信に満ちていた。
甘えん坊な長女だから、帰国したらもっとまとわりついてくるかと思ったのに、澄ました横顔で微笑んでいる。
どこか幼かった長女がほんの少し、お姉さんになっていた。
知らない町に飛び込んだこと、初めてなものをたくさん食べたこと、慣れない家族と密に過ごして大切にしてもらったこと、思いを巡らせるほどすべての時間が贅沢で尊い。
「毎年行く!次は私が案内するね」
と得意げに微笑む長女は確かに発光していた。
そうか、子どもは私の知らないところへ行くたびに、こうしてうんと大きくなるのか、と子育ての理のかけらを見たような気がした。
長女に「オーストラリアでなにが一番楽しかった?」と尋ねると「Kくん!」と義姉の夫の名前を言った。
「どういうこと?」「Kくんのお料理がどれもすっごくおいしかった!」
とやはり、食いしん坊な答えが返ってきた。
一応念のため書くけれど、「なにがおいしかった?」とは訊いていない。
オペラハウスで鑑賞したオーケストラよりも、コアラよりも、青い海よりも、やっぱり長女は「おいしい」だった。
いっそ、このぶれない強い芯でどんどん広い世界を見てほしい。
ちなみに、あの幼かった長女が見た「桃のような果物」をめでたくオーストラリア旅行で食べることが叶ったらしい。
まだ忘れていなかったことに驚いて思わず笑った。


 ハネ サエ.
ハネ サエ.
 ハネ サエ.
ハネ サエ.