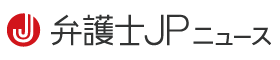TBS系日曜劇場『アンチヒーロー』は、長谷川博己演じる弁護士・明墨正樹(あきずみまさき)が、どんな疑わしい人物でも手段を選ばず“無罪”にする異色のリーガルドラマだ。
こうした専門的な職業が登場するドラマに欠かせないのが“監修”。リアリティとドラマとしての面白さを両立させるために、監修という仕事は近年重要さを増している。そこで、本作で法律監修を担当している國松崇弁護士に、その重要性と仕事の魅力について話を聞いた。
法律監修の仕事とは
『アンチヒーロー』での法律監修は、具体的にどんなことをされているのですか。
國松弁護士:今回のドラマはテーマがテーマですので、企画段階でプロットを見せてもらい、弁護士はこういうことをやっていいか、やるにしてもどこまでなら許されるのかなど、そもそもこの物語がある程度のリアリティを保ちながら成立するのかどうかを具体的にシミュレーションするところからお手伝いしています。
たとえば、物語上は「ここで盛り上げたい」が、それは刑事司法の手続きに則しても無理のないストーリーかどうか? を検討するなどしています。『アンチヒーロー』の主人公である明墨は、きわどいこともやるタイプの主人公ですから、監修は気合を入れないといけないなと思いましたね。
脚本の監修だけでなく、現場の撮影に立ち会って助言されることもあるのですか。
國松弁護士:そうですね。撮影していく中で監督や出演者の皆さんからの提案でアドリブを入れたいということがあったりしますし、特に法廷シーンでは弁護士や検察、裁判官の動きとか喋り方をこの目で見て、「どこまでなら違和感を持たれないか」など、私が現場について相談に乗っています。
しかし、それでもドラマと現実には違いがあります。現実の法廷で弁護士は動き回らないけど、役者さんや監督は動きで表現したいものですから、どんな動きならおかしくないかを助言します。たとえば、証人に必要以上に詰め寄る、傍聴席に向かって何か言う、裁判官に食ってかかるといった出来事は現実の法廷ではあまり起きませんが、そういう時も裁判官に注意させる、刑務官に止めに入らせるといった形で、周囲のリアクション、いわゆる「受け」の演出に一工夫加えてもらったりして、視聴者にも違和感なく受け止めてもらえるようなアイディアを現場で出していきます。

ドラマならでは? 法廷内を歩き無罪を立証していく明墨弁護士(©TBS)
なるほど。映像作品ならではの悩みですね。明墨(長谷川博己)は法廷でノーネクタイですけど、そういう弁護士はいるんですか。
國松弁護士:夏場なら普通にいますよ。完全に私服の人はあまり見ませんが、オフィスカジュアル程度の服装ならちらほら見かけます。さすがにノーネクタイでダボッとしたスーツをオシャレに着こなす弁護士、というのはなかなか突飛な設定ではありますけど、絶対いないわけじゃないかなというぐらいの感じですね(笑)。
監修者も気になるドラマへの反応
監修としてかかわった作品で、一般の方や同業者の反応はやはり気になりますか。
國松弁護士:それはもちろんありますね。私は専門家として法律や実務に基づいた助言を出しますが、最終的には、いろいろなバランスを見ながら監督を中心とした制作陣が判断していくわけです。制作陣がやりたいことをきちんと理解した上で、具体的な表現の違和感のレベル感を伝え、「とことんリアルに行くか」、「あえて非リアルを飲み込んでエンタメに振っていくか」、その選択肢を提供するのが私の仕事だと思っています。「エンタメとしてどう見せたいか」と「法律のリアル」、その塩梅には常に気を配っています。
やっぱりポジティブな意見をいただければ嬉しいですが、同業者からの指摘も勉強になりますし、次の場面に活かそうと肯定的に受け止めるようにしています。
先生が番組制作に関わるようになった初期のころ(2014年頃)と比べると、SNSなどの普及で一般の方はもちろん、さまざまな専門家からも意見が出やすい状況になっていると思います。監修に対するテレビ局側の意識の変化はありますか。
國松弁護士:昔と比べると意識は高くなっていると思います。ドラマ制作の方たちは、当然「これはあくまでフィクション」という意識を持っているとは思うんですけど、一方でSNSでさまざまな意見が可視化され、それがドラマの評判、ひいては役者さんの評判にもつながりかねないわけですから、エンタメを大事にしつつ、一方であまりに設定が破綻しないようにバランスを調整しようと考える傾向になってきていると思います。最近はバラエティ番組、特に情報系の番組でも監修を入れるケースが増えています。

緑川(木村佳乃・右)、菊池(山下幸輝)ら検察官の所作にもリアリティがある(©TBS)
正しい情報が出ることは良いことですが、作る方は大変になっているわけですね。
國松弁護士:そうですね。法律監修、医療監修などはもはや定番になりましたが、今は料理監修とか他にもいろいろな監修があります。『アンチヒーロー』も法律監修、警察監修、医療監修、刑務官監修などが入っています。刑務官監修は手錠のかけ方とか、腰縄のまき方などを監修されているみたいですよ。
「エンタメの現場」弁護士としても勉強になる
國松弁護士は、もともとTBSの社員として監修の仕事をするようになったそうですね。TBSにはどのような経緯で入社されたのですか。
國松弁護士:弁護士になるために司法修習を受けていたころ、自分が興味のあることを改めて振り返ったら、昔からエンタメやメディアの世界に憧れがあったことを思い出しました。当時は弁護士の数が増えて、従来の法律事務所などはいわゆる“買い手市場”になっていて、その結果、法律事務所以外にもさまざまな就職の選択肢が開拓されていったんですね。そんな中、弁護士としてエンタメやメディアの世界に関わっていきたいなら、いっそのこと「テレビ局で働けたら面白いかもしれないな」と思ったんです。
それで、モノは試しだということでいろんなテレビ局に直接電話して、「話をさせてください」とダメ元でお願いしてみたところ、たまたま手が空いていたのか、TBSだけが人事の社員さんに電話をつないでくれたんです。その社員の方は後日、対面でもいろいろと話を聞いてくれました。もちろん、それがそのまま採用に繋がったわけではありませんが、私としては熱心に耳を傾けてくれたTBSにぜひ入ってみたいと思いましたし、その後、法務部員をキャリア採用するという話を聞いて、迷わず応募しました。その結果、TBSのインハウスローヤー(※)第一号として、著作権や契約法務を担う部門に就職することになりました。
※一般企業に従業員として雇用され、法務関連業務等に携わる弁護士のこと。
同期入社にドラマ部に配属された社員がいるんですが、助監督をしている新ドラマの中にいろいろと法律が出てくるが、調べてもよく分からない……という状況になったようで、「そういえば同期に弁護士がいたからちょっと聞いてみるか」ということで相談を受けたのが最初のきっかけです。そこから裏方的にいろいろとアドバイスをしているうちに、じゃあ本格的に脚本のチェックも頼めないか? ということになり、そこから法務の仕事と並行して、徐々にドラマの監修も仕事として頼まれるようになりました。
実際にドラマの仕事をしてみてやりがいは感じましたか。
國松弁護士:弁護士に依頼する人は「こういう請求がしたい」「こういう風にされたくない」など、いろいろな思いを持っていますが、同様に役者や脚本家、監督にも「物語をこうしたい」という思いがあります。
依頼人の場合は相手方や裁判所へ、ドラマの作り手の場合は視聴者へ、ということで、思いを届けたい先はそれぞれ異なりますが、自分の思いをどう具現化して“いかに届けるか”を考えるという点では、両者はとても似ていると感じています。
こう説明すれば、こういう反応になるのかと視聴者の反応を見て勉強になりますし、一般の方が裁判や弁護士の仕事に対してどんなイメージを持っているのかなど、実際の我々の仕事の中でも参考になることが多いです。

明墨のもとで働く赤峰(北村匠海)と紫ノ宮(堀田真由)両弁護士。監修は“役”も支えている(©TBS)
実務に活かせることを、エンタメから学べることもあるのですね。
國松弁護士:参考になると思う瞬間はいっぱいあります。先ほど法廷で動き回る弁護士は少ないとお話ししましたが、裁判員制度が始まってからは、あえて法廷内で立ち回る弁護士がちょっと増えた実感があります。それは、裁判員という一般の方を相手にプレゼンテーションするという要素が必要になったからです。
弁護士会などの組織の中でも、どう表現すればより裁判員に思いが伝わるのかを実践的に研究するグループがあったりしますが、そういう時にドラマの見せ方が参考になることはあると思います。どんな言葉で、どんな所作をすれば説得力が増すのか、より感情に訴えかけられるのかといったことは、まさに役者さんが体現されていることですよね。
法曹界を目指す人でも、エンタメの世界を一度体験してみると思わぬヒントがあるかもしれないですね。
國松弁護士:そうですね。なによりプロの仕事を間近に見られるのは刺激にもなり、それが監修の仕事の醍醐味でもあるかもしれません。
最終的には、私が監修したドラマを通して、それまで法律に興味のなかった人が興味を持ったり、「弁護士になりたい」と思ってくれれば最高に嬉しいです。