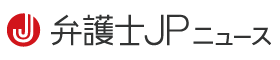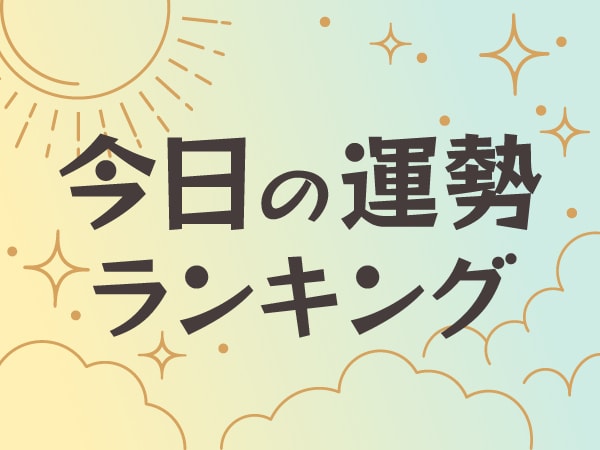米大リーグで活躍する大谷翔平選手の銀行口座から元通訳の水原一平被告が“ギャンブル”に使用するために不正送金を行っていた事件は国内外に大きな衝撃をもたらした。
しかし、ギャンブルのために罪を犯した人は水原被告以前にも多くいる。公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」が発行する「ギャンブル等の理由で起こった事件簿(平成第3版)」には、平成以降に起きたギャンブルを動機とした横領、強盗、窃盗、詐欺等の事件699件が記録されている。
社会的なリスクをはらむ「ギャンブル依存症(病的賭博)」について、厚生労働省は2017年に実施した調査から、成人の3.6%、推計320万人にギャンブル依存症の疑いがあるという推計を発表している。
この連載では、会社員のセイタ(28)がギャンブルに飲み込まれていく様を追体験する。第2回では、セイタが「ダサい」と思っていたパチンコにのめり込んでいく様子が描かれる。(#3に続く)
※この記事は染谷一氏の著書『ギャンブル依存 日本はなぜ、ギャンブル依存が深刻なのか。』(平凡社)より一部抜粋・構成。
厳格な両親のもとで
セイタが生まれ育ったのは、中国地方の県庁所在地。厳格な親のもと、高校を卒業するまでは典型的な「良い子」だった。もともと足が速く、小学2年生からは地元のクラブチームでサッカーを始めた。英国プレミアリーグ「アーセナル」で活躍していたティエリ・アンリ選手にあこがれ、自身もフォワードとして、チームの前線を担った。相手ディフェンスと1対1で勝負するときの興奮が大好きで、味方からパスが回ってくると、「絶対に決めてやる」と闘志に火がつく。生まれついての負けず嫌いだった。
学校の成績も上々だった。中学受験になると、県内有数の中高一貫校に合格し、親の期待にしっかりと応えてみせた。中高6年間を通じて、サッカー部の熾烈なレギュラー争いに明け暮れながら、親の言いつけに従って、合間にきちんと塾通いも続けた。文武両道の優等生。
学校や塾への行き帰りに、パチンコ店から出てくる人たちを見ると、「バカなことをやっているな。自分とは生きている世界が違う」と、軽蔑の視線を浴びせる側にいた。
さほど必死に勉強をした自覚はないが、大学入試になると、関西の有名大学法学部の合格通知をきっちりと勝ち取っていた。
ギラギラした都会での生活が
大阪での大学生活がスタートした。初めての一人暮らし。ほどほどに勉強をしながら単位を稼ぎ、彼女をつくったり、海外旅行に行ったりして、4年後には就職……。そんな当たり前の未来図しか思い描いていなかった。
大都会はまぶしかった。セイタが育った地元にもそれなりの活気はあったが、大阪のスケールは桁違いだった。表通りには、キラキラと華やかに着飾った男女が行きかい、裏通りに回ると、一転、ギラギラと黒光りする欲望があちこちにしみついていた。未知の刺激に満たされた世界で、親の目が届かない解放感。少し前までは、親元で多少の息苦しさを当たり前に受け入れていた18歳の周囲に、いきなり無限の自由が広がった。
経済的な心配はない。マンションの家賃も、当面の生活費も、親が自分の銀行口座に積んでおいてくれた。それでも……。もっとカッコいい洋服を着たい。若い男性に流行していた「クロムハーツ」のアクセサリーも身に着けてみたい。仕送りだけでは、さすがにそこまでの余裕はなかった。もうちょっとだけお金があれば――。そう考えていたら、すぐに居酒屋のアルバイトが見つかった。
10代の若者が、慣れない大都会に出てくれば、最初に孤独感を感じ、次にそれを払拭できるかの不安を覚える。セイタも例外ではなかったが、バイト先の先輩たちは、にぎやかに自分を受け入れてくれた。長い間、サッカーチームに所属してきたにもかかわらず、セイタは自分から人の輪に加わっていくタイプではない。誰かと話をすることは嫌いではないが、かなりの人見知りだった。大学の授業が始まっても、不思議なことに、クラスで一緒になる同級生よりも、バイト仲間たちと一緒にいるときのほうが自然な自分でいられた。
居場所ができた。心強かった。孤独への不安は、日を追うごとに、居酒屋の喧騒にかき消されていった。
都会生活は順調に滑り出した。だが、セイタの「未来」は、思わぬ方向に軌道を変えていた。もちろん、そんなことに気づくはずはなかった。
「ダサい」と思っていたパチンコ店に
バイト先の先輩たちに連れられて、生まれて初めてパチンコ店に足を踏み入れた。高校生までの自分なら、近くに寄ることもない場所だった。セイタの「基準」では、ギャンブルは「ダサい行為」、パチンコ店は「ヤバい場所」だった。それでも、バイト仲間たちとの行動は楽しく、18年間、心に根づかせてきたささやかな規範など、簡単に吹き飛ばされた。むしろ、知らない世界に、胸を高鳴らせている自分がいた。
バイト先の居酒屋には、集団でパチスロをする「チーム」があった。メンバー5、6人で店に出向き、複数の台を試し打つ。設定のよさそうな、つまり「勝てそうな台」を得たメンバーは徹底的に粘り、そうでないメンバーは投資額を最小限に抑えて早々に撤退する。最終的に儲かった人の利益をメンバー間で分配する。セイタも躊躇なくチームに加わった。
パチンコやパチスロの勝ち負けは、ほぼ座った台で決まる。もちろん、多くの台は、店側に有利な調整がされており、客が勝てる台はほんの一握りだ。逆に言えば、どこかに潜んでいる「優良台」を探し当てれば、ほとんど勝ちは確定する。
当時のパチンコ・パチスロには、かつてのプロたちが駆使していた裏技や必勝法はなかったものの、セイタが加わったチームのシンプルな戦術は、意外に利益を生んだ。
なぜか。
ギャンブルは「やめどき」の見極めが難しい。調子が悪く、途中で「このままでは負け戦になる」と感づいても、「報酬期待」で脳内に放出されたドーパミンに理性が支配されて、さらにジャブジャブと資金を突っ込んでしまう。
これがチームとなれば自制心が働く。自分が大負けすれば、チーム全体に迷惑をかける。サッカーと同様の団体競技なのだ。一人がドリブルで突っ走っても、ディフェンスに阻まれればゴールできない。自分に得点のチャンスがなさそうなら、いいポジションにいる味方に攻撃をゆだねることで、ゲーム全体を優位に運べる。ストライカーなんか必要ない。チームが勝てばいい。
情報戦を有利に運べることもチームのメリットだった。新装開店や新台入れ替えなど「勝ちにつながる情報」はメンバーの誰かが必ずチェックし、決して逃さなかった。パチンコ店ごとの設定の傾向や特徴、それに台を管理する店長のクセなども、一人一人が情報を持ち寄り、全員で分析する。
報酬は山分けなので、大きな儲けにはならなくても、チームは着実に勝ちを拾っていた。
月々のバイト代に加え、パチスロの「副業分」がセイタの手元に転がり込むようになった。ほんの数か月前まで心のなかに根づいていたギャンブルの「ダサいイメージ」は、大都会のブラックホールに吸い込まれ、目の前には「自由」と「刺激」、そして「豊かさ」に満ちた空間が広がっていた。
(第3回に続く)