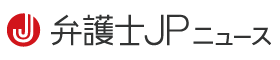東京都世田谷区の自宅で昨年9月末から10月頭にかけ、介護中だった妻(当時85)を殺害し、殺人の罪に問われている吉田友貞被告(80)の初公判が12日、東京地裁で開かれた。
公訴事実について争いはなく、裁判の争点は量刑に絞られている。
仕事で知り合い、1994年に結婚
現在は保釈されており、弁護士とともに法廷へ現れた吉田被告は、黒いスラックスに薄いグレーのジャケットを羽織り、ネクタイをきっちりと締めていた。すらりとした穏やかそうな風貌からは、わずか8か月前に妻を殺(あや)めたことなど想像もできない。
年齢相当の耳の遠さが感じられる場面もあったが、冒頭、裁判長から氏名や生年月日などを確認されると、ハッキリした声で「はい」と答えていた。
都内の百貨店などに勤めていた吉田被告と妻は仕事の関係で知り合い、1994年に結婚した。ふたりの間に実子はおらず、2016年頃、殺害現場となった世田谷区の共同住宅に引っ越してきたという。
妻はこの頃から視力が低下しており、その後悪化。事件当時は「要介護1」に認定され、ほとんど見えていない状態だったという。ふたりの日常生活について、検察側は「トイレや風呂は妻ひとりで入れる状態であり、洗濯や掃除も多少はできていた」と主張。一方、弁護側は「(吉田被告が)妻の髪の毛を洗ったり、トイレの介助をしていたほか、毎日妻のために足湯を用意したり、妻の好みに合った食事を用意したり、通院の付き添いなどもすべてひとりで行っていた」と説明した。

裁判長の質問に答える被告(画:Minami)
徘徊し、近隣住宅のインターホンを…
目の問題に加えて、妻は事件の数か月前に精神疾患を発症。神経症・うつ状態と診断された。
この頃から、妻は地域の高齢者支援センターで「死にたい」「死んだほうがまし」などと発言するようになったという。徘徊(はいかい)も始まり、近隣住宅のインターホンを押して回る、上がり込んで近隣住民相手に支離滅裂な話を長時間続けるなどの行動も目立つようになる。さらには被害妄想も激しくなり、「財布を盗まれた」「夫が浮気している」などと繰り返し主張していたという。
このような状況から、被告はそれまで従事していたシルバー人材センターの仕事を辞め、妻を付きっきりで介護するようになった。妻は人の好き嫌いが激しかったため、ヘルパーには散歩の同行だけを手伝ってもらっていたそうだ。
なお、妻が発症した精神疾患には通院や入院による治療が必要だったものの、妻がこれを拒絶したため実現せず、訪問診療で対応することとなった。
これらは弁護側の冒頭陳述だけでなく、近隣住民やたびたび訪れていたヘルパーらからの証言としても紹介された。
犯行当時の心境がつづられた「日記」
ほぼワンオペで懸命に介護を続けていたものの、限界を迎えた被告は妻を殺害するにいたる。
事件当日も、妻は「財布を返せ」「(被告が)浮気している」「(浮気)相手のところへ行こう」などと騒ぎ始めた。被告は妻をベッドに座らせてなだめたが、おさまらなかったため「殺害しよう」と決意する。ベッドの上で首を絞めると、妻は抵抗し泡を吹いたが、それでも締め続けた。その後、確実に殺そうと電源コードで首を絞めたところ、妻は息絶えたという。
当時の被告の心境は、証拠として提出された被告の「日記」に表れている。被告には、携帯電話のメール未送信フォルダにメッセージを入れて日記をつける習慣があった。そこには、9月30日から10月2日にかけて、立て続けに以下のようなメッセージが保存されていた。
「なかなか死ぬ踏んぎりができません」
「でも限界です!!やってみます」
「刃物は傷つけてかわいそうなので首を絞めようと思います」
「あるだけの酒を飲んで死のうと思います」
「(酔いつぶれて朝になり)みっともなくまだ生きています」
「かわいそうだよな、○○(妻の名前)の頭の中どうなっているのかな」
「また酔いつぶれそうで怖いです」
検察側の冒頭陳述によれば、被告は犯行後、飲酒の上で自殺しようとしたが思いとどまったという。
自身のつづったメッセージが証拠として法廷のモニターに写し出されると、当時の心境を思い出したのか、被告はうつむき、沈痛な面持ちを浮かべているように見えた。

資料を見るときなどはメガネを着用していた(画:Minami)
6割を超えている「老老介護」世帯
厚労省が「国民生活基礎調査」の一環として3年に1度実施している介護の状況調査によれば、2022年時点で要介護者等のいる世帯のうち、いわゆる「老老介護」をしている世帯(※)は63.5%だった。
※ 「要介護者等」と「同居の主な介護者」がともに65歳以上だった割合
また、介護する側・される側がともに75歳以上の後期高齢者の世帯も35.7%と高い割合となっている。老老介護世帯の割合は右肩上がりで、今後も増加することは想像に難くない。
初公判では、老老介護のみならず、介護そのものの難しさも改めて実感させられた。殺人は決して許されるものではないが、吉田被告の起こした事件は、誰もが当事者となり得るものなのかもしれない。