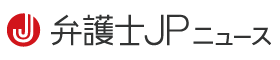4月1日に初回放送がされて以来、SNSは毎日のように視聴者のコメントで賑わっているNHKの連続テレビ小説『虎に翼』。日本初の女性弁護士・三淵嘉子(みぶち よしこ)を主人公のモデルにした本作は“新しい”朝ドラとして、法曹界でも注目を浴びている。
本作の特徴は、主人公の寅子が理不尽な状況に直面したときに「はて?」と異議を唱えながらルールを変えようとする姿に象徴されているように、NHKの朝ドラとしては異例なほどに「社会問題」が扱われていることだ。また、主人公の月経や登場人物の同性愛など、ジェンダーに関する描写が多々含まれている。
6月10日に放送された第51話では、カフェの壁に憲法14条の文言が墨書きされたシーンが多くの視聴者の印象に残った。本作において「憲法14条」は何を意味しており、現代の社会にどんなメッセージを投げかけているのか。数々のドラマ評を執筆した実績があり、女性やジェンダーの描写にも造詣の深いライターの西森路代氏が、作中の演出を深掘りしながら分析する。
あえて「玉音放送」を使わない演出
『虎に翼』の第一話は、憲法14条のナレーションから始まる。ドラマが始まったばかりの頃は、なにげなく聞いていたこの憲法の読み上げだが、話が進み第八週の終わりの予告でふたたび同じ箇所が読み上げられたときに、なぜか聞いていて涙がこみあげそうになった。
直前のシーンが主人公の佐田寅子(伊藤沙莉)の夫・優三(仲野太賀)が出征するシーンだったことで、感傷的な空気を感じたのだろうか。ただ、憲法の読み上げでここまでの感情になるのはなぜなのだろうと自分に対して不思議に思うところもあった。
翌週の放送では、寅子の兄の直道(上川周作)が戦争で亡くなり、ほどなくして終戦が描かれる。このとき、朝ドラにはつきものの玉音放送が使われなかったことが意外だった。
そもそも、この日に「戦争は終わりました」と一方的に言われても、人によってその実感を持つ瞬間は違っているだろう。玉音放送で戦争の終わりを描くことが誰にとっても戦争が終わった実感を意味するものにはならないのかもしれない。
その頃の寅子は、優三の帰りを待ちながらも、家を支えようと弁護士事務所での仕事を探していた。しかし寅子は、父の直言(岡部たかし)が優三の死亡告知書を隠していたことを知る。父に怒りながらも、最終的には許すが、その父も栄養失調と肺炎で亡くなってしまった。優三を失った事実をまだ受け入れられない寅子に、母親のはる(石田ゆり子)はお金を渡し「自分のためだけに使いなさい」「優三さんの死を向き合いなさい」と声をかけるのだった。

戦争がもたらす悲劇のなか、寅子は悲しみを乗り越えて生きる(写真提供:NHK)
生きるために“こっそり”と食べる登場人物たち
このドラマでは、みな「こっそり」と何かを食べている。母のはるも、寅子の兄嫁の花江(森田望智)も、みな悲しみを乗り越えるために「こっそり」何かを食べてきた。死の直前に、これまでの罪を告白していた父の直言も、こっそり寿司を食べたり、闇市でお酒を飲んだりしていたことを明かしていた。寅子と共に働く裁判官の桂場等一郎(松山ケンイチ)も、いつも焼き芋などの食べ物を仕事場にしのばせている。このドラマで、「こっそり」と食べることは、とても重要なのだ。
戦争は食べることを奪う。それは戦争が終わってからも続く。寅子と大学時代に出会い、寅子に好意を抱いていた花岡悟(岩田剛典)は、後に判事として食糧管理法違反に関する事件を取り扱うようになっていた。つまり「ヤミ商売」を裁いていたのだった。しかし、当時の世の中では、ヤミ市場で食料を調達しないで生きている人はいなかった。
実直な花岡は、ヤミ商売で得た食料を一切、口にしなかったこと、つまり「こっそり」食べることをしなかったために亡くなってしまった。寅子が花岡の死の一報を聞いた後に、ヤミ米で作ったのであろう弁当を感謝しながら食べているシーンが記憶に残る。
寅子と優三は、元々は契約結婚で寅子には何の感情もなかったが、「こっそり」と何かを食べる時間に愛情が芽生えた。
優三の出征の直前にも、寅子と一緒に河原で「隠れて」おいしいものを食べた。そのときに優三は、「寅ちゃんができるのは、寅ちゃんの好きに生きることです。また弁護士をしてもいい。別の仕事を始めてもいい。ゆみのいいお母さんでいてもいい。僕の大好きな、あの何かに無我夢中になってるときの寅ちゃんの顔をして、何かに頑張ってること、いや、やっぱり頑張らなくてもいい、寅ちゃんが後悔せず、心から人生をやりきってくれること、それが僕の望みです」とありったけの愛情のこもった言葉を残して戦地に向かう。
優三の死後、思い出を胸に、寅子は母にもらったお金を握りしめて、ひとり町に出て焼き鳥を食べるのだが、優三と一緒でないと何を食べてもおいしく感じられない。食べかけの焼き鳥を残して後を去ろうとすると、お店の女性が、その鶏を新聞紙に包んでおいかけてくる。きっとこの女性も、つらい思いをしたときに、「こっそり」何かを食べてきた人なのだろう。
「憲法14条」が登場人物たちを包み込む
寅子は包みを持って河原に行くが、その新聞紙に憲法14条の記事を見つけるのだった。憲法14条に書かれていることとは、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」 というものだ。
これは、優三が生前に寅子に言っていたことと重なる。優三の言葉は、寅子に自由に自分のやりたいことを、やりたいようにやれる世の中であってほしいという願いが込められていたが、憲法14条では、寅子だけでなく、すべての人に向けて書かれている。
寅子は、河原で憲法14条を読み、優三の言っていたことと重ね合わせたことで、自分にとっての戦争を終わらせ、前に向いて歩き始めたのだ。
このドラマの中では、憲法14条は、優三のように優しく、温かく、そっと守ってくれている毛布のような存在に見える。
50話で、寅子は何年ぶりかで恩師の穂高(小林薫)と偶然、再会する。穂高は自分が寅子を法曹界に引きずり込んだことを悔やみ、これ以上傷ついてほしくないと、新たに家庭教師の職を紹介しようとするが、寅子は「私は好きでここにいるんです」「それが私なんです」と言って穂高の元を立ち去る。
腹が立ち、呼吸も荒くなっていた寅子は、おもむろに憲法13条と14条をつぶやくことで、興奮状態を鎮める。そのときに傍らにいるのは、憲法と「イマジナリー」な優三だ。ここでも、憲法13条、14条は、寅子に寄り添う優三と重なっているのだ。
同じ頃、民法改正審議会では、家制度を重んじる、つまり結婚して夫が妻の姓を名乗ることをよしとしない神保衛彦(木場勝己)と、家制度を撤廃し、妻の姓を名乗ることをよしとする穂高とで意見を戦わせていた。寅子は、家制度の撤廃に賛成の立場であった。
寅子は民法改正審議会で、戦争未亡人で父も兄も亡くした自分も「前の民放でいうの、家と言う庇護(ひご)の傘において守られてきた部分は確かにある」が、「個人としての尊厳を失うことで守られても、あけすけに申せば、大きなお世話である」と言い切るのである。このシーンを見ても、人は「家制度」にも守られているが、それよりも前に、人の尊厳を守る「法」にこそ守られているのだと実感する。

登場人物が集まるカフェの壁面には憲法14条が墨書きされている(写真提供:NHK)
「国や法、人間が定めたものはあっという間にひっくり返る」
新憲法に守られていると感じているのは、寅子と明律大で共に学んだ山田よね(土居志央梨)も同じだった。よねは、「ずっと、これが欲しかったんだ、私たちは。男も女も人種も家柄も貧乏人も金持ちも、上も下もなく、横並びである、それが大前提で、当たり前の世の中が」と語る。
よねは、このシーンで、同じく明律大の同窓生の轟太一(戸塚純貴)が花岡に惚れていたのだろうということを指摘する。二人のシーンを見ると、性的マイノリティにとっても、14条は平等である、あるべきだということが強く伝わってくるのだ。
同時によねは、「これは自分たちの手で手に入れたかったものだ。戦争なんかのおかげじゃなく」とも語る。法は変えられることもあれば、万能ではない。それは花岡が、「人としての正しさと司法としての正しさがここまで解離していくとは思いませんでした」と悩み、後に亡くなってしまったことからもわかる。
寅子の上司である多岐川幸四郎(滝藤賢一)は、花岡の死を、「法律を守って餓死だなんて、そんなくだらん死に方があるか。大馬鹿たれ野郎だね」と思っており、その真意は当初ははっきりとは見えなかった。
しかし、彼が後に「人間、生きてこそだ。国や法、人間が定めたものはあっという間にひっくり返る。ひっくり返るもんのために、死んじゃならんのだ。法律っちゅうもんはな、縛られて死ぬためにあるんじゃない。人が、幸せになるためにあるんだよ、幸せになることをあきらめた時点で矛盾が生じる。彼がどんなに立派だろうが、法を司る我々は、彼の死を非難して、怒り続けねばならん。その戒めに、この絵を飾るんだ」と語るシーンがあり、彼の真意がそこで初めてあきらかになる。
法は簡単にひっくり返される。そしてそのことで死ぬ人が現れる可能性は現代でも大いにある。14条のナレーションを聞いて、なぜか泣きたくなったのは、今でも、人が法の下に平等であるということは、実現できているのだろうかということや、本来なら、どんな人のことも平等に守ってくれるはずの憲法が、変えられようとされている事実が、知らず知らずのうちに頭の中によぎっていたからなのだろう。