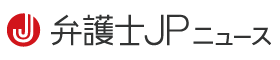米大リーグで活躍する大谷翔平選手の銀行口座から元通訳の水原一平被告が“ギャンブル”に使用するために不正送金を行っていた事件は国内外に大きな衝撃をもたらした。
しかし、ギャンブルのために罪を犯した人は水原被告以前にも多くいる。公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」が発行する「ギャンブル等の理由で起こった事件簿(平成第3版)」には、平成以降に起きたギャンブルを動機とした横領、強盗、窃盗、詐欺等の事件699件が記録されている。
社会的なリスクをはらむ「ギャンブル依存症(病的賭博)」。厚生労働省は2017年に実施した調査から、過去1年以内にギャンブル依存が疑われる人は約70万人(成人の0.8%)に上るという推計を発表している。
この連載では、会社員のセイタ(28)がギャンブルに飲み込まれていく様を追体験する。最終回では、家族に助けを求め依存症の克服を目指すセイタが、身近に「ギャンブル」がある“怖さ”を口にする。
※この記事は染谷一氏の著書『ギャンブル依存 日本人はなぜ、その沼にはまり込むのか』(平凡社)より一部抜粋・構成。
早朝の会社に忍び込み……
そのときはあっさりとやってきた。
勝ち負けを繰り返しながら、なんとかプラス収支を続けてきた勝負が、負け一辺倒に転じた。
失った分を取り返そうと重ねた借金も、悪い夢を見ているようにスマホのなかで溶けていく。経験や知識が勝敗にかかわってくる競馬やマージャンなどに比べて、カジノには個人の能力が介在する余地はなく、すべては運任せ。負け続ける可能性など、算数レベルの知識で説明ができる。
これまでに、セイタが経験した経済的ピンチなどとは、比較にならない惨状となっていた。会社の給料が出ても、消費者金融の利息分だけで吹っ飛んでしまう。
そして、2020年10月、入ったばかりの給料を、数時間で溶かす結果になったセイタは、会社の同僚たちの金に手をつけることを決意した。
早朝の会社に忍び込んだセイタは、2度にわたって部費9万円を盗み出した。負けたら本当に終わり。生きるか死ぬかのバカラ勝負に突っ込んだ。喫茶店のテーブルで、一心不乱に、スマホのなかでカードをめくり続けると、うまくいい波をつかまえることができて、持ち金は12万円にまで増えた。
「これで、盗んだ部費は返せる」
始業時刻が近づいたので、喫茶店を出て、いったん会社に戻った。とりあえず、気持ちには少しだけ余裕が生まれていた。だが、このときのセイタにとって3万円のプラスなど焼け石に水。勝負続行の一択しかない。
ホワイトボードの「外出先」に得意先の名前を書くと、再び喫茶店に出向き、オンラインカジノへと戻った。
正午前には、カジノ口座の12万円はきれいに溶けてなくなった。
もう死ぬしかない……
手をつけてしまった部費の「返済」もできない。絶望の2文字がセイタにのしかかった。死ぬしかない……か。
だが、実行するほどの度胸はなかった。
結果的には、実家に電話をかけて、母親に泣きそうな声で「ギャンブルで借金をつくり、会社の同僚の金に手をつけてしまった」と、これまでの経緯すべてを包み隠さずに説明した。かつての「素直でまっすぐな息子」が、「ギャンブルのせいで、他人の金に手をつけた」と言ってきたのだから、母親のショックは計り知れないものがあっただろう。それでも、電話器越しに伝わってきたセイタの沈鬱な様子から、母親は息子が犯した罪以上に、自殺を恐れたようだった。
「まずは落ち着きなさい」
冷静な口調でセイタを諭すと、その日のうちに、会社から盗んだ金、それに消費者金融やクレジットカードの借金分を、セイタの口座に振り込んでくれた。久しぶりに感じた家族の存在に、なんとかセイタも落ち着きを取り戻した。夕方までには消費者金融やクレジットカードからの借金は一気にきれいになくなり、盗んだ部費も、その日の夜のうちに戻しておいた。
それと引き換えに両親が出した条件が、オンラインカジノだけでなく、すべてのギャンブルに二度と手を出さないこと。親なら当たり前の言い分だろう。そして、もう一つの条件が、ギャンブル依存の回復施設への入居だった。こちらもセイタ自身が望むところだった。
高校を卒業し、大阪から東京へと生活の拠点が変わってからは、いつも自分につきまとった「報酬期待」にがんじがらめになって、ギャンブルに依存し、結果的に破滅したことは自覚していた。そんな自分から、もう離れたい。ギャンブル、そして金の束縛から自由になりたい。生まれ故郷にいたころの自分に戻りたい、と。
二度とギャンブルには手を出さないか
勤務先には「うつ病」と申告し、長期の療養休暇を取得した。
セイタが入った都内の回復施設では、いろいろな人と出会った。アルコールやドラッグの依存者と同様にギャンブルから離れたことで、禁断症状を起こしている人もいた。セイタ自身、そんな典型的なギャンブル依存者たちと自分との間に違いを感じていながらも、これまで過ごしてきた過去と徹底的に向き合った。
どうして、自分は変わってしまったのか。どうして、かつて軽蔑さえしていたギャンブルに手足を縛られてしまったのか……。
思えば、大学へ入学して以来、ギャンブルに興奮を求めた記憶はほとんどなかった。安易に金を手に入れられる、というより、手に入れられると錯覚した手段がギャンブルだったに過ぎず、そこから抜け出せなくなっていただけだった。あまりにもギャンブルが身近にあったことも、セイタの「変節」に拍車をかけた。
いつだって、自分のポケットのなかにはスマホがあった。バイト先の先輩にパチスロを教わり、簡単に金を手にすることができてから、スマホのディスプレーを通じて、中央競馬、地方競馬、そしてオンラインカジノと、破滅への道がつながっていった。
もちろん、時代や環境、道具のせいにするつもりはない。自分が弱かっただけだった。けれど、「そこ」にギャンブルがなければ、セイタの人生は違ったものになっていたかもしれない。
「それでも、やっぱり自分はギャンブル依存だったと思います。パチンコへの禁断症状に見舞われていた人とはタイプが違うけれど、お金が欲しくてギャンブルからは離れられなかった。破滅することは不可避だったとも思います」と振り返る。
10か月の入居を経て、回復施設を「卒業」したセイタは、現在は元の職場に復帰している。部費に手をつけたことはもちろん、ギャンブル依存であったことも会社には知られていない。入社当時のように、しっかりと仕事に打ち込む毎日だ。もちろん、ギャンブルには手を出していない。
ただし、こうも言う。
「今後、二度とオンラインカジノに手を出さないなんて確信はありません。いつだって自分の手元にはスマホがあり、そこからオンラインカジノへと道がつながっている。やっぱり怖いですよ」
世界が狭くなったために
インターネットは、人間の生活を飛躍的に向上させたと同時に、負の側面も持ち込んだ。国際的なサイバー犯罪はもちろんのこと、身近なデバイスを使った詐欺、薬物取引、個人への誹謗中傷、児童ポルノの取引など、ネットを媒介とした卑劣な行為は後を絶たない。
だが、考えてみればどれも現実社会でも起こっていることばかりで、世界が狭くなったネット空間では、負の側面も近くになっただけだ。
ICT(情報通信技術)の波は、オンラインカジノにとどまらず、とっくにギャンブルの世界を席巻している。競馬、競輪、競艇、オートレースなどはすべてネットで賭けられるようになり、さまざまな公営ギャンブルを一括で個人管理できるサイトも登場した。
ギャンブルの危険性は、リアル社会も変わらないはずだが、ネットの場合、電子口座のなかで金が動くだけ。勝負に負けた現実さえ、バーチャルな出来事と錯覚しがちになり、破滅の足音に気づくのが遅れてしまうことがある。
そんな現状を見ると、数年前にIR整備法の議論がきっかけで導入されたギャンブル依存対策は、すべてが空虚に響く。カジノ施設に入れる回数の制限や高額な入場料設定、さらに医療的な効果をしっかり見極めることなく、ギャンブル依存の治療に保険が適用されてもいる。どれもカジノ法案を成立させるための場当たり的な政策だったことは明白だったが、さらに斜め上を行くオンラインカジノの存在は、そんな小賢しさなど簡単に吹き飛ばしてしまう。
時も場所も選ばず、24時間365日、入場無料のギャンブルに耽溺できる環境がスマホやPCのなかから手招きして、依存予備軍の報酬期待をあおり続けている。しかも、法的に「クロ」のはずのギャンブルが、現時点では「シロ」と扱われる矛盾を抱えたままに。
ギャンブル依存は、財政破綻者を増やすだけでなく、違法行為、犯罪を助長する懸念も抱えており、その代償は、いつだって社会全体で負うことになる。
新型コロナウイルス感染症の拡大以降、在宅時間をどう過ごすかについての関心は高まってきた。なおさら、オンラインカジノに対する法的な枠組みづくりは急務のはず。「シロ」だ「グレー」だと、先延ばししている場合ではない。