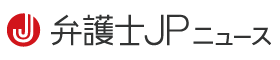奈良県警からストーカー規制法に基づく「警告」を受けた女性がその「取り消し」を求めた訴訟の控訴審(第二審)で、6月26日、大阪高裁は、原告女性の控訴を棄却した。上記「警告」が「行政処分」にあたらず、女性はそもそも取消訴訟を提起できないという「門前払い」の判決。また、警告に従う義務がないことなどの「確認の訴え」も否定された。女性は最高裁に上告している。
訴状によれば、女性は警告によって大きな不利益を被っている。もしストーカー行為の事実がないにもかかわらず「警告」を受けてしまったら、どのように権利救済を求めればいいのか。ストーカー被害者保護の要請がある一方で、「冤罪」のリスクを排除する必要性も大きい。本件を掘り下げると、現行のストーカー規制法の抱える問題点が浮かび上がる。
身に覚えのない「ストーカー扱い」で重大な不利益
原告は、AIの研究者をめざし大学院で学んでいた女性Xさん。同じ研究室の上級生である男性Aさんに対する「ストーカー行為」を行ったとされ、2022年6月にストーカー規制法4条の「警告」を受けた。
訴状によれば、Xさんが主張する事案の概要は以下の通りである。
Aさんは研究室でのXさんの指導役だったが、Xさんにアプローチするようになった。Xさんは当初、気に入られないと勉強を教えてもらえない、就職に際して意地悪される、などと思い、渋々ながらも応じていた。しかし、Aさんのアプローチが激しくなってきたので拒絶をしたところ、Aさんの態度が変わった。
Xさんは2022年2月に県警から口頭注意を受けたが、身に覚えがなかった。その後、Aさんとは関わらないよう注意していたが、研究活動のためやむを得ずSNSでメッセージを送ったところ、警察から文書でストーカー規制法に基づく「警告」を受けた。
その後、教授からは授業への出席を禁じられた。また、将来への不安から心身に変調をきたし、大学の医務室に相談に行ったら「あなたがストーカーなんだから」などと言われた。大学に通うことができず、現在はオンラインでの履修や研究活動を余儀なくされているという。
ストーカー規制法「警告」制度の問題点
Xさんの弁護団の一員である松村大介弁護士は、現行のストーカー規制法の「警告」が抱える問題点を指摘する。
松村弁護士:「現行のストーカー規制法では、警告を発する前提として、『恋愛目的』か『怨恨(えんこん)目的』の有無を警察が判断することになっています。
しかし、現行法の要件は緩く、何かもめ事があったら『恋愛目的』か『怨恨目的』のどちらかが認定されてしまうおそれがあります。『言ったもの勝ち』になってしまいかねません。
また、『警告』を受けた事実は個人情報ファイルに掲載されます。Xさんは、個人情報保護法に基づく訂正請求を行いましたが、認められませんでした。その理由は『奈良県警が行った警告の内容に基づき正しく登録されているので訂正できない』というものです。
緩い要件の審査に基づいて『警告』が行われ、それに基づいて対象者の個人情報が管理され、訂正請求も認められません。しかも、前述のような重大な不利益を受けるおそれもあります。
ストーカー対策が社会問題であること、被害者を速やかに救済しなければならないことは当然です。しかし、被害者だと主張している側の言い分をうのみにすると、酷な結果となります。
誰もが一方的にストーカーとして扱われてしまう危険性があるのは大問題です」

ストーカー相談件数の推移(2014年~2023年)(警察庁「令和5年の犯罪情勢」より)
警告の「取り消し」を求めるのに「処分性」がハードルに
本件訴訟で、Xさんはストーカー規制法の「警告」の効力を争うため、「処分の取消訴訟」(行政事件訴訟法3条2項)を提起している。
「警告」は典型的な「処分」ではない。条文の文言上は、従うかどうかが対象者の任意に委ねられる「ふつうのお願い」(行政指導)として規定されているように見える。そこで、「警告」が取消訴訟の対象である「処分」と認められるかが問題となる 。
「処分」の定義(処分性)について、従来の裁判例では形式だけでなく実質にも着目して判断されてきており、最高裁の判例により以下の判断基準が固まっている(最高裁昭和39年(1964年)10月29日判決参照)。
「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
この基準は大きく、「①公権力性」「②法的効果」の2つの要素に分けられる。そのうち、本件で問題となるのは「②法的効果」である。
「②法的効果」とは、その行為(本件では「警告」)によって国民の権利義務に影響が生じることを意味する。なお、場合によっては、あとの段階まで待っていたのでは原告の権利の救済が困難になるということも考慮に入れる。
Xさんの弁護団は、これらについて以下のとおり立論し、本件では処分性が認められると主張した。
・ストーカー規制法および関連法令の「銃刀法」のしくみにてらし、「警告」は国民の権利義務に影響を与える
・「命令」が出されるまで待っていては原告の権利救済が困難になる
ここで、銃刀法という、Xさんと直接関係のないように見える法律が登場している。しかし、この点について、松村弁護士は、あくまでも従来の判例・通説の枠組みに即した主張であると説明する。
松村弁護士:「弁護団の主張は、決してとっぴなものではありません。あくまでも、いわゆる『行政指導』について処分性を認めた最高裁の判例の枠組みに留意したものです(平成16年(2004年)4月26日判決、平成17年(2005年)7月15日判決、平成24年(2012年)2月3日判決等参照)。
また、高名な行政法学者の先生にも何人か相談し、意見を聞いています。
まず、ストーカー規制法自体について。『警告』が発せられるしくみ、現状の実務運用によって対象者がこうむる不利益の大きさからみて、『行政指導』の域を超えていると考えられます。
すなわち、行政は『行政指導』と言っているけれども『従わない自由』は事実上認められません。従わない場合には『禁止命令』が待っています。
次に、ストーカー規制法自体に加え、関連法令である『銃刀法』のしくみや運用の実態も詳しく調べたうえで、主張を組み立てています。
ストーカー規正法と銃刀法はいずれも警察庁が所管する法律であり、互いに密接な関連性があります 。というのも、2000年代に『ルネサンス佐世保散弾銃乱射事件』『秋葉原無差別殺傷事件』等の犯罪が多発し、それを受けて2008年にストーカー規制法と銃刀法がリンクする法改正(法システム)が採用された経緯があるからです」
しかし、本件訴訟では一審・二審ともにこの主張を認めず、処分性を否定し、「門前払い」した。

一審の奈良地裁(HAPPY SMILE/PIXTA)
不利益を被っているのに“訴訟で争えない”という現実
松村弁護士は、「警告」に処分性が認められないことによりXさんの権利救済が困難になってしまうことを強調する。
松村弁護士:「Xさんは、身に覚えもないのに『ストーカー』扱いされて『警告』を受け、大変な不利益を被っています。
一審・二審の判決は、『警告』の段階ではなく、『命令』が出されてから争えばよいとしています。しかし、Xさんはそもそもストーカー行為をする意思がない以上、『命令』は下されようがありません。他方で『警告』はずっと残ってしまいます。
たとえば、個人情報ファイルにも、Xさんが『警告』を受けたという事実が記載されてしまっています。
『警告』が単なる行政指導ではないことは明らかです。つまり、Xさんの権利が救済されるには、端的に『警告』の効力を否定できる取消訴訟によるしかありません」
「受け皿」のはずの訴訟類型も否定され…
仮に、行政機関の行為について「処分性」が否定され、「取消訴訟」で争うことが認められない場合でも、訴訟で争う道が完全に閉ざされるわけではない。「実質的当事者訴訟」(行政事件訴訟法4条後段)という訴訟類型がある。
Xさんのケースに即していえば、「ストーカー規制法の『警告』を受ける者として取り扱われない地位の確認」「個人情報ファイルに『警告』の事実が記載されない地位の確認」などを求めて訴えを提起する方法である。
そして、この「実質的当事者訴訟」が機能する典型的な場面は、まさに本件のような「処分性」が認められなかったケースである。つまり「受け皿」となる訴訟類型として理解されている。
ところが、本件訴訟の一審(奈良地裁)、二審(大阪高裁)はいずれも、Xさんの「確認の利益」がないとして、実質的当事者訴訟の提起も否定した。
松村弁護士:「実質的当事者訴訟では『確認の利益』が要件とされています。これは、民事訴訟の『確認の訴え』と同じ基準で判断されるべきものです。すなわち、『現在の法律関係に関する争いであること』(対象選択の適否)と、『他の訴訟類型では争えないこと』(手段選択の適否)を意味します。
Xさんが受けている法律上の不利益は紛れもなく現在のものです。また、『警告』の処分性が否定されてしまった以上、もはや、訴訟で争う手段は実質的当事者訴訟以外に残されていません。
ところが、一審では『過去の事実関係を求める訴え』と判断され、確認の利益が否定されてしまいました。
二審では『現在の法律関係に関する確認の訴え』であることは認められました。しかし、『重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないこと』等の条文にない要件を勝手に付与して、結論として確認の利益が否定されてしまったのです。
もし、二審判決の理屈に従えば、実質的当事者訴訟が機能する場面は事実上ほとんどないということになりかねません」
裁判官が「2004年改正法」に対応できていない可能性も?
考えられる可能性の一つとして、「一審・二審の担当裁判官の行政事件訴訟法の理解が不十分だったのではないか」ということが挙げられる。
というのも、実質的当事者訴訟はかつて「死文化」していたが、2004年に行政事件訴訟法の大改正が行われた際に一転して「受け皿」として積極的に活用する方向性が示されたという経緯がある。
法務省の資料にも(「平成16年改正行政事件訴訟法の概要」参照)、すべての行政法の教科書にも、そのように記載されている。かつ、法科大学院(ロースクール)などの法曹養成機関でも、当然の前提として教えられている。
他方で、行政法は2000年代の司法制度改革以前、司法試験の必修科目ではなかった。そのこともあってか、旧司法試験制度下で任官した裁判官のなかには、行政法ないしは改正行政事件訴訟法についての理解が不十分な人がいるという問題点が指摘されることがある。
本件も、その影響を受けている可能性があるのではないか。
現に、二審判決は前述のように、実質的当事者訴訟の「確認の利益」を検討する際に、「重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないこと」という要件を付加してしまっている。これは、活用場面がまったく異なる「一定の『処分』の義務付け訴訟」(非申請型義務付け訴訟)を提起するための要件と混同している疑いがある(行政事件訴訟法27条の2参照)。
松村弁護士:「もしかしたら、一審・二審の裁判官の行政法の理解が不十分である可能性はあるかもしれません。
最近でも、『執行停止』という制度(行政事件訴訟法25条)について、東京地裁が2004年法改正後の条文に忠実に判断して執行停止を認めたにもかかわらず、東京高裁が却下したという事例がありました。東京高裁の判断は、法改正前の裁判例に従ってなされたのではないかと指摘されています(※)。
行政事件訴訟法の大前提についての共通理解が定着するまで、ある程度の時間がかかるのはやむを得ない面があるのかもしれません。
しかし、そのことによって、国民の裁判を受ける権利までが侵害されてしまうのは、きわめて深刻な問題です」
※2024年5月21日の記事でこの事例を取り上げている
二審判決を受け、Xさんと弁護団は、7月2日に最高裁への上告を行った。「勝算」はあるのか。
松村弁護士:「前述したように、本件での『処分性』の主張は、あくまでも過去に『行政指導』等について処分性を認めた有名な最高裁判例の判断枠組みに留意したものです。
それらの判決では、いずれも一審・二審では処分性が否定され、上告審で認められました。本件でも、上告審で一転して最高裁が処分性を認める可能性は十分に考えられます。
Xさんが身に覚えのないストーカー扱いをされ、重大な不利益を被っているのに、その元凶である『警告』について訴訟で争う手段がないというのは、きわめて深刻な問題です。
現行制度の下では、誰もが、ある日突然、身に覚えのないストーカー規制法の『警告』を受けるリスクがあります。本件訴訟はもちろんXさんの救済を目的としていますが、究極的には、すべての人の人権を守るための訴訟だと考えています」