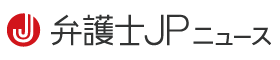パワハラ、体罰、過労自殺、サービス残業、組体操事故……。日本社会のあちこちで起きている時代錯誤な現象の“元凶”は、学校教育を通じて養われた「体育会系の精神」にあるのではないか――。
この連載では、日本とドイツにルーツを持つ作家が、日本社会の“負の連鎖”を断ち切るために「海外の視点からいま伝えたいこと」を語る。
第4回目のテーマは、過労死に代表される「仕事=自己犠牲」という“潜在意識”だ。
※この記事は、ドイツ・ミュンヘン出身で、日本語とドイツ語を母国語とする作家、サンドラ・ヘフェリン氏の著作『体育会系 日本を蝕む病』(光文社新書)より一部抜粋・構成しています。
仕事のためなら「ハラキリ」する?
過労死が初めて問題になったニッポンのバブル期以降、世界では「日本人は仕事のためならハラキリのように命まで捨てる」と思われています。
言うまでもなくニッポンにもマトモな企業はたくさんあるので、「ハラキリ」に関しては話が誇張されて、ある種の都市伝説のように語り継がれているのは否めません。
ただ火のない所に煙は立たぬで、その中にも一片の事実はあるのではないでしょうか。
というのも、日本では「自分の命よりも仕事が大事」と口に出して言う人こそあまりいませんが、それはそう発言することが「ダサいから」というのが理由です。
実際には、有休を取れないことを「仕方ない」と容認していたりしますし、無理な残業で睡眠時間が減ってもこれもまた「仕方ない」と容認していたり、一人では処理できないような莫大な仕事量を「自分は頼りにされている」などと解釈して自分にハッパをかけながら頑張ってしまい、その結果「死」が待っているというケースもニッポンには確実にあるわけです。
「仕事を優先して、無理して頑張ってしまう」ことは気質として確かにあるので、「日本人は命よりも仕事」というのはあながち間違っていません。
上の人が“使いやすい”ように「諦めさせる」
日本の社会には「二足のわらじ」を許さない雰囲気があります。だからこそ、わざわざ「二足のわらじ」という言葉があるのでしょう。
もし同時進行でいろんなことを極めていくことが日本で当たり前だと見なされていたなら、そもそも「二足のわらじ」といった言い回しは使われないはずなのです。
何かのために、別の物を諦めることが「潔い」という考えがニッポンでは強いため、ある時点までニッポンでは「結婚をするなら、女性は仕事を諦めるべきだ」とか「(男性は)仕事だけをすべき(家事や育児、趣味はダメ)」というような論がまかり通ってきました。
まさに精神論の世界ですが、今一度振り返ってみると、上の人としては下の人に「諦めてもらう」ほうが単純に「使いやすかった」のでしょう。
ブラック労働は業種を問わず、たとえば「俳優」でも、昔から「親の死に目には会えないと思え」という教えのようなものが当たり前と見なされてきました。
舞台を楽しみにしているお客さんのことを考えたらこれは分からないではありません。ただし「親の死に目には会えないと思え」は、実際にはスケジュール調整で間に合うこともあるのに、単に使う側が「休ませたくないから」といった理由で使う便利なフレーズになっていることも忘れてはいけません。