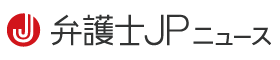「紀州のドン・ファン」として知られた和歌山県の資産家・野崎幸助氏。その突然の死をめぐっては殺人の疑いももたれ、現在、元妻の裁判が行われている。本記事では、外から見えるドン・ファンと元妻の華やかな結婚生活の裏で何が起きていたのか、野崎家の元家政婦が回想する。
今回は、野崎氏が望んだ地元神社での結婚式に新婚の妻が猛反発する様子から見えてくる、2人の間の溝に迫る。(第2回/全5回)
※ この記事は「紀州のドン・ファン」の家政婦・木下純代氏による著作『家政婦は見た! 紀州のドン・ファンと妻と7人のパパ活女子』(双葉社、2021年)より一部抜粋・構成。
幻に終わったドン・ファンの結婚式
ドン・ファンとサエちゃん(仮名) が電撃入籍したのは、2018年2月8日のことです。
普通は入籍したら同居を開始し、アツアツの新婚生活が始まるものですが、2人の場合は、残念なことにそううまくはいきませんでした。田辺市役所で婚姻届を提出するやいなや、サエちゃんはすぐさま東京に戻ってしまったのです。
「急な話だったので田辺まで来ましたけど、これからしばらく、東京で仕事をいろいろ片づけなくちゃ。海外出張の予定もあるし、すぐには田辺に引っ越せません」
そんな言い訳をします。入籍するまでの間は、東京や和歌山で頻繁にドン・ファンと会っていたようですが、婚姻届を出してからの彼女はどうも様子がおかしいのです。
パーティや食事会が大好きなドン・ファンは、サエちゃんとの結婚をみんなに自慢したくてたまりませんでした。
「結婚式は、3月24日に鬪雞(とうけい) 神社でやります。サエさんが帰ってくるまでに、急いで段取りを整えて準備してください」
毎日あちこちに電話をかけまくりながら、会社のスタッフや私に、矢継ぎ早に指示を出していました。
鬪雞神社とは、田辺市にある有名な神社です。熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の別宮(本宮と密接な関係のある神社)と位置づけられており、1600年以上にわたって人々に親しまれてきました。2016年10月には、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録された名勝です。
実はドン・ファンはとても信心深い方でした。毎年神社にお参りに行き、莫大なお金を寄付していましたし、自宅には神棚を祀りお供物をしていました。
せっかく結婚のお披露目式を楽しみにしていたのに、サエちゃんはこの計画に猛反発しました。
「結婚式なんてやるなら、離婚するから!」
「人前でなんて、私と社長の関係をさらしたくないの。絶対に嫌……」
見事にはっきりと断られ、3月24日の結婚式は、お流れになってしまったのです。
ボンと渡された100万円の札束
サエちゃんが初めて和歌山に来たとき、ドン・ファンはいきなり「はい、これはお小遣いね」と言って100万円の札束をボンと渡しました。パパ活セックスをしてくれるほかの子には10万円しか渡さないのに、ケタが一つ違います。
「ありがとう」
サエちゃんはすぐさま、その札束をバッグにしまいました。
家政婦の私には、日当1万円プラス交通費、私に帰ってもらいたくないからと帰りの交通費を渋って、くれないことも多々ありました。たまには、いくらかボーナスをくれても良さそうなものなのに、昨日や今日会った小娘にいきなり100万円を渡しているのを見て、良い気分はしませんでした。
ドン・ファンとパパ活をし、入籍までしたのは、報道されているとおり、お金目当てだったのでしょうか? セックスフレンドでは1回のデートに10万円支給が限界、結婚すれば会わなくても、セックスをしなくても100万円が自動的に手に入る。こんな楽なことはない。あくまで私の推測にすぎませんが、そう考えていたのかもしれません。もちろん、本当の気持ちはサエちゃんにしか分かりませんが……。
あるとき、結婚早々、「和歌山に来ないなら離婚だ!」とドン・ファンが騒ぎ立て、サエちゃんが無理やり東京から連れ戻されたことがありました。すると、ドン・ファンが席をはずしたタイミングで、サエちゃんは私にボソッとこのようなニュアンスのことを漏らしました。
「社長が死んだら、私、お金もらえるんですかね?」
パパ活のセックスフレンドでいる限り、遺産を相続することはできません。1カ月100万円のお小遣いをくれると約束してくれたとしても、ドン・ファンが亡くなった瞬間、お小遣いの支給はたちまちストップします。しかし、籍を入れた配偶者となると、話はまったく別です。妻には遺産相続の権利がありますから、総額50億円とも言われる莫大な財産のうち、かなりの額を手にすることができます。
「結婚して奥さんなんだから、そりゃお金もらえるんじゃない?」
まさか、このときの会話が、のちの大騒動に発展しようとは……。当時の私は知る由もありませんでした。