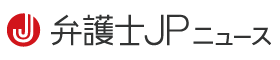一市民が刑事事件の犯人と間違われたとき、「冤罪」が生まれる。あってはならない、究極的な間違いだ。
疑われた人の人生を狂わせる冤罪はなぜ発生してしまうのか。そこに問題意識を持ち、撲滅を見据えて多方面から客観的に分析し、再発防止に役立つよう体系的にまとめた一冊「冤罪 なぜ人は間違えるのか」。
著者の西愛礼弁護士は「人は間違える」ことを受け止めたうえで、努めて冷静に「司法の落とし穴」を解き明かしている。
第4回では人を誤った判断に導きやすい「先入観」をテーマに、マスメディアの事件報道における”予断形成”の問題について取り上げる。
※ この記事は西愛礼氏の書籍『冤罪 なぜ人は間違えるのか』(集英社インターナショナル新書)より一部抜粋・再構成しています。
メディアによる予断形成の問題
メディアが特定の事件に対する「予断形成」に大きな影響を与えているのではないかという指摘がなされています。
心理学的にも、被疑者を犯人視する新聞記事を読んだグループのほうが、それを読んでいないグループよりも有罪を支持する割合が多いという実験が存在します。裁判官がどんなに気を付けたとしても、一度記憶した情報を頭の中から消し去ることはできませんので、無意識のうちに予断に囚われてしまう危険性は否定できないのです。
そもそも、日本の報道においては、事実の伝達に記者の主観や意見を入れてはならないという「客観報道主義」というルールが存在します。
主観を入れてはならないということは一見、良いことのように思えますが、こと刑事事件では警察・検察といった捜査機関側が公表した情報が、報道において不可欠な「裏取り」もないまま、あたかもそれが事実であるかのように報じられるのが日本では通例になっています。
独り歩きしがちな事件報道
一方、被疑者や弁護人側は捜査機関の持っている証拠を見ておらず、捜査状況も分かりません。この状況では被疑者サイドが警察の流す情報に対抗するために情報を公開すると、それが捜査機関に利用される可能性もあり、インタビューで語ったときの、ささいな記憶違いなどがより疑いを強めてしまうリスクがあるため、基本的には取材に応じることができません。
特に人違いの冤罪事件の場合、被疑者にはまったく心当たりがないのですから、メディアに対して事件について何も説明できません。
その結果、捜査機関側の情報のみが市民に伝えられてしまい、確定した事実として一人歩きすることになります。
また、メディアとしても、他社が報じるであろう以上その事件について報じないわけにはいかないということになり、さながらチキンレースのように事件に関する詳細な情報が憶測を含めて早期の段階から報じられてしまうことになります。
報道では「推定無罪」の原則が”形骸化”
刑事裁判は「推定無罪」、つまり裁判所の判決によって有罪が確定するまでは無罪と推定するという原則があるものの、被疑者のプライバシーにほとんど配慮されずに逮捕時点で実名報道されることが多く、その結果、捜査報道に接した人には被疑者がそのまま犯罪者であるかのような印象づけがなされてしまいます。
こうした被疑者が犯人と確定しているかのような報道は捜査機関、弁護人、裁判官・裁判員らに予断を植え付けるものであり、改善されなければなりません。
実際にこれまでにも足利事件や袴田事件などの冤罪事件において、当時の犯人視報道が冤罪を作り出したものとして問題視され、雪冤後に検証されたり、メディアが謝罪したりしたこともあります。
「逮捕=犯人」という間違い
「国際人権規約」(1966年の国連総会において採択され、1976年に発効、79年に日本批准)の自由権規約においては無罪推定原則が保障されていて(14条2項)、その解釈指針において「報道機関は、無罪の推定を損なう報道は避けるべきである」と明記されています(一般的意見32パラグラフ30)。
日本でも、2007年に開催されたマスコミ倫理懇談会全国協議会において、当時の最高裁判所参事官は、問題のある報道として次の内容を挙げました。
・被疑者が自白していることやその内容を報じること
・被疑者の弁解の不合理性を指摘すること
・犯人かどうかに関わる状況証拠を報じること
・前科や前歴を報じること
・被疑者の生い立ちを報じること(生い立ちと犯罪事実には直接の関係がない)
・事件に関する「有識者」のコメントを伝えること
2008年には、日本新聞協会が「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」として、次の内容が確認されました。
捜査段階の供述の報道にあたっては、供述とは、多くの場合、その一部が捜査当局や弁護士等を通じて間接的に伝えられるものであり、情報提供者の立場によって力点の置き方やニュアンスが異なること、時を追って変遷する例があることなどを念頭に、内容のすべてがそのまま真実であるとの印象を読者・視聴者に与えることのないよう記事の書き方等に十分配慮する。
被疑者の対人関係や成育歴等のプロフィールは、当該事件の本質や背景を理解するうえで必要な範囲で報じる。前科・前歴については、これまで同様、慎重に取り扱う。
事件に関する識者のコメントや分析は、被疑者が犯人であるとの印象を読者・視聴者に植え付けることのないよう十分留意する。
しかし、こうした指針公表以後でも逮捕時点であたかもその人の有罪が確定したかのような世論を形成してしまっています。このような報道は「無罪推定」を受ける権利を侵害するものといえます。
メディアでも過去の失敗検証する取り組み始まる
近年、冤罪が発覚した時に過去の自社の報道を検証し、その責任として冤罪当事者の名誉回復に努めるという取り組みも行なわれるようになりました。過去の失敗を検証するという取り組みがメディアの中でも始まりだしたのです。
上記のような予断を形成する情報を報じないようにすることや、無罪推定が及んでいることに配慮して「逮捕=犯人」というような印象を与えないよう心がけることといった再発防止策を講ずる必要があると思います。
近年ではSNSの発達により、一般市民も情報の拡散に寄与することになりました。これは、誰しもが冤罪に関する情報の拡散に加担してしまい得るということであり、刑事事件に対する予断を作ってしまいかねないということです。そのため、刑事司法関係者だけでなく一般市民も、冤罪事件の発生を助長しないように気を付けて情報を扱うべきと言えるでしょう。