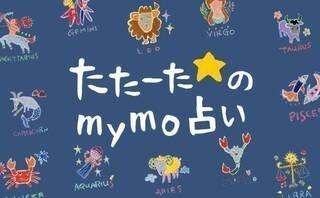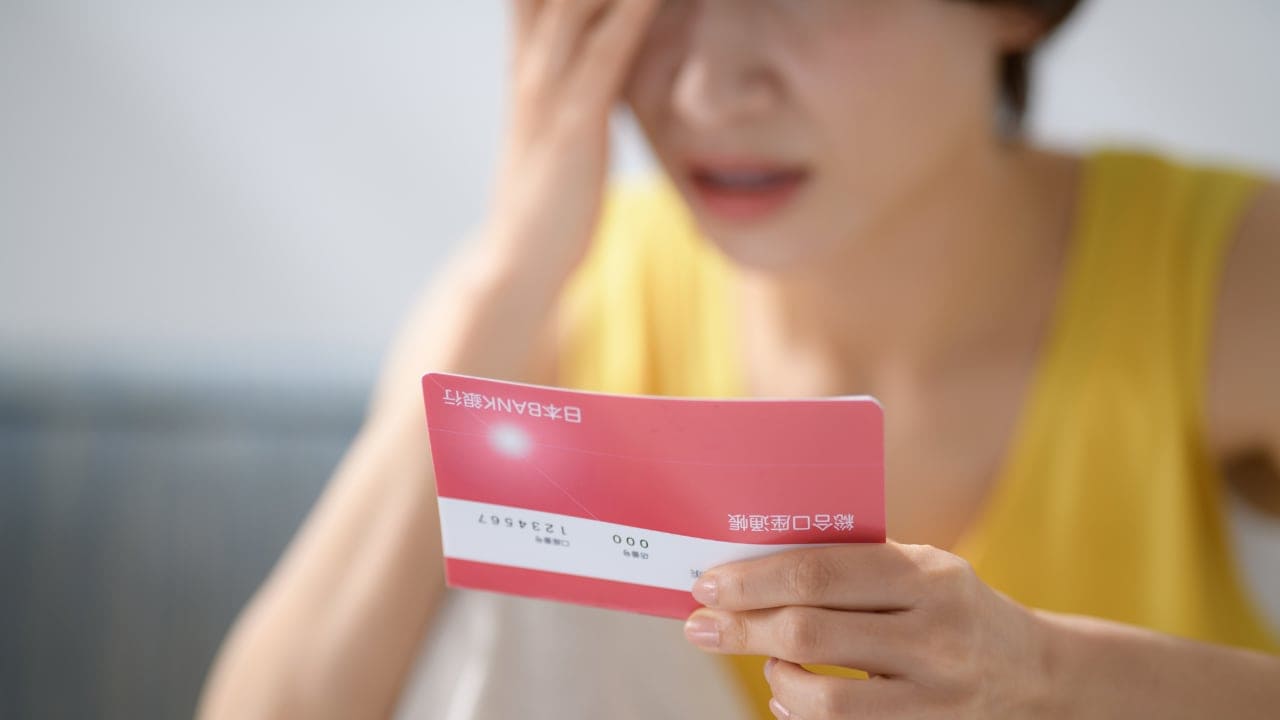
投資信託は誰でも手軽に資産運用を始められる便利な仕組みですが、実は手数料や信託報酬といったコストが利益に大きな影響を与えることをご存じでしょうか。とくに長期で運用する場合、コストの違いがリターンに大きく響くことも…。投資信託にはどのようなコストがあり、何に気をつけるべきなのか、その詳細を詳しく見ていきましょう。伊藤亮太氏の著書『図解即戦力 資産の運用と投資のキホンがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)から一部を抜粋・再編集し、解説します。
投資信託の3つのコストを理解する
投資信託でかかるコストは、募集(販売)手数料、信託報酬、信託財産留保額の3つ。このうち、販売する金融機関によって異なるのが募集手数料です。これは販売時にかかる手数料であり、同じ投資信託商品でも金融機関によって無料の場合もあれば、そうではない場合もあります。投資信託を選定する際は、募集手数料が無料または低く販売する金融機関から購入しましょう。
信託報酬は運用管理費用であるため、同じ投資信託商品であればどこで購入してもかかるコストは同じです。そのため同じ種類の信託報酬を比較し、できるだけ低い銘柄を選ぶべきです。ただし、コストが低ければなんでもよいわけではありません。比較サイトなどを活用して、過去の運用パフォーマンスも確認しましょう。
また、純資産総額が多い投資信託のほうがさまざまな株式や債券などに投資できるため、分散によるリスクヘッジの効果は大きくなります。純資産総額が少なく、解約する人が多い投資信託では継続的な運用が難しく、場合によっては償還となる恐れがあります。
(広告の後にも続きます)
中長期投資では信託報酬が負担になる
信託財産留保額は、解約時にかかるコストです。この信託財産留保額は、解約によって、投資信託を保有し続けるほかの投資家に迷惑がかからないようにするための費用です。一般的には、基準価額の0.3%程度がかかります。なかには信託財産留保額がかからない投資信託もあります。
中長期投資で、最も負担となるのは信託報酬です。毎年かかるコストのため、長く保有するほど負担が大きくなります。インデックス型のほうがアクティブ型よりも信託報酬は低い傾向があります。
●募集手数料と信託報酬はできるだけ低いものを選ぶ
●必ずかかるコストは信託報酬。中長期投資では必ず確認する