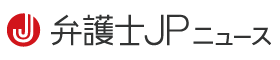今年、落語家・吉原馬雀(ばじゃく)氏の、落語界で最高位にあたる「真打」への昇進が予定されている。
その馬雀氏が監修や一部編集を行った、落語家・三遊亭はらしょう氏の初の著書『俺とシショーと落語家パワハラ裁判』(彩流社)が今年2月に刊行された。
師匠との「パワハラ」裁判で勝訴
2022年、馬雀氏は元師匠の三遊亭圓歌(えんか)氏から暴力や暴言などのパワーハラスメントを受けたとして、損害賠償を請求する民事訴訟を提起した。
2024年1月、東京地裁は馬雀氏の訴えを認め、圓歌氏に80万円の支払を命じる。圓歌氏は控訴したが、同年9月に取り下げ、判決が確定。
関連記事:「落語家パワハラ裁判」で元師匠に勝訴 元弟子が業界に「ハラスメント対策」を要望
『俺とシショーと落語家パワハラ裁判』は、破門にあった二人の落語家が復帰を志すストーリー。
「私小説」の形式で書かれているが、馬雀氏の経験したハラスメントと訴訟、および、はらしょう氏と師匠である三遊亭円丈氏(故人)との実際の関係が題材になっている。
長い伝統を誇る一方で、閉鎖的な縦社会でもある「落語界」に潜む問題を『俺とシショーと落語家パワハラ裁判』はどのように描き出したのか。
以下、同著を出版した経緯、そしてハラスメントの背景にある「師匠」や「先輩」が絶対視される構造について、はらしょう氏が語る。(本文:落語家・三遊亭はらしょう)。

作品の監修を行い、モデルにもなった吉原馬雀氏(撮影:大浦タケシ)
縦社会で生み出される「人間サンドバッグ」
チャカチャンリンチャンリン♪
え〜落語の方には毎度馬鹿馬鹿しい人たちが出てまいりまして~ 「こんちは」 「おやおや誰かと思ったら熊さんじゃないか」 などと、今日はそんな愉快な話ではない。
あまり知られてないが、2022年から2024年にかけて、落語の世界でパワハラ裁判があったのだ。落語家の吉原馬雀が、元・師匠からの長年に渡る理不尽な暴言・暴力を訴えたのである。
おお! ついにきた! と俺は歓喜した。
というのも、俺はこの世界に入って数えきれないくらいのパワハラを目撃し、自身でも体験してきたからだ。
落語家は年齢に関係なく(例えば俺の入門は31歳、指導係の先輩は、なんと18歳!)、一日でも早く入門した者が先輩であるという縦社会で伝統が受け継がれていく。
だが、この制度は時として過剰な行為を生む場合がある。それは、後輩が意見を言えず、心を殺し、人間サンドバッグになってしまうことだ。
師匠の命令に従ったら「破門」に…
俺が入門したのは2009年だったが、楽屋ではこのシステムを利用するかのごとく、己のストレスを「修行」というキラーワードで正当化する先輩が一定数いた。彼らの顔つきは軍隊の嫌な上官そのもので、俺は何度も暴言、時には暴行を受けた。
そして、最悪だったのが、俺は自分の師匠からもそれを受けていたことだ。
「お前は破門だ!」
ある日、師匠は俺を破門にした。
ある方に電話をかけろと師匠から言われた俺は、忠実にその用事をした。ところが、師匠はそんなことは頼んでないと言う。結果、俺が勝手に電話をかけたことになって、破門である。完全なる冤罪だった。このまま破門されてしまったら他の一門への移籍は困難だ。
本当の理由はなんであれ、師匠をしくじったという結果だけで「破門=悪」という図式になり傷物扱いされてしまうのがこの世界だ。
「破門だけは許して下さい!」
俺は何度も懇願した。だが、師匠は大真面目な顔でこう言った。
「俺はお前に電話をかけろと言ったかもしれない…でも言ってないんだ。破門だ! そういう世界なんだ!」
そういう世界って! おいおい、一回認めかけていたのに、これって師匠という立場を利用しただけじゃないのか!
落語界は「特殊な世界」なのか?
そして数か月後、突然、 「一門会に出ろ」と師匠から言われ、俺はあっさりと復帰した。もう何が何だか分からない。
しかし、いったん落語協会から名前を外された俺は、フリーの落語家という特殊な道を歩むことになってしまった。そのため、現在の俺は、芸歴は「真打」なのに、その肩書がない。
師匠や先輩の気分次第ですべてがまかり通ってしまう落語界。これまでは「そういう世界」が答えだった。
だが、パワハラ裁判がはじまって傍聴を続けた俺は、はっきりと気付かされた。この答えは間違っている。
落語家は確かに特殊な仕事かもしれないが、それは芸で稼ぐという部分であって、倫理観までが特殊になるということではない。
吉原馬雀の裁判はいったんは勝訴したものの、控訴され、取り下げられて、結局2年近くかかったが、最終的には勝訴で幕を閉じた。

著者の三遊亭はらしょう氏(本人提供)
「お前は、本を書け」師匠の“遺言”
今の所、関係者たちの意識は以前より変わったように思うが、きっと喉元過ぎれば熱さを忘れる。
俺にはこれからの落語界がどう変わっていくのかは分からないが、これまでのことを残しておくべく、本を書こうと思った。
それが先日発売された小説『俺とシショーと落語家パワハラ裁判』である。
入門してから俺が体験した理不尽、支離滅裂、荒唐無稽の数々と、裁判によって変化していく落語界。そこに登場するのは、奇妙なシショーという男と、振り回される弟子と、これまでの矛盾に気付き裁判を起こす男。
重いテーマではあるが、読みものとしてエンターテイメントにするために40%はギャグを散りばめている(みんな買ってね!)。
宣伝はさておき、ではなぜ俺は本を書いたのか。
実は、生前、師匠の円丈から、 「お前は、本を書け」と言われたのだ。
聞けば、師匠が落語家にしてはたくさん本を書いてきたのは、死んだ後にも自分のメッセージが残るからだという。
確かに、円丈の代表作である実話小説『御乱心』(※)は1978年に起こった落語協会分裂騒動の裏側を実名で描いてベストセラーにもなり、令和の現在でも読み継がれている。もし出版しなかったら、あの大きな出来事はとっくに忘れ去られていただろう。
※1986年『御乱心 落語協会分裂と、円生とその弟子たち』が主婦の友社から刊行。2018年、内容の加筆・修正がされて、『師匠、御乱心!』のタイトルで小学館より文庫で復刊。
「やってみます」
俺は返事はしたものの、書きたいほどのテーマがなかった。
それから一年ほど経って師匠は亡くなった。
俺は日に日に、あれは遺言だったのではないかと思ってきた。俺が書くべきことはなんなのだろうか?
そんな中、吉原馬雀の裁判がはじまった。弟子が師匠を訴えるというのは、俺が知る限りでは落語の歴史の中で初めての出来事だ。
「不自由な時代」ではなく「いい時代」
「そんな世界」だと受け入れるしかなかった落語界に変革期が来ている。俺は書きたいことが、そして死んだ後も残したいことがようやく見つかった!
その日から俺は裁判を追っかけた。
そして傍聴していく中で、過去に円丈から受けた理不尽の数々は、認めたくはなかったが、パワハラだったのだと気付かされた。
だが、俺は師匠を恨んでない。そこは吉原馬雀の場合とは違う。
なぜなんだろう? 散々、酷い目にはあったが、弟子として復帰している。晩年は親子会も開催し、偏屈ジジイと孫のような関係だった。
そう、円丈はいい人だった。亡くなった今、師匠の優しい記憶だけが残っている。何より、円丈のパワハラは支離滅裂すぎて面白い。俺も芸人の性なのか、おいしいと思って笑い話にできる。未だに、師匠の才能に惚れ、ファンであることは変わらない。

『俺とシショ―と落語家パワハラ裁判』
今回の俺の本はある意味『シン・御乱心』だ。
俺が見たこれまでと現在の落語界のありのままを描いた。読了した方からは「円丈が余計に好きになった!」という声も出たほどだから多くの人に読んで頂きたい。
この数年、芸能界、政界とハラスメントが表面化してきた。だが、決して不自由な時代ではなく、いい時代がやって来たのだと思う。
ボブ・ディランの『時代は変わる』ではないが、古い風習を日々アップデートしていく今、「時代は分かる」のではないだろうか。
落語界のおあとが、きっとよろしいようで。
チャカチャンリンチャンリン♪
■三遊亭はらしょう
落語家、作家、俳優。1977年兵庫県神戸市生まれ。2009年4月、落語家三遊亭円丈に入門。2015年から東京演芸協会に所属。古典でも新作でもない実話を落語形式で語る第三の落語「ドキュメンタリー落語」を多数発表。放送作家としては三遊亭円丈の新作落語「牛肉少年」の原作ほか、古今亭菊志ん、キャプテン渡辺などにネタを提供。2013年には自らがメガホンをとった映画『ジャカルタ』を製作。