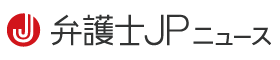一般に、裁判を起こすと莫大な費用と時間がかかるイメージがあります。
特に経済的に困窮している人、生活保護を受給している人は、揉め事や紛争に巻き込まれても、戦う手段を持たずに泣き寝入りするしかない…と考えてしまうかもしれません。しかし、泣き寝入りすれば、不正や理不尽な状態が永続化することになります。
私が深く関わり、その行方を注視し続けている裁判があります。それは、「いのちのとりで裁判」と呼ばれる、生活保護基準の不当な引き下げを巡り、全国の生活保護利用者の方々が国を相手に提起した訴訟です。経済的に最も弱い立場にある人々が、尊厳ある生活を送る権利を求めて立ち上がった裁判です。
この訴訟が報道されるたび、一部で「裁判する暇があるなら働け」といった批判の声が起こります。しかし、訴訟の背景を知れば、それは「不正」を助長し、的外れといわざるを得ないものです。また、憲法はすべての人に「裁判を受ける権利」を保障しています(憲法32条)。
今回は、「いのちのとりで裁判」の原告らが訴訟を提起せざるを得なかった背景と、訴訟が長期化した要因について考えます。(行政書士・三木ひとみ)
生活保護受給者が提起した「いのちのとりで裁判」
「いのちのとりで裁判」は、2013年から2015年にかけ、国が史上最大幅の生活保護の基準額引き下げを行ったことが、憲法25条が保障する生存権の侵害にあたり違憲だとして、全国で提起されている訴訟です。
当初こそ原告の敗訴が続いていましたが、昨今は相次いで勝訴判決が出され、地裁も高裁も原告が勝ち越しています(2025年4月14日現在、地裁は19勝11敗、高裁は6勝4敗)。これは行政裁判では異例です。そして、今年7月までに最高裁の判決が行われる見込みです。
「いのちのとりで裁判」は2014年に提訴され、2025年4月現在、すでに提訴から11年という歳月が経過しています。この長期化は、原告である生活保護利用者の方々の生活に深刻な影響を与えています。
高齢化が進み、病に苦しみ、志半ばで亡くなられた方も少なくありません。提訴当初は全国で1000人を超えていた原告の数は、現在では900人を下回っています。
この裁判がこれほどまでに長期化した背景には、原告側と行政側双方の、複雑で困難な事情が絡み合っていました。
原告側の事情:脆弱な経済基盤と「統計不正」
原告の多くは生活保護利用者であり、経済的な基盤が脆弱です。そのため、弁護団の弁護士たちは、十分な報酬を得られるわけではなく、多くの方が文字通り「持ち出し」でこの裁判に取り組んでいます。
潤沢な資金を持つ弁護団と比較すると、人員体制や調査能力において、どうしても限界がありました。もし原告側に十分な資金力があれば、主張をより迅速かつ精緻に構築できたことは想像に難くありません。
さらに、この裁判の核心的な争点の一つである、厚生労働省が2013年の生活扶助基準改定の根拠とした統計データには、「物価偽装」や「2分の1処理(※)」といった重大な統計不正が行われた疑いが濃厚でした。
※低所得者世帯の消費水準の指数に1/2をかける処理
原告側が、この複雑で巧妙な統計操作のカラクリを解明し、裁判所に対し説得力を持って説明できるようになるまでには、膨大な時間と労力を要しました。
2019年の通常国会で統計不正問題が初めて大きく社会的な注目を集めるまで、一般には「統計不正」という概念すら浸透していなかったため、原告側関係者も、統計の専門的な知識を持つ人材を確保することが極めて困難でした。
そのような状況の中、元中日新聞記者でフリージャーナリストの白井康彦氏と数名の弁護士が、物価指数計算の基礎的な仕組みから徹底的に研究を重ねました。これは、気の遠くなるような時間のかかる作業であり、さらに、この不正を裏付ける専門的な知見を持つ物価指数研究の学者を原告側の証人として法廷に立たせるまでにも、長い年月を要したといいます。
また、「2分の1処理」という、生活扶助基準をさらに不当に引き下げるための隠蔽された手法については、行政側がその存在自体を秘匿していました。この事実が明るみに出たのは2016年になってからであり、全国弁護団もそこから「2分の1処理」に関する調査と研究を開始せざるを得ず、物価偽装問題に比べて、どうしても取り組みが遅れてしまいました。
裁判の過程においても、国(厚生労働省)側は具体的な計算過程を示す資料をかたくなに開示せず、原告側の主張立証活動をさらに困難にしました。「実行したことすら秘匿した」という事実は、「2分の1処理」という手法の異常性を如実に示しています。
生存権(憲法25条)という基本的人権の範囲を具体的に定める行政処分の取り消しを求めるこの重要な裁判では、行政裁量論、生活保護利用者の方々の過酷な生活実態、現代社会における貧困問題、憲法解釈、行政手続きの適正性など、多岐にわたる法律的、社会的な論点を精緻(せいち)に主張していくことが不可欠でした。
そのため、各分野の研究者からの意見書を収集したり、弁護団が詳細な準備書面を作成したりするのにも、多くの時間が費やされました。
国側の「責任回避と時間稼ぎ」も長期化に拍車をかける
さらに、裁判が進むにつれて、国側は当初の主張を大きく変更することがありました。これは、一審、二審で原告側が一部勝訴する判決が出始めたことへの対応と見られます。
行政側の主張の変遷に対して、原告側が的確に反論していくためにも、また時間を要することになりました。
2013年の生活扶助基準改定という行政処分の根幹部分において、厚生労働省が統計不正という「禁じ手」に踏み込んだ背景には、当時の政権与党、特に自民党からの強い圧力があったとされています。裁判所の判決の中には、その点をはっきりと明記したものもあります。
もしこの裁判で、最終的に行政処分の取り消しが確定した場合、その影響は甚大です。過去の過誤が明確になり、生活保護利用者への不当な給付抑制が行われていた事実が確定すれば、厚生労働省や当時の政権与党の責任問題が大きくクローズアップされることは避けられません。
生活扶助相当CPI(※)の計算が明らかに異常であると専門家に指摘されても、国側が「計算値がたとえ不正確であったとしても、それは行政の裁量権の範囲内である」といった主張を繰り返してきたことに対し、白井氏は強い憤りを覚えたと言います。
※厚生労働省が独自に作成し、生活扶助基準引き下げの根拠とされた消費者物価指数(2013年1月公開)。
報道も盛り上がらず…
行政側にとって不幸中の幸いだったのは、「いのちのとりで裁判」に関するマスメディアの報道が、その重要性にもかかわらず、十分に盛り上がらなかったことかもしれません。
生活保護というテーマは、一部で根強いバッシングが起こりやすい上に、この裁判の法廷では、複雑な統計の論点に関する専門的な主張や反論が頻繁に繰り広げられました。
そのため、憲法、生活保護法や統計学の知識を持たない多くの記者にとって、裁判の内容を深く理解し、一般の読者に分かりやすく伝えることは困難であり、結果として深く踏み込んだ報道がされなかったという側面があります。
このように、「いのちのとりで裁判」の長期化は、原告である生活保護利用者の方々にとって、精神的にも肉体的にも大きな負担となっています。
「いのちのとりで裁判」が問いかけるもの
「いのちのとりで裁判」の長期化は、単に個別の訴訟の遅延という問題に留まりません。それは、行政が重要な政策決定を行う際に証拠として示す統計数字を「都合よく作る」ことが国、厚労省で行われているという、より根深い構造的な問題を示唆しています。
もし、そのような行政行為に重大な不正が露見した場合には、すみやかに実態解明を進め、それら不正に基づいた政策決定は直ちに停止されるべきです。しかし、現状は理想の体制にはほど遠いと言わざるを得ません。
2013年の生活扶助基準改定は、2013年1月27日に改定案が公表され、行政処分が実行されたのが同年8月1日という、極めて短期間での強行でした。
同年の通常国会で、野党議員から「生活扶助相当CPIの計算がおかしい」という具体的な指摘が強く出されましたが、当時の政権与党はこれを完全に無視しました。もしこの時点で、行政処分の実行を一旦中止し、国民の疑問に真摯に向き合って基準改定案を作り直していれば、そもそも、これほど長く苦しい裁判闘争は起こらなかったはずです。
また、前提となる統計データに重大な疑義が生じた場合は、独立した機関による徹底的な検証作業が開始される体制を確立することが不可欠です。
統計委員会がその検証作業を実行するのが最も適切であると考えますが、現状では、統計委員会の検証対象は定期的に公表される基幹統計を原則としています。統計委員会の権限を拡充し、迅速かつ専門的に検証作業を行えるよう、法令で明確に定めるべきです。
さらに、このような疑義が生じた場合には、統計データの作成に至るまでのすべての関連文書の公開を義務付けるべきでしょう。
経済的弱者の「裁判を受ける権利」を支える制度
「いのちのとりで裁判」では、前述のように、原告弁護団の弁護士たちは多くの方が「持ち出し」で弁護活動を行っています。しかし、個々の弁護士が使命感や良心によって協力してくれるのには限界があります。
実は、わが国には、経済的に困窮している方や生活保護を受給している方が、裁判を受けられるための公的な支援制度が存在します。そのような制度をごく端的にではありますが、紹介します。
まず、裁判手続きにかかる費用(訴訟費用)は、経済的に困窮して支払いが難しければ、「勝訴の見込みがないとはいえない」を条件に、裁判所への申し立てにより、裁判費用の免除や猶予を受けることができます(民事訴訟法82条)。
「勝訴の見込みがないとはいえない」というのは緩やかに解されており、請求の内容がよほど無理筋のものでない限り認められるという意味です。
次に、弁護士費用は日本司法支援センター(法テラス)による援助があります。生活保護受給者の方は、原則無料で法律相談ができます。また、弁護士に依頼する場合、弁護士費用の立て替えを受けることが可能です。
立て替え金は、原則として利用者が返済しなければなりませんが、生活保護受給者の方については、収入が見込まれないケースでは、基本的に立て替え分の返済が免除となります。また、返済の免除がされない場合でも、分割払いが可能です。
生活保護受給者の方は、担当のケースワーカーに相談すれば、近くの法テラスの相談窓口を案内してくれるはずです。
他にも市町村などの地方自治体が無料で法律相談センターを開催している場合があります。また、各地の弁護士会で独自に支援を行っている場合もあります。
裁判を受ける権利を守る「経済的支援」と「司法へのアクセス」の重要性
憲法がすべての人に保障している「裁判を受ける権利」を真に確保するためには、経済的な側面からの支援制度は不可欠です。そして、「いのちのとりで裁判」が長きにわたり続いている現状は、行政による政策決定の不透明さと、それに対し正義の実現を求める国民が、いかに困難な状況に置かれているかを如実に示しています。
もしあなたが今、何らかのトラブルや困ったことに直面し、生活保護を受けていて経済的な余裕がない。あるいは、弁護士に相談したくても費用が心配で諦めかけている、という状況にあるならば、決して一人で抱え込まないでください。
法テラスをはじめとして、困難な状況にある方へのサポートを惜しまない制度や人々が必ずいます。そして、必要であれば、勇気をもって理不尽な状況に声を上げ、「いのちのとりで裁判」の原告の方々のように、 司法の力を借りて戦うことをためらわないでほしいと、心から願っています。
三木ひとみ
行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)。官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。