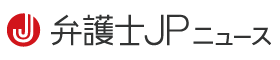詐欺被害はその悪質性が報道などで明るみになることが多いが一向に減る兆しがない。認知件数、被害総額は年々増加傾向だ。
警察が対策に乗り出し、人々の警戒も強まっている。それでも詐欺集団はその裏をかいてくる。「お金の受け取り方ひとつをとってもバレないようやり方を微妙に変えてくるんです」と詐欺に詳しいルポライターの多田文明氏は話す。
まさにあの手この手で、詐欺集団が捜査陣、ターゲットをだます「スライド型」と呼ばれる手口を、多田氏が解説する。
※ この記事は悪質商法コラムニスト・多田文明氏の書籍『最新の手口から紐解く 詐欺師の「罠」の見抜き方 悪党に騙されない40の心得』(CLAP)より一部抜粋・再構成しています。
振込詐欺に透ける「スライド型」の手口
スライド型といわれる手口が、もっとも顕著に表れているのは、振り込め詐欺における金の騙し取り方だ。
この犯罪が出始めた当初は、その名前の通り、騙し取った金を銀行のATMから振り込ませる形で送金させていた。
ところが、警察と銀行が連携し、人々に注意を呼び掛けた結果、振り込め詐欺に使われたと思われる銀行口座は、警察に通報されるとすぐに凍結されるようになった。
詐欺師からみれば、せっかく口車に乗せて騙し取れそうになった金を、最終の受け取り段階で逃がすことになる。
さらに詐欺師たちにとって状況は悪化した。「振り込め詐欺」という言葉が世に知られるようになり、「ATMへの振り込み=詐欺」という認識が多くの人にでき上がり、詐欺自体がやりづらくなってきた。
警察庁が発表した統計を見てみても、それがわかる。平成20年の振り込め詐欺を含む特殊詐欺の被害は2万481件で、被害総額は275億9000万円だった。
それが、平成21年度は7340件、被害総額は95億8000万円に激減し、翌年も6888件、112億5000万円だった。
このまま振り込め詐欺は下火になり、根絶されると思われたーー。
金の受け取り方にバリエーション
ところが、ここで詐欺師たちは知恵を働かせる。金の受け渡し方法にバリエーションを加えたのだ。銀行での振り込みをなるべく回避して、郵送や宅配を使う方法にシフトしてきた。
騙し取った金を、会社の住所だけが置いてある私書箱や、空きアパートなどの住所に送る手を使うようになった。空きアパートは郊外に多数あり、そこを内覧する人のために、鍵をポストや水道メーターのところに置いておくことがよくある。詐欺犯はその鍵を勝手に使い、空き部屋内で荷物を受け取るのだ。これにより、足が付かずに現金を受け取ることができる。
最初はうまくいっていたものの、そのうち詐欺に使われた郵送先が警察に摘発されたり、送金先だったアパートが次々にマークされて、この手口も行いづらくなる。すると、今度はバイク便などを使う形を考え出した。
すでに逮捕されている事例もあるが、詐欺をするためだけにバイク便の会社を立ち上げるケースも出てくるほどだった。
このように、お金の受け渡し方法をスライドさせながら、バリエーションを増やしていったため、徐々に被害が広がっていった。
「非対面」から「対面」への大転換
被害が広がった理由は、なんといっても手渡し型が出てきたことがもっとも大きいだろう。それまでの詐欺は、電話のみのやりとりで金を騙し取る形だった。非対面でお金を取る方が逮捕されるリスクも低く、効率的に詐欺を行えたからだ。
私もこの当時は、講演やテレビに出演する際には、「詐欺師は家にこないので、お金の請求を受けて『自宅はわかっている。今から行くぞ!』と脅されても、臆する必要はありません。きっぱりと、断りましょう」ということを、徹底して訴えてきた。
ところが、ATMでの振り込みが厳しくなると、詐欺師たちは逮捕されるリスクも十分承知したうえで、息子の同僚、部下などを装い、お金を直接自宅に受け取りにくるようになったのだ。銀行口座のように凍結されることもなく、確実に金を受け取れるというわけだ。
ここでついに、非対面式から対面式への大きなパラダイムシフトが行われたのだ。それまでは、「電話による詐欺では、逮捕されるリスクを恐れて、詐欺師は家にやって来ない」ということが常識だったが、それが破られた瞬間だった。それにより、一気に詐欺の被害が広がっていった。
平成26年には、被害件数は1万3392件、被害額は565億5000万円で、過去最悪となった。直近の平成29年も1万8201件、3903億3000万円と、今なお、高い数字となっている。
逮捕リスクを織り込む詐欺師たち
むろん、警察も黙っていない。電話がかかってきた家人に騙されたフリをしてもらい、自宅を訪れた犯人らを逮捕する「騙されたフリ作戦」の手法を取るようになる。
だが、逮捕リスクは詐欺犯らの想定の範囲内である。彼らはリスクヘッジの方法として、もし金の受け渡しをする受け子が捕まっても、その上の人間が芋づる式に捕まらないようにして、詐欺を継続できるようにしていたのだ。
そこで、詐欺の電話をかける「架け子」のグループと、お金を受け取る「受け子」のグループを非対面でつなげて、対面での関係を断つようにしていた。それゆえ、警察による「受け子」の検挙数は上がるものの、なかなか組織の上部にまではたどり着けない状況が続く。それは、電話をかける「架け子」というグループも同様だ。
もし架け子のアジトが摘発されても、その運営を指示する人間までには到達できないようにしておく。そうすれば、首謀者が新たな架け子グループを立ち上げれば、同じ詐欺が継続して行えるという仕組みになっている。
いずれにしても、どこの組織が捕まっても、すぐにトカゲのしっぽ切りができる状態で詐欺ができる態勢を組んでいる。それゆえに被害はなかなか減らないのだ。
逮捕リスクを減らすために横行した「呼び出し型」とは
確かに、受け子は切り捨てられる存在だ。そうだとしても、詐欺組織にとってお金を運んでくる重要な駒であることには違いない。そのため逮捕のリスクを減らす努力も欠かさない。
家を訪ねていっては逮捕される可能性が高いと思えば、手口を少しスライドさせた。被害者を近くの駅や公園などに呼びだして、お金の受け渡しをさせるようになる。いわゆる、「呼び出し型」という詐欺の横行である。
呼び出し型にすれば、受け渡し場所をコロコロと変えながら、相手の状況を遠くから見て、周りに警察がいるかどうかを伺い知ることができる。若干ではあるが、逮捕されるリスクを減らせる。そこで、受け子を見張る役も配置して、確実にお金をゲットできるようなシステムを構築していった。
ただし、ここで問題になるのは、悪事の一助を担ってくれる「受け子」の手配である。詐欺のターゲットになる人は全国にいる。騙した相手のもとにいくためには、その地域に受け子を向かわせなければならない。これはなかなか手間だ。
人の多い首都圏であれば受け子を用意するのは比較的容易だが、都心から離れた地方となれば、人口も少なく、受け子の手配がしづらかった。そこで、詐欺師たちはまた頭を働かせた。
被害者を遠方に「呼び出す」手口とは?
考え出されたのは、遠方から新幹線などの鉄道を使って、東京、大阪、福岡などの首都圏に呼びよせる方法である。それにより、首都圏から新幹線で2~3時間圏内のエリアに被害が集中した。なかには、飛行機を使って、羽田や成田の空港まで金を持ってこさせる手口まで出てきた。いわゆる、上京詐欺の横行である。
つまり、お金は「取りに行く」ものではなく、「持ってきてもらう」という発想に、またもや大きく変えていったのだ。
いまもなお、地方に住む高齢者が、偽の息子に東京や神奈川、大阪、名古屋などの都市部に呼び寄せられて、お金を渡してしまう被害が全国で後を絶たない。
ここから見えてくるのは、これまでの手口がやりづらくなる状況になれば、手口を少し横滑りさせながら、私たちの目を惑わすような手法を編み出すということだ。そして、ある時に大きなパラダイムシフトを起こして、一気に私たちの持っている詐欺対策や常識を覆していく。
ひとことでいえば、騙しとは、私たちの持つ考え方の裏をいかにつくか、という頭の働かせ方だ。その洗練された術により、いまもなお、多くの被害者が続出している。