◆精神鑑定医「説明は了解できる」/遺族へ初めて謝罪
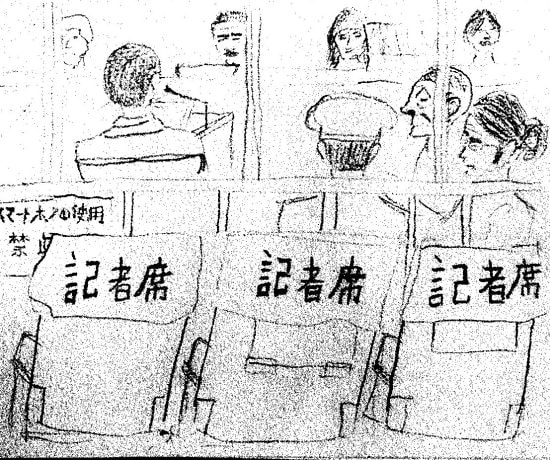
弁護側の被告人質問の最後に、被告は遺族へ「私が安倍元総理を殺害し、3年半非常につらい思いをされてきた。弁解の余地はなく、非常に申し訳ない」と初めて謝罪を表明した。事件後に統一協会問題が社会化し、解散命令へ動いたことについては「ありがたい」と述べる一方、模倣犯や陰謀論が生まれた責任の重さにも言及した。
裁判長は倫理的歯止めについて問うた。被告は「人を死なせてはいけないというルールを超えてしまった部分」を認めつつ、安倍氏が「全く関係なかったわけではない」という認識が切り替わらなかったとも述べた。裁判員から最後の被告人質問で質問が出なかったのも印象的だった。
◆何が「飛躍」だったのか
検察や多くの報道では、山上被告が事件の5日前、2022年7月3日に安倍元首相を狙う決意を固めたとされ、統一協会幹部から安倍氏へと標的が「突然切り替わった」かのように語られてきた。だが、14回にわたる公判で被告本人、家族、専門家の証言を聞く限り、その説明だけでは法廷で明らかになった事実を十分に説明しきれないと、私は感じた。山上被告は繰り返し、「安倍氏を襲いたいという気持ちは2003年ごろから頭の片隅にあった」と述べている。主たる標的が統一協会の組織や最高幹部であったとしても、安倍氏は「次に狙うべき対象」として、長年、被告の認識の中に位置づけられていた。これは、事件直前の思いつきや衝動だけで説明できるものではない。
また、母親や妹の証言からは、家庭内で安倍氏が「統一協会と政治をつなぐ象徴的存在」として、日常的に語られていた様子が浮かび上がる。統一協会系の媒体や関連団体のイベント、信者からの働きかけを通じ、安倍氏の存在は被告の生活空間の中に繰り返し現れていた。被告が安倍氏を「教団と政治の関わりの中心にいる人物」と認識していった過程は、断続的ではあっても、連続性を持っていたと言える。
確かに、教団幹部への直接的な襲撃が困難になり、経済的に逼迫する中で、最終的に安倍氏への襲撃を選択した点には、状況的な要因が重なっている。しかしそれは、「標的の飛躍」というよりも、被告の中で既に用意されていた選択肢の中から、実行可能性の高い対象へと収斂していった過程と捉える方が、法廷での供述には整合的ではないか。
裁判員や裁判官の質問もまた、単なる動機の単純化を求めるものではなかった。「なぜ人を殺してはならないという倫理が歯止めにならなかったのか」「どこで考えが切り替わらなかったのか」という問いは、被告の内面の固定化や、長期にわたる思考の積み重ねを前提として投げかけられていたように思う。
14回の公判を通じて、少なくとも「なぜ安倍氏だったのか」という問いに対する被告なりの説明は、断片的ながらも相当程度言語化された。納得するかどうかは別として、それを「論理の飛躍」と一言で片づけてしまえば、この裁判が明らかにした構造的な問題ーー宗教2世の孤立、救済の遅れ、政治と宗教の距離の曖昧さを見失う危険がある。
<取材・文/浅野健一>
【浅野健一】
1948年、香川県高松市生まれ。72年、共同通信社に入社。84年『犯罪報道の犯罪』(学陽書房)を発表。ジャカルタ支局長など歴任。94年に退社。94年から2014年まで同志社大学大学院メディア学専攻教授。人権と報道・連絡会代表世話人。『記者クラブ解体新書』(現代人文社)『安倍政権・言論弾圧の犯罪』(社会評論社)『生涯一記者 権力監視のジャーナリズム提言』(社会評論社)など著書多数。 Xアカウント:@hCHKK4SFYaKY1Su


