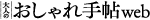生まれ育った奈良を拠点に映画づくりに取り組みながら、高い芸術性でフランスをはじめ世界から評価を受ける映画監督・河瀨直美さん。新作『たしかにあった幻』では、臓器移植治療と失踪者問題というふたつの社会的課題を軸に、愛の本質を問いかけます。大切な存在は、いついなくなるかわからない。でも、たとえ姿が失われたとしても、心のなかにその魂は永遠に宿り続ける――死や別れを乗り越えて続く絆の存在を信じたくなる一作がどのように生まれ、育っていったのか。創作の軌跡を尋ねました。
他者を受け入れず、幸せを喜べない閉塞感のなかで

劇場公開デビュー作『萌の朱雀』でカンヌ映画祭カメラドール(新人監督賞)を最年少受賞し、27歳で世界にその名を広めた映画監督・河瀨直美さん。以降、男と女、親と子、さらには生者と死者、人と土地など、さまざまなシチュエーションでの愛とつながりを描いてきました。まもなく公開される『たしかにあった幻』は、劇映画として6年ぶり、オリジナル脚本作品としては8年ぶりとなる新作。神戸の病院で小児の臓器移植治療に携わるフランス人女性・コリーを主人公とする物語で題材としたのは、「臓器移植」と「失踪」。一見、関連を見出しにくいこのふたつが、河瀨さんのなかで時間をかけて結びついていったと言います。
「最初は、年間8万人もの失踪者がいると聞いて『なぜ日本ではこんなにも失踪者が多いんだろう?』と感じたことがはじまりでした。その現象からは、長いものに巻かれないと安全にはいられない日本社会の閉塞感が見えてきますし、一方で、人には探されない、どこかへ行って生き直せる自由もあるんじゃないかとも感じられたんです。そして同じ頃、海外の病院で行われる臓器移植の無許可斡旋が摘発されたことをニュースで知りました。思えば、臓器移植にも、法律上の諸問題や家族の負担だけでなく『人の臓器を奪ってまで生きるのか』と他者から言われかねない社会のなかで、移植を受けた人たちがその事実を隠して生きていかなくてはならないような現実があります。つまり、今の日本は他者の生き方を受け入れられず、幸せを喜べない世の中になっているのかもしれない……外国人であるコリーの眼差しを通してそれを描き出すことができたら、どんなふうに受け取ってもらえるだろうか?と」
困難なときほど広い世界に耳をそばだて、心を開く

欧米では「Gift of Life(=命の贈りもの)」と呼ばれる臓器移植。しかし、生命に対する倫理観などの違いから遅々として環境整備が進まない日本で、コリーは患者家族に寄り添いながら、困難な仕事に取り組みます。さらに彼女の心を揺らすもうひとつの存在が、旅先の屋久島で出会った恋人・迅。暮らしをともにしながらも、自分の来歴や心情をほとんど語ろうとしない彼への不満がつのり、ある日、言葉を荒らげてしまうコリー。翌日、彼は姿を消し、その足跡を辿るなかで、コリーは迅が家族の元から失踪していた事実を知るのです。
「臓器移植という命の橋渡しや、愛する人を失うという現実に正面から向き合えるコリーは、とても強い女性だと思います。泣くときは泣くけれど、それでもいつかは立って、自分の行く先を見つけられる人」
彼女の強さは「聞く耳を持っていること」に根ざしていると、河瀨さん。映画のポスターには彼女が耳に手のひらをかざし、後ろ側の音を聞き取ろうとする様子が写し出されていますが、これはより広い世界に耳をそばだて、ものごとの道理を悟ろうとしていることの象徴。女性が社会で生きていくうえで、困難に対峙する際の姿勢にも通じるといいます。
「結婚し、出産して、家庭を築きながらキャリアも伸ばす。今の世の中、やはり女性に強いられていることはまだまだ多く、しかもそれを後押ししてもらえるような空気ではありませんよね。だから、そのハードルを超えていくというよりは、自分を開き、他者を受け入れ、自分とその周りにある世界を慈しむ……葛藤を抱え、愛した存在が幻だったとしても、行動を起こしたことは何かにつながっていくし、その道の終わりには必ず光が差すはず。そんな感覚を、コリーを通して味わっていただけたらと思っています」