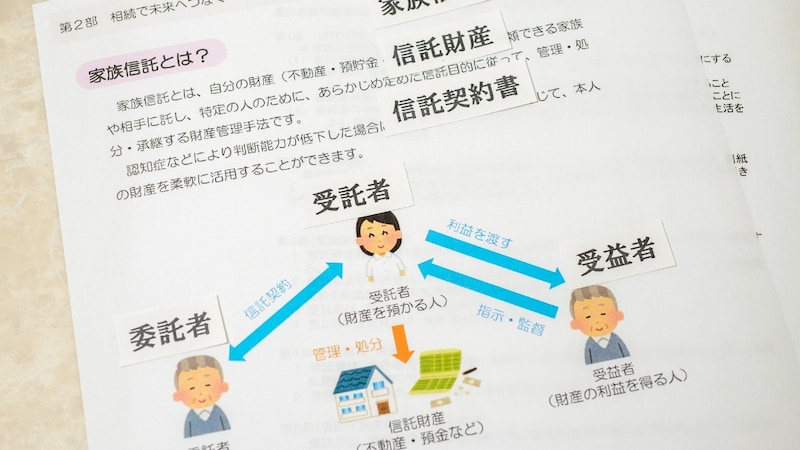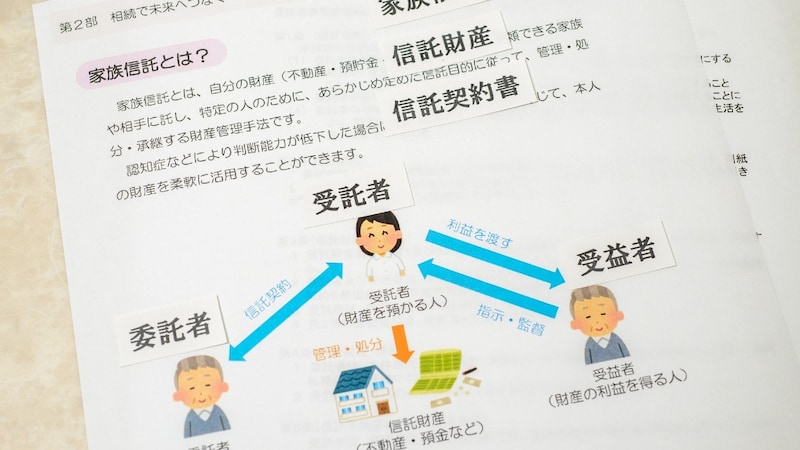
認知症などで判断能力が低下した人の契約や財産管理を支える成年後見制度について、制度のあり方そのものを見直す動きが進んでいます。法制審議会の部会は、現行制度を大きく転換する要綱案を取りまとめ、政府は2026年度中の民法改正を目指す見通しです。今回の見直しは、制度を利用する本人だけでなく、家族の関わり方にも影響を及ぼす可能性があります。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。
現行制度、「本人の自己決定権」を過度に制限か?
現行の法定後見制度では、判断能力の程度に応じて「補助・保佐・後見」の3類型が設けられています。
とくに「後見」に該当すると、原則として後見人が広範な代理権を持ち、本人の法律行為は大きく制限されます。また、判断能力が回復しない限り制度の利用を終了できず、結果として事実上の終身制度となるケースもありました。
この点が、本人の自己決定権を過度に制限しているのではないか、という問題意識につながっています。
要綱案の柱① 3類型の廃止と「補助」への一本化
要綱案では、現行の3類型を廃止し、法定後見を「補助」に統一するとされています。
今後は、遺産分割や不動産処分などの個別の法律行為ごとに本人の同意を求め、家庭裁判所が必要に応じて補助人に代理権を付与する仕組みが想定されています。
これは、包括的に代理権を与えるのではなく、必要な場面・必要な範囲に限って支援するという考え方への転換といえます。
【家族が知っておくべき点】
今後は、「一度後見が始まったら、すべてを任せきり」という関係にはなりにくく、その都度、本人の意思確認や家庭裁判所の関与が前提になる可能性があります。家族にとっても、制度を「一任して終わり」ではなく、継続的に関わる場面が想定されます。