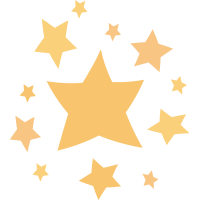2000年以降、監獄法、刑事訴訟法、刑法など明治時代や戦後すぐにできた古い法律の改正が続いた。法務省でその舵取りをしたのが元検事総長の林眞琴氏だ。
検察官・法務官僚として奉職した39年間、組織の不祥事に向き合ってきた。2022年に退官すると、大手企業法務事務所という異なる世界に飛び込む。そこでも旧ジャニーズ事務所の性加害問題に切り込み、辣腕を振るった。(弁護士ドットコムニュース編集部・山口紗貴子、写真/永峰拓也)
●ジャニーズ性加害「法を超えた救済」を提言
「踏み込んだな」
2023年8月29日午後。都内の会議室に集まった記者たちから驚きの声が次々に漏れた。
英BBCや「週刊文春」の報道により明らかになった旧ジャニーズ事務所の創業者、故・ジャニー喜多川氏による所属タレントらへの性加害問題。事務所が立ち上げた「外部専門家による再発防止特別チーム」の座長として、陣頭指揮をとったのが林氏だった。
この日、特別チームは事務所に調査報告書を提出後、記者会見を開く。会見場では事前に、記者たちに67ページの報告書が配布されていた。
そこにあったのは、ジャニー氏や事務所役員らを厳しく非難する文言だった。
被害について〈多数のジャニーズJr.に対し、長期間にわたって広範に性加害を繰り返していた事実が認められた〉〈ジャニー氏に顕著な性嗜好異常が存在していた〉として、被害者への謝罪と救済を求めたさらに、同族経営の弊害、取締役会の機能不全と各取締役の監視・監督義務の懈怠などを指摘し、藤島ジュリー景子社長の辞任にも言及した。
速報記事を出すべく、会見を前に慌ただしい雰囲気となった。
林氏は会見で「マスメディアから強い報道、批判が出ていれば、事務所が隠蔽の対応を改め、防止するための自浄作用を働かせられたかもしれない」と、メディアの姿勢に疑問を投げかけることも忘れなかった。
それから約5カ月後、今回のインタビューが実現した。詳細については「守秘義務があるため話せません」とする林氏だが、特別チームの仕事は「検事としてのキャリアが役立ったのかと言えば、逆だと思います」と話す。
「私はコーポレートガバナンス、ビジネスと人権の観点で関わりました。調査では、ジャニー喜多川氏がいつ、どこで、誰に対してどのような性加害をしたのかという詳細な事実認定はしていない。ご本人も亡くなっていますし、時間も経過している。名乗り出た被害者もまだ決して多くはなかった時点で個々の事実認定をどう進めるのか。詳細な証拠を集めて刑事責任を緻密に立証していく検事の手法は、事案の全体像を明らかにする上でむしろ適切ではないと考えました」
「再発防止策を考えてくださいというミッションなのだから、概括的な事実認定ができればいい。検事であれば緻密な証拠を求めることになります。とても“法を超えた救済”とはいえませんからね」
その後、旧ジャニーズ事務所は「SMILE-UP.」に社名を改め、タレントのマネジメント業務は新会社で行うと発表。すでに被害者に対する補償も始まっている。検事総長を退いて、1年余り。検察組織で培った改革手腕を、民間でも惜しみなく振るった。

●「職場の雰囲気が温かった」検察官志望の理由
愛知県豊橋市に生まれた。戦後、宮大工となった父は、一般大工の棟梁として事業を営んでいた。中学を卒業したばかりの10代の少年たちが大工見習いとして住み込みで働く。彼らにかわいがられ、父母や姉とともに家族のように育っていく。
旧吉田藩の藩校(1752年創設「吉田藩時習館」)の名称を受け継ぐ名門校、愛知県立時習館高校(豊橋市)に進学した。部活は中学から始めたテニス部。成績は良かったものの、政治問題を論じるような早熟なタイプではなく、「平凡だった」と振り返る。
「当初は家業を継ぐため建築学科を検討していましたが、絵が下手で、これでは建築家にはなれないと悟りました。法学部に進学したのは、進路指導の先生に『文系なら法学部が潰しがきく』と言われたのがきっかけです。今とは違って、当時は法学部にいけば会社員、役人、弁護士、何にでもなれるという時代だったんですね」
現役で東大法学部に進学するが、そこで初めての逆境を味わった。
周りは“教育大駒場”(現在の「筑波大学附属駒場高校」)や灘の出身ばかり。孤独を感じ、徐々に大学へは足が遠のいた。語学など最低限の講義にしか行かず、かといってクラブ活動やアルバイトに精を出すわけでもない。卒論は無いし、必須ではないからゼミにも入っていない。
「だからご学友は?と言われても、いないんです。振り返れば平野龍一さん、松尾浩也さんなど名だたる法学者が教壇に立ち、後に学者となる酒巻匡さん、佐伯仁志さんら同級生たちにも囲まれていたわけですが、それがわかるのは後に検事となり、法務省で法制審議会にかかわるようになってからでしたね」
奮起するのは大学3年生の秋になってのこと。国家公務員上級職や司法試験受験を決意する。合格率はまだ2、3%。500人弱しか突破できない時代だ。
「この時点では何になろうというより、試験を突破することだけを考えていました。当時まだ少なかった司法試験塾には通わず『受験新報(』中央大学真法会・編)を読んで司法試験のことを知り、基本書を読みノートにまとめたりして独学で勉強を始めました」
翌年には短答式に合格するも、論文で失敗。留年した5年時に合格した。この年(1980年)の司法試験では、28,656人の出願者に対して合格者は486人。合格率は1.7%という狭き門だった。
当時は2年間の司法修習期間があり、1年4カ月の実務修習は岐阜で行った。検事を志すようになったのは実務修習が終わり、東京・湯島にあった司法研修所に戻る直前のことだったという。決め手は修習を通して感じた検察組織の雰囲気だった。
「検察庁の9割は検察事務官たちなんですね。事務官の人たちが非常に温かかった。弁護士事務所は小さな組織ですし、裁判所は検察庁に比べると、人間関係はもう少しあっさりしていました。大工の見習いの若い人が住み込みでいた実家と検察は温かい雰囲気が似ていたんですね。それが決め手だったと思います」
配信: 弁護士ドットコム