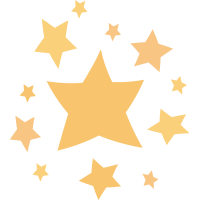生命に関わる小児がんの後遺症
生命に関わる小児がんの後遺症を以下で詳しく解説します。
二次がん
小児がんの治療後、生命に関わる後遺症として二次がんのリスクが高まります。特に、化学療法で使用されるアルキル化剤(シクロフォスファミドなど)、トポイソメラーゼ阻害剤(エトポシドなど)、アントラサイクリン系抗がん剤(ドキソルビシンなど)は、骨髄性白血病や骨髄異形性症候群などの二次がんを引き起こすリスクがあります。
放射線治療も、治療を受けた部位に関連した二次がん、例えば頸部や胸部の放射線照射後の甲状腺がんや乳がん、肺がんが発生するリスクがあります。
二次がんは、治療完了後数年から数十年後に発症する可能性があるため、長期的なフォローアップと定期的なスクリーニングがとても重要です。
心機能障害
小児がんの治療による心機能障害は、アントラサイクリン系抗がん剤(例:ドキソルビシン、ダウノルビシンなど)の使用により発生することがあります。これらの薬剤は心臓に毒性を示し、使用量が増えると心筋へのダメージが蓄積され、拡張型心筋症や心不全などの深刻な症状を引き起こすリスクが高まります。
なかでも若年で治療を受けた患者さんでは、成長とともに心臓への負担が増大し、思春期に症状が顕著になることが多いとされています。心機能障害を予防または発見するためには、定期的な心機能評価が推奨されます。
呼吸器障害
小児がん治療後、ブレオマイシンやカルムスチンなどの化学療法、または胸部放射線療法などの治療により肺の晩期合併症リスクが増大します。晩期合併症にはホジキンリンパ腫やウィルムス腫瘍、幹細胞移植を受けたがんが含まれます。
肺の機能が低下し、慢性的な呼吸困難、持続的な咳、その他の呼吸器系の問題が生じる可能性があるため、適切な診断と早期の介入が重要です。
妊娠に影響する小児がんの後遺症
小児がんの後遺症は妊娠にも影響を与えるのでしょうか?以下で詳しく解説します。
妊孕性(にんようせい)の低下
妊孕性、すなわち妊娠しやすさは、抗がん剤治療や放射線治療により影響を受けることがあります。子宮、卵巣、精巣など生殖器官への治療が直接的な影響を及ぼし、将来妊娠しにくくなる可能性があります。
しかし、医療進歩により、若年がん患者さんの妊孕性の温存が可能とされており、がんに関する生殖医療は、地域ネットワークを通じて支援が強化されているため、不妊に関する不安がある場合は、医師に相談し、適切な情報と支援を求めることが重要です。
性腺機能異常(せいせんきのういじょう)
性腺機能異常は、中枢性と原発性に大別され、それぞれが視床下部・下垂体異常や性腺自体の異常に起因します。抗がん剤や放射線治療は、性腺刺激ホルモンの分泌不全や性腺への直接的なダメージを引き起こし、妊孕性の低下につながります。
男児では精子産生に必要な細胞が、女児では原始卵胞数の減少が見られ、それぞれ妊孕性への影響が懸念されます。このため、がん治療後は定期的なホルモン検査や生殖機能の評価が必要です。
配信: Medical DOC