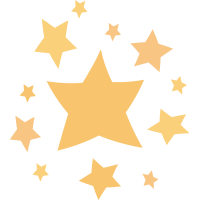テレビやネットで報じられる殺人事件に触れ、亡くなった被害者への同情を覚えることは少なくありません。例えば、親の介護に疲れ果ててしまい、やむを得ず親を殺してしまった人々や、被害者から「お願いだから殺してくれ」と頼まれ殺したケースなど、これらの事例において、刑法199条がどのように成立し、処罰されるのかについて知りたいと思う方も多いでしょう。
今回の記事では、刑法199条の殺人罪の構成要件や、単純殺人罪との違い、また有罪となった場合の執行猶予に関する疑問に答えつつ、分かりやすく解説いたします。刑法199条がどんな状況で成立するかについて疑問を抱いている方のお役に立てれば幸いです。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、刑法199条の殺人罪(単純殺人罪)の定義と刑罰

刑法199条の殺人罪は、人を殺した場合に成立します。殺人罪が成立した場合の刑罰は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となっています。
人の生命という、人間にとって最も重要なものが保護法益となっているため、死刑も含む重い刑罰が定められています。
殺人罪の構成要件となる、人を殺す行為を実行しても、必ずしも被害者が死亡するわけではありません。被害者が死亡していないのであれば「殺した」とまでは言えません。
この場合は殺人未遂罪が成立し、法定刑は殺人既遂罪と同じとなっています(刑法203条)。
2、刑法199条の殺人罪の構成要件

「人」を「殺した」場合に刑法199条の殺人罪が成立しますが、殺人罪成立には具体的にどのような条件が必要なのでしょうか?「人」および殺す行為の定義を含め、構成要件を確認していきましょう。
(1)人の定義
刑法199条の客体となるのは「人」です。普段「人」という言葉は特に深く考えずに使うことが多いですよね。
殺人罪での「人」は行為者以外の自然人を指します。では、たとえば妊娠中の女性のお腹にいる胎児や既に死亡している人に対して殺人罪の実行行為となるような危害を加えた場合、殺人罪は成立するのでしょうか?
①「人」の始期について
刑法199条の客体となる「人」にはどの段階から該当するのでしょうか?妊娠中の女性のお腹の中で胎児は育っていきますが、胎児の段階も様々です。
妊娠初期の段階では、母体の外に出されても生存していくことが難しいですが、妊娠後期であれば母体の外に出ても適切な医療のもと生存していくことができる段階になっている胎児もいます。
また、胎児が母体の外に出れば「人」に該当すると考えても、たとえば、胎児の体が全部母体の外の出ないといけないのか、それとも胎児の体の一部だけが母体の外に出れば「人」になるのか等、細かく考えていくと「人」の始まりはいつなのか考え方が分かれます。
「人」の始期の考え方には、以下の4つの説があり、実務上は「一部露出説」が採用されています。
独立生存可能性説
こちらの説は、母体の外に出ても母体なしで独立して生存していくことができる可能性があると判断できる段階で「人」に該当すると考えます。
全部露出説
こちらの説は、胎児の身体の全部が母体の外に出た段階を「人」と考えます。
一部露出説
こちらの説は、胎児の身体の全部が母体の外に出ていなくても、胎児の一部が母体の外に出た段階で「人」と考えます。
たとえば、胎児の頭が母体の外に出ても身体の全部が母体の外に出てくるまで少し時間がかかるような場合があります。
一部露出説によれば、胎児の頭(身体の一部)が母体の外に出ればその段階で「人」に該当することとなります。
独立呼吸説
この説は、胎児と母体をつなぐへその緒を切り、胎児が独立して肺呼吸をするようになった段階で「人」に該当すると考えます。
②「人」の終期について
それでは、始期ではなく「人」の終期についてはどのように考えるべきでしょうか?終期については以下の4つの説があり、実務上は「総合判断説(三徴候説)」が採用されています。
呼吸終止説
自力での呼吸が完全に止まった段階で死亡したと考えるこちらの説では、呼吸が完全に止まる前までの段階が「人」に該当します。
脈拍終止説
脈拍が完全に止まった段階で死亡したと考えるこちらの説では、脈拍が止まる前までの段階が「人」に該当します。
総合判断説(三徴候説)
こちらの説では、上述の呼吸終止、脈拍終止、瞳孔反射の消滅の3つを総合的に判断して人の終期を考えます。
脳死説
こちらの説は呼吸や脈拍ではなく、脳機能が完全に停止した段階を人の終期と考えます。
(2)殺す行為
刑法199条の殺人罪の構成要件となる「殺す行為」とは、人の生命を自然の死期以前に断絶することです。
①物理的方法だけでなく心理的方法も含まれる
人を殺す行為には、ナイフで心臓を刺す等の物理的方法だけでなく、精神的に追い詰めて死亡させる等の心理的方法も含まれます。
②作為だけでなく不作為も含まれる
また、人を殺すという言葉を聞くと、意識的に殺す行為をすること、すなわち作為による殺人行為をイメージする人が多いでしょう。
しかしながら、作為だけでなく不作為という何にもしないこと自体が人を殺す行為に該当するケースがあります。
ただし、何もしなかったことが全て殺人罪の構成要件に該当するわけではなく、作為による殺人罪が成立するためには、①作為義務の発生と作為義務違反、②作為の可能性・容易性が必要であると考えられています。
③人の死という結果が起こりうる現実的危険性があることが必要
死亡結果が発生したからといって全てが殺人罪になるわけではありません。
殺人罪の実行行為である「人を殺す」行為は、その行為自体に「人の死」という結果が起こりうる現実的危険性があることが必要です。
たとえば、そっと肩に手を置いただけであるにもかかわらず、肩に手を置かれたことに驚いた人が階段から落ちて死亡したようなケースでは、そっと肩に手を置く行為自体に人の死の結果を招く現実的危険性がありませんので、殺人罪の実行行為とは言えません。
(3)殺意があること
殺人罪が成立するには、客観的に人を殺す行為を行うだけでなく、主観において殺意があることが必要となります。
殺意については人の主観ですので「殺すつもりはなかった」という加害者の主張が常に認められるわけではなく、客観的事情を総合的に考慮し殺意の有無が判断されます。
「殺してやる!」と意識している場合にのみ殺意が認定されるわけではありません。「殺してやる!」と意識している場合は確定的故意といって、犯罪の実現を確定的に認識・認容している場合です。
これに対し、「死ぬかもしれないがそれでもかまわない」と考えている場合のように、犯罪の実現可能性を認識・認容している場合を未必的故意といいます。
確定的故意だけでなく未必的故意がある場合についても、刑法199条の殺意があると判断されます。
なお、殺人罪で起訴された場合、裁判員裁判となり一般人から採用された裁判員と職業裁判官で構成される裁判体が殺意の有無を判断することになりますが、裁判員は裁判所から「人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った」場合には一般的に殺意があると認定していると説明されることがあるようです。
配信: LEGAL MALL