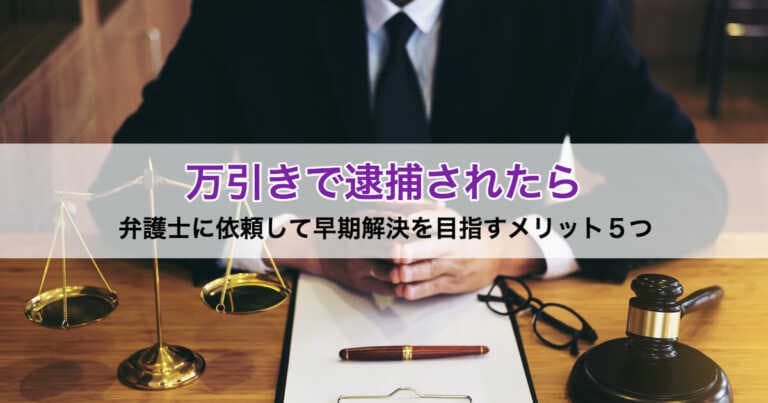「つい出来心で万引きをしてしまった……どうすればよいのか弁護士に相談したい」
「息子が万引で逮捕された!前科がつかないように早期に解決したい」
ご自身やご家族が万引きをして逮捕されてしまい、このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
万引きは刑法上、「窃盗罪(刑法第235条)」として、その法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。また、起訴され、有罪となった場合には刑を受けるだけではなく、前科がついてしまいます。
起訴され有罪となった場合には、このように前科がつくことに加え、本人はもちろんのこと家族の生活にもさまざまな支障が生じるおそれがあります。また、逮捕や勾留をされた場合の身柄拘束の間や、処分や裁判を待つ間の被疑者本人や家族の負担も大きいものです。そこで、できる限り早期に弁護士によるサポートを受け、適切な対応を行っていくことが重要です。
そこで今回は、
万引き事件で弁護士がしてくれること
万引き事件で弁護士を選ぶポイント
万引き事件の弁護士費用
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。加えて、実際に弁護士が介入することによって万引き事件を早期に解決できた事例も紹介いたします。
1、万引きで弁護士に依頼すべきケースとは
逮捕されてしまった
万引きの前科や前歴がある
クレプトマニア(「窃盗症」や「病的窃盗」とも呼ばれる精神疾患のひとつ)
営利目的での万引き
万引きが見つかりその場から逃げた
家族にバレたくない
2、万引きにおいて弁護士に相談するメリット
今まで弁護士と関わりがなかった人にとっては、弁護士に依頼することによって実際にどのようなサポートを受けられるのかイメージしづらいことでしょう。
そこでまずは、万引き事件を依頼した場合に弁護士がどのようなサポートをしてくれるのかについて、具体的にご説明します。
(1)被害店との示談交渉
万引き事件を解決するための弁護士の最も重要な活動の1つは、被害店、具体的には被害店の社長や、店長などとの示談です。
示談が成立すれば、金銭的な被害は回復されたとして、被害店が被疑者を許してくれる場合もあり、被疑者本人も深く反省していることを示すことができます。その結果、警察や検察官が軽い処分や不起訴処分で済ませる可能性が高くなるからです。
そもそも、日本では、警察がある犯罪を事件として覚知した場合、被疑者を取り調べた上で、事件や被疑者の身柄を検察に送致することが基本です。送致されると、検察で再び取り調べを受けることになり、起訴されるか不起訴になるかが判断されます。なお、起訴されると刑事裁判が行われますが、9割以上の確率で有罪となり、なんらかの処罰が下されます。
もっとも、警察が事件を覚知した段階で、すぐに弁護士に依頼されるなどして、早期に示談が成立した場合には、逮捕されても警察から検察に送致されず、逮捕から1日から2日で釈放される微罪処分で済む可能性が高まります。微罪処分は、一定の条件の下に認められますが、被害金額が少なく、前科や常習性のない被疑者による万引き事件などにおいて、示談が成立している場合には、微罪処分を得られる場合も多くあります。
また、警察から検察に送致された後に、示談が成立した場合には、起訴されずに釈放されるという不起訴処分となる可能性も高まります。
微罪処分や不起訴処分となった場合には、前歴は残りますが、有罪となり前科がつくことを避けることができます。
したがって、示談をすることは、被疑者にとって有利な処分を獲得するためにも、最も重要な活動の1つとなります。もっとも、逮捕された場合には、被疑者本人が自分で示談交渉をすることは難しいですし、被疑者本人や家族が被害店に連絡をしても被害店の被害感情が強く、示談交渉に応じてもらえないことが多々あります。
そこで、万引き事件を扱う弁護士は、被害者の感情にも十分に配慮し、まずは本人に代わって真摯に謝罪をして話し合いを始めます。
示談による被害店にとってのメリットなども説明し、冷静かつ粘り強く話し合うので、当初は被害店が示談交渉に応じてくれない場合であっても、被害店の対応も変わり、話し合いも円滑に進みやすくなることも多々あります。
示談金の額についても、実務上の相場を弁護士が説明しながら交渉するため、適切な金額で話し合いがまとまりやすくなります。
その結果、円満に示談が成立する可能性が高まります。
(2)被害届の提出前の働きかけ、被害届の取下げを求める働きかけ
万引きをしてしまっても、そもそも、警察に発覚する前に解決できれば、警察が事件として覚知し、その後の捜査や、逮捕・勾留、起訴処分などをうけることを回避できる可能性が高くなります。そして、万引き事件の場合には、警察は、被害店からの被害届によって事件を覚知することが多いため、示談を行い、被害届の提出を行わないことよう合意をすることが重要です。
また、警察がすでに被害届を受理している場合であっても、被害届が取り下げられた場合、事案によっては事件化されることを回避することが可能な場合がありえます。
したがって、弁護士は、万引き事件の依頼を受ければただちに被害店との示談交渉を開始します。被害店と被害届の提出をしないことや、提出した被害届の取下げについて合意ができ、円満に示談が成立すれば事件化される被疑者の不利益を防ぐことが可能になります。
(3)接見における本人へのアドバイス
万引き事件に限らず、刑事事件で逮捕や勾留をされた場合には、被疑者本人は、身柄を拘束された状態で1人で取り調べを受けなければなりません。このような取り調べでは、取調べでの被疑者の説明が不十分であったりする場合や、被害者側からの聴取などにより取調官が先入観をもって取調べを行う場合などもありえますから、被疑者本人の経験、認識した事実とは異なる内容の供述調書が捜査機関に取得される可能性があります。
事実と異なる、捜査機関側に有利な供述調書が取得されると、被疑者にとっては不利益に働き、釈放がなされず処分も重くなる可能性が高まります。そのため、被疑者は、取調べでは適切な受け答えを行い、供述調書の内容に間違いがないかどうかを慎重に確認する必要があります。
もっとも、逮捕された被疑者が何のアドバイスもなく、適切に取調べの対応を行うことは難しいものです。特に、勾留が決まるまでの逮捕中(最大で72時間)は家族であっても面会できないことが多く、励ましを得ることもできません。
それに対し、弁護士はいつでも被疑者と接見できます。逮捕されたらすぐに被疑者本人と接見し、取調べで誤った内容の供述調書が取得されないように、取調べの対応について具体的なアドバイスを行います。また、手続きの流れ、処分の見込みなどについても説明を行い、被疑者と今後の方針について打ち合わせを行います。また、家族からの伝言なども伝え、被疑者を励ますこともできます。このように、弁護士は、身柄を拘束された被疑者に代わり、外部との連絡窓口となり、また取調べ対応などについて専門家としてのアドバイスなどを行っていきます。
(4)本人の生活環境の調整
万引き事件で、どのような処分が下されるのかという点について、「再犯のおそれ」の程度が重要な影響を及ぼします。
再犯のおそれが強いと検察官に判断された場合には、起訴される方向に働く事情となります。逆に、再犯のおそれがないと判断された場合には、不起訴処分が下される事情となります。また、警察が微罪処分として処分するかどうかを決定する際にも、再犯のおそれは考慮する事情の1つとなります。
被疑者に再犯のおそれがないことを警察や検察に信用してもらうためには、本人の生活環境を改善し、その事実を適切に警察や検察に伝えていく必要があります。そのために、有効な活動の1つは、日常生活をしっかりと指導・監督してくれる身元引受人を確保し、その身元引受人が、被疑者の生活を指導・監督する旨を記載した身元引受書などを提出することです。
弁護士は、依頼を受ければ早急に身元引受人についても適切に人選を行い、身元引受人を確保します。
また、窃盗を繰り返してしまう病的窃盗(クレプトマニア)などの症状を有する被疑者に対しては、医師などの専門家を紹介し、適切な治療を受けるようアドバイスなどを行います。また、専門家が作成した治療のプログラムなどを意見書とともに警察や検察に提出し、被疑者が治療を受け、症状の改善に努める意欲があることや、治療の効果などを伝え、被害者に再犯のおそれがないことを説得的に伝えるなどの活動も行います。
(5)警察や検察への働きかけ
弁護士は、以上のような活動を行いながら、警察や検察に対して軽い処分を求めるための働きかけを行います。
具体的には、送致されていない被疑者については、警察に対して、微罪処分などを求め、送致後は検察官に対して不起訴処分を求めるなどの活動を行います。
検察官も、必ずすべての被疑者を起訴するわけではありませんので、被害回復を行い、被害店の処罰意思がないことや、被疑者に再犯のおそれがないこと、十分に反省していることなどが認められた場合には、軽微な万引き事件においては、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にありえます。
また、弁護士から検察官に連絡した際には、当該被疑者について、不起訴処分を行うにあたって必要な条件などについて教えてもらえる場合もあります。
このような対応は被疑者本人やご家族では難しいことなので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
配信: LEGAL MALL