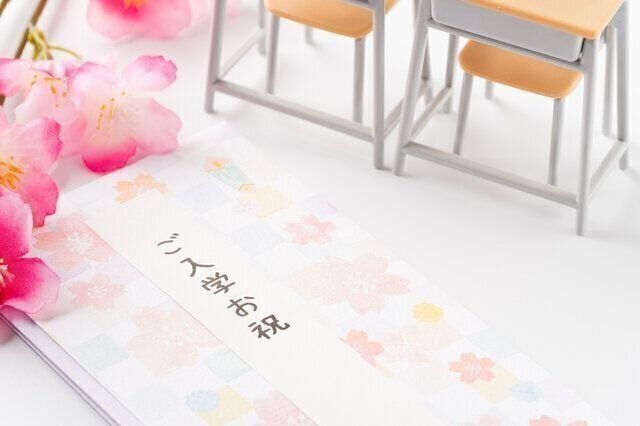春は入学のシーズンで喜ばしい反面、親せきの子どもへの入学祝いはいくらい渡せばよいのか悩んでしまうなんてことも。自分や夫のきょうだいの子どもの場合いくらが相場なのか、いとこの子どもまで渡す必要がある?など口コミサイト「ウィメンズパーク」のママたちのお悩みの声を紹介するとともに、ファイナンシャルプランナーの菅原直子さんにお祝い事情についてアドバイスいただきました。
ママたちのお祝いのマイルールとは
――まずは、ママたちのお祝い事情について紹介します。
■お年玉はあげるけど、お祝いはしないです
「いとこが祖母と同居していたので、お正月に挨拶に行った時にお年玉をあげたりはしますが祝いごとはしません。相手も面倒に思っている可能性もあるので、親しくないならある程度でやめるべきかなと考えています」
■キリがないので、いとこはなしかな
「各ご家庭でルールがあるとは思いますが、私はいとこの結婚ですらお祝いを渡していません。だから、いとこの子どもの入学祝も渡したことはないです。正直、そこまでするとキリがないので」
■姉妹同然なので、いとこにもお祝いを
「ウチは夫婦1人っ子同士で子どもも1人ですが、いとこたちとは姉妹同然の濃いつき合いです。お互いの結婚、仏事の香典、出産、新築祝いを贈りあっています。もし、自分や夫にきょうだいがいたら多分、節目のお祝いは贈っていると思います。言い方は悪いですが、何かしら繋がりがないと自分たちが死んだ後、子どもが天涯孤独になるのが心配ということもあります」
■お祝いは祖父母、おじおばの関係まで
「入学祝い以上は、祖父母、おじおばくらいまででいいと思います。いとこの子は、お祝いするべき関係とまではいかない気がします」
■私がお祝いするのは甥姪まで
「仲の良いいとこには結婚のプレゼントはしましたが、お祝いまでしていません。年の離れたいとこには言葉だけかけさせてもらいましたが、金品のお祝いはしませんでした。もちろん私の親にとってのいとこは、甥姪になるのでお祝いしていましたが、親と自分たちは立場が全然違いますから」
■同じいとこでも仲がいい人にお祝いをします
「仲良くしているいとこもいるし、一度くらいしか会ったことないいとこもいます。仲良くしているいとこには子どもはいないですが、もし生まれていたらお祝いしていたと思います。結婚祝いもあげたので。一度くらいしか会っていないいとこには、何もしないです」
お祝いは義理よりも「マイルール」を決めておくことが大事
お祝いはどこまでするべきか、ファイナンシャルプランナーの菅原直子さんに伺いました。
「お祝いは、地域や家庭によって祝う相手の範囲や金額が異なります。まずは、親がどうしていたのか教えてもらい参考にしましょう。親の時代より親戚づきあいは薄れているのなら日頃の付き合いの深さを考えて、最終的には自分で決めることになります。
『私はこうする』というマイルールを決めておくことで悩んだり迷ったりせずにすみます。
<関係性>
兄弟姉妹の子どもまで、いとこの子どもまで、近隣に住んでいて日頃から行き来があるいとこの子どもにも…など。
<理由>
小学校や中学校など学校種別ごとに入学時、毎年の進級時、受験のある高校や大学の入学時だけ…など。
<金額>
学校種別に関係なく入学祝いなら○万円、上級学校になるほど増額、大学進学しない子には成人祝い…など。
FPとしてのアドバイスは、義理や見栄や祝ってあげたい強い気持ちをいったん脇においてほしいということ。第一子にお祝いしたら、第二子・第三子にも同じようにするのがマナーとされているので、同じ金額を包み続けられるかどうか冷静に考えてみることです。第一子には奮発したけれど、自分の子どもの成長で生活費がかさみ、相手の第二子のお祝いを包むのが苦しいというケースも見られます。そうならないよう、交際費にどれだけ使えるのか家計を見通しておくことが大切です。
また、すでに自分がお祝いをもらった相手には、同じようにすることになります。きちんと記録しておき、その時が来たらお祝いできるよう準備しておきましょう。
反対に、相手が同じように祝ってくれない場合は、今は財布が大変なのだろうと思いやるようにしてみてください。お祝いは、祝う気持ちと財布の両方が整わないとできないものです。モヤモヤしがちですが、自分のためには気持ちを切り替えることです」
(お話/菅原直子さん)
入学シーズンは、どの家庭もお金が必要な時期です。アドバイスにあるように、「マイルール」を決めて無理のない範囲でお祝いすることが大切ですね。
(取材・文/酒井範子、たまひよONLINE編集部)
配信: たまひよONLINE