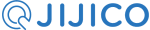草木が芽吹き桜や花々が美しい春は、寒暖差や環境変化など「ストレッサー」の多い季節でもあります。
「ストレッサー」とは、ストレスを引き起こす要因のことです。結果として起こる「ストレス」とは、ボールがギュッと潰されているような不安定な状態を指します。
どのようなストレッサーがどのようにストレスを引き起こすのか、また、人間の基本的な苦を知ることで、ストレスを緩和し成長に活かしましょう!
ストレスというと、嘆かわしいことにイライラするようなイメージですが、意外にも、新年度、新生活、入学などの喜ばしいこともストレスの要因「ストレッサー」になることがあります。
ホームズ博士(アメリカ)の『生活上のストレス表』によると、配偶者の死:100点、結婚:50点、再就職:39点、入学・卒業:26点、住居の変化:20点、といった具合です。
約40年前の表なので、現在ならSNSによる一喜一憂もストレスの上位を占めそうですね。
程よいストレスは、環境適応や柔軟性を育み、自己成長の糧となりますが、過剰なストレスが続くとどうなるでしょう?
潰されたボールが元通りに押し戻ろうとするように、心身を環境に適応させて安定させる体内システム「ホメオスタシス(生体恒常性)」が追いつかなくなります。そして、自律神経が乱れ、内分泌のバランスが崩れ、免疫力が低下、心身に不調をきします。
まずは、どんな種類のストレッサーがあるのか見てみましょう。
「ストレッサー」にはいくつかの分類があり、互いに影響し合いながらストレスとなります。
〈外的要因〉
物理的ストレッサー
自然:寒暖差、花粉、騒音などによる身体的なストレス
社会的ストレッサー
社会環境:人間関係、家庭や職場環境、経済状況などのストレス
〈内的要因〉
心理的・情緒的ストレッサー
個人的:不安や恐怖、寂しさや怒りなどのストレス
生理的・身体的ストレッサー
生理的:病気、疲労などのストレス
出典:健康管理士・健康管理検定1級 公式テキスト
人間の基本的な苦を深掘りするために、数千年前の東洋人のストレス(苦)をご紹介します。
「四苦八苦する」など、日本でもよく耳にする言葉ですが、出典は上座部仏教のパーリ仏典『律蔵』で、仏陀の原初の教えが納められている古典です。
四苦と八苦
・四苦/生、老、病、死
・愛別離苦(あいべつりく) - 愛する対象と別離する苦
・怨憎会苦(おんぞうえく) - 怨み憎む対象と会う苦
・求不得苦(ぐふとっく) – 求めるものが得られない苦
・五蘊盛苦(ごうんじょうく) – 色(身体)・受(感覚)・想(表象)・行(意思)・識(認識)に依る苦
また、古代インドにおけるサーンキャ学派では、苦を大きく三つに分類しています。
サーンキャによる3つの苦(ドゥッカ)
・依内苦:身体/粘液・腺、精神/渇望、恐怖、困惑、嫉妬
・依外苦:人間、家畜、鳥獣、蛇、植物
・依天苦:寒熱、風雨、悪霊、天神の憤怒
出典:『サーンキャ哲学体系序説』
人間のストレスや苦悩は、数千年前と現在とであまり変わらないようですね。
古代インドでは司祭階級を持つバラモンの影響が強いため、天に依る苦に悪霊や天神が現れます。現在もお祓いやお守りなどで、目には見えない脅威に対処しているのかも知れません。
さて、同じストレッサーを受けているのに、ストレスになりやすい人となりにくい人がいます。それは、感知能力や回避能力などのストレス耐性の違い、また、完璧主義や自己嫌悪、ストレッサーに気付かないなどの性格の傾向による違いなどに要因があります。
コップに半分入った水を、「半分しかない」と思うか、「半分もある」と思うか、受け取め方の違いもストレスを左右します。
なんとなくイライラ、モヤモヤ、焦り、不安を感じたら、どんな「ストレッサー」を受けているのか考察し、要因をなるべく回避したり、視点を変えたりしてみましょう。
睡眠と休息、軽い運動、数分間の瞑想などを生活の合間に入れることをおすすめします。ちょっと立ち止まって、空や景色を眺めるのも良いですね。
ある程度のストレスは、成長ホルモンの分泌を促し、ストレス耐性を育み、心身を成長させてくれます。先人たちも厳しい生活環境の中、辛抱強く変化を待ったことでしょう。
「ストレッサー」を知り、ストレスをほんの少しでも和らげて元気な新生活を!
健康管理士、古典ヨガ指導者
中里えみこ
(中里 えみこ/ヨガインストラクター)
配信: JIJICO