「やさしさの輪郭」楠井志保1
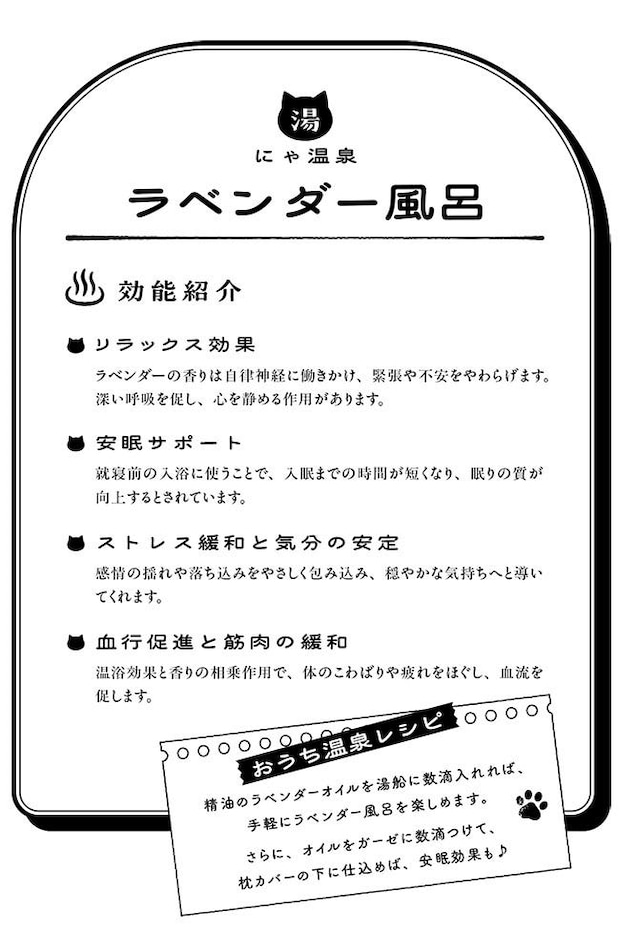
ファミレスに着いたのは、約束の時間から三十分遅れだった。
席に着くなり、健治(けんじ)くんのママである梨沙(りさ)さんが斜め前の席から身を乗り出した。
「朝陽(あさひ)くん、スクールの代表に選ばれたんだってね」
周りのママ友たちが一斉に感嘆の声を上げ、何人かの客が何事かとふり向くのが見えた。
「ああ……うん。すごいよね」
気もそぞろにうなずくと、
「ちょっと志保(しほ)さん、自分の子どものことでしょ」
と、ママ友のひとりにツッコまれてしまった。
ファミレスの奥にある八人がけのテーブルには、いつものママ友たち。四十代は私だけで、ほかはみんな二十代か三十代前半。華やかな化粧にトレンドを意識した服装、会話のテンポも軽やかで、ランチ会は毎回、学生時代の延長のようなノリだ。
私は仕事を抜け出してきたので、Tシャツにパーカーを羽織ってきただけ。下なんてジーパンを穿いている。
「でもさ」
梨沙さんの声に視線を戻す。
「英語朗読コンテストの代表なんてすごすぎ。うちの健治じゃ、一生かかっても無理だもん」
「そんなことないよ。それに、私はなんにもしてないし」
そう言うと、前の席に座る香澄(かすみ)さんがやわらかくほほ笑んだ。若々しく美しく、ゆるいパーマの髪に控えめなブランド服が似合っている。
英会話スクールに入ったのは、朝陽が小学一年生の時。同じ小学校のクラスメイトの涼太(りょうた)くんが英会話スクールに通っていることを、母親である香澄さんから聞いたのがきっかけだった。体験入学で朝陽が『また来る!』と宣言したので通うことになった。ママ友たちとの交流も間もなくしてはじまった。
あれから二年が過ぎ、子どもたちは三年生になった。数ヶ月が過ぎ、気がつけばあと数日で七月。
絵本の朗読コンテストがあるとは聞いていたけれど、まさか朝陽が選ばれるとは思っていなかった。連絡があったのは昨日で、夏休み中に県大会があり、上位二名が全国大会に出場できるとのこと。
昨日は家族で大喜びしたけれど、コンテストに出たかった子たちのことを考えると、ここではしゃぐわけにはいかない。
それに、私には最近ずっと気になっていることがあって……。
「あたし、思うんだけどさ――」
香澄さんが口を開いた。
「やっぱり志保さんって、大人だよね。こんなすごいことが起きたら、あたしたちの年だとはしゃいじゃうもん。年の功、ってやつ? グループにひとりいると安心感あるよね」
その言葉に、ファミレスの店内に流れるBGMがぷつりと消えた気がした。
――まただ。
胸の奥がじんわりと冷えていくこの感覚。でも、悪意があるわけじゃない、と思う気持ちもわずかに残っている。
香澄さんは明るくて、人当たりがよくて、いつも場を盛り上げてくれる。
「ありがとう」
無理やり笑顔を作ってから視線を窓の外に流すと、視界の端になにか動くものが映った。
ファミレスの外、窓枠にちょこんと三毛猫が乗っている。かなり太っていて、ふてぶてしい顔の三毛猫が、なぜか私をじっと見つめている。
「わかる。志保さんがいないと、話がまとまらないもんね」
梨沙さんがそう言い、周りのママ友がうなずいた。
「だってえ」と香澄さんが甘い声を出した。
「あたしたちにとって、志保さんは年の離れたお姉さん的存在だもん。ちなみにあたしは末っ子ね」
ドッとみんなが笑う声が押し寄せてくる。
香澄さんとは家が近所ということもあり、たまにお互いの家に行ったりもしていた。何気ないひと言にチクリと胸が痛むことがあっても気づかないフリをしてきた。
違う話題に移るのを確認してから、席を立ちトイレへ。
洗面台に手をつき、深いため息をつく。鏡に映るのは、少し疲れた顔の私。白い髪やパサつく髪、眠そうなまぶた……年齢を隠せない。
当たり前か。朝陽を生んだのは三十六歳の時。不妊治療を諦めた途端に妊娠がわかり、夫と涙を流しよろこんだことを覚えている。
「大丈夫」
鏡に向かってつぶやいてみる。
四十四歳の私が、ママ友の間で浮いてしまうのは仕方のないこと。重い人だと思われることは避けないと。許される空気の重さにも、年齢制限があると思うから。
ドアを開け、ぎこちない笑みを浮かべながらテーブルに戻った。
「おかえり。今ね、夏の合宿の話をしてたとこなの」
香澄さんが長い髪をかき上げながらほほ笑んだ。
少し動くだけでさわやかな香りが漂ってくる。はっきりしたメイクに長いまつ毛。私では絶対に選ばない色のリップを好んでいる。
「合宿……。あ、スクールの?」
毎年八月に、夏合宿が開催されている。朝陽の申し込みは済ませてあるが、今年も香澄さんたちは同行するらしい。
「そうそう。子どもたちはバスに乗れるけど、親は同行するなら自分たちで行かないとでしょう。こんなに長く通ってやってんのに、マジでありえない。あたし、塾長に抗議してやったの」
口々に塾長の悪口がはじまってしまった。
仕事があるので、朝陽の送り迎えはほとんどしていない。悪口が言えるほど塾長のことを知らないので、ただ黙ってうなずくしかなかった。
会話が一段落したところで、思い切って「あの」とみんなに尋ねた。
「夏の合宿、みんなも同行するの?」
「当たり前じゃない」と、香澄さんが代表で答える。
「ここにいるみんな、参加するよ。ね?」
周りのママ友が同じ動きでうなずくのを見て、香澄さんは満足そうに視線を戻した。
「え、志保さん行かないの?」
「ごめんね、仕事があるから、今年は朝陽だけで……」
「絶対一緒に行ったほうがいいって」
視線が集中する。
「志保さん、お父さんの工場の仕事を手伝ってるんだよね? 合宿の期間くらい休めないの?」
「……どうだろう。難しいかも」
そもそも塾長からは『なるべく保護者は同行しないように』とお達しが出ている。
去年も同行したのは私たちのグループだけだった。
長い髪を指先でときながら、香澄さんが眉を下げた。
「夕飯の時にひとりだけ親がいないなんて、朝陽くんがかわいそう」
梨沙さんが「そうよね」と声にしてうなずき、周りにその波が広がっていく。
いつもそうだ。香澄さんの言葉は、まるで空気の流れを変える風のように、みんなの意見を塗り替えてしまう。
「それに、あたしたちだって志保さんがいてくれたら心強いし。大げさじゃなくって、あたし、ほんとに志保さんのこと、頼りにしてんの。ね、なんとかならない?」
強引に物事を進める香澄さんに違和感を覚えながらも、仲間外れにされるのが怖くていくつもの無理を重ねてきた。
断ろう。そう決意したのに、
「主人に相談してみるね」
そう口にしていた。
「隆幸(たかゆき)さんに話すなら、あたしも同席しようか?」
香澄さんは涼太くんを連れ、何度か家に遊びに来たことがある。きっと隆幸さんは香澄さんの提案に同意するだろう。
「ううん、大丈夫。今夜話してみるね」
なんとか明るい声で答えるが、香澄さんの視線はまだ私に向いたまま。
「隆幸さんって、なにしてる人なんだっけ?」
「今は製紙会社に〝出向〟って形で行ってるけど、もうすぐ戻ってきて、父の工場を継ぐ予定」
だから夏は忙しくて、と続ける前に「え!」と香澄さんが声を上げた。
「お父さんの会社を継ぐの? たしか紙職人よね。職人の娘ってなんか憧れる~」
「そんないいものじゃないよ。小さな会社だし」
「隆幸さんが継いでくれるなら安泰だね。でも、大変な仕事でしょう? あたしだったら出向先で再就職しちゃうけどな。だって、大手のほうが安心じゃない」
心配してくれているだけ。そう自分に言い聞かせ、顔から笑みを消さないように力を入れる。
「もともと夫は父の弟子だから、戻るのを楽しみにしてるみたい」
ふうん、と香澄さんがアイスコーヒーをストローで混ぜた。
「まあ、そういう仕事もいいかもね。うちは毎日帰りが遅いし、昇進試験前らしくて、休みの日も部屋に閉じこもって勉強ばっかり。隆幸さん、よく家の前で朝陽くんとキャッチボールとかしてるじゃない? 涼太がいつも言うのよ。『朝陽んとこのお父さん、時間があってうらやましい』って」
夏央(なつお)くんママが「あら」と目を丸くした。
「香澄さんのご主人、化粧品の一流メーカー勤務じゃない。私からすればよっぽど香澄さんのほうがうらやましいわよ。ね?」
会話をふられた梨沙さんが大きくうなずく。
「誰もが知ってる会社だもん。そうそう、こないだくれた新作の化粧水、ほんっと最高。肌にすっと入ってきて、さすが高級品って感じ」
周りのママ友も口々に賞賛の声を上げる。
「今度、志保さんにもあげるからね。あと、髪にいいオイルがあるの。髪が傷んでるように見えるから、軽くつけるだけでパサパサになるのを回避できるよ――って、余計なお世話だよね」
ひとつに結んだ髪を無意識に触りながら、なんとか口を開く。
「うん。ありがとう」
見ないフリをしているうちに、ヒビがどんどん大きくなっていく。曖昧にほほ笑むと、また窓の外にいる三毛猫と目が合った。なにか怒っているように見えるのは気のせいだろうか。
話はスクールの担任の話に変わった。香澄さんを中心に、担任への文句が湧き水のようにあふれている。
自分の話題が終わったことに、そっと胸をなでおろす。時計を見ると、もう二時間以上経っている。
「ごめんなさい。そろそろ仕事に戻らないといけなくて」
ドリンクバーの代金を置いて席を立つ私に、
「大変ねえ。仕事って三時までだっけ?」
香澄さんが心配そうに尋ねた。
「うん。繁忙期以外は三時までだよ」
「合宿のことは、またグループLINEに返事するから」
にこやかな笑みにホッとしながら荷物をまとめていると、香澄さんが続けた。
「そうそう。レンタカー会社はどこでもいいけど、車は八人乗りのにしてね」
え、と体が固まる。
「前にお願いしたじゃない。よろしくね」
合宿に使うレンタカーを手配するなんて、お願いされていない。
が、香澄さんはもう顔をそむけ、さっきの話題の続きをはじめている。
私の存在なんて最初からなかったように、高い笑い声が店内に響いていた。
店を出て夏の午後の光に包まれた駐車場へ向かう。急いで戻らないと、事務仕事が終わらない。それに、レンタカーの手配もしないと……。
足取りを速めようとしたその瞬間、なにかが私の前に飛び出てきた。
――あの三毛猫だ。
さっき窓枠に座っていた太った三毛猫が、行く手を阻むかのようにちょこんと座っている。思っていたより毛並みは艶やかで、首に朱色の首輪をしている。どうやら飼い猫のようだ。
猫はじっと私を見つめていたかと思うと、急にあごをツンと上げた。その表情には、どこか挑むような鋭さがあった。
三毛猫が口を開けた。
「お前、自分に正直じゃないな」
耳に届いたのは、間違いなく男性――おじさんの声だった。
「――え?」
辺りを見回すが、駐車場にはほかに誰もいない。青空の下、車の陰に人の姿もなく、ただ暑い日差しだけが降り注いでいる。
「嘘……。え、なに?」
心臓が跳ね、手のひらに汗がにじむ。
三毛猫は一瞥をくれると、堂々と尻尾を揺らしながら去っていった。
どれくらい立ちすくんでいたのだろう。急いで車に乗り込み、エンジンをかける。
――まさか、猫が人間の言葉をしゃべったの?
そんなわけがない。きっと幻聴だ。
そう自分に言い聞かせながら車を走らせるけれど、あの低く落ち着いた声が、耳の奥でいつまでも消えなかった。
父の製紙工場に入ると、独特の匂いに包まれる。
紙すき場の湿った水の匂い。竹枠の青くてやわらかい匂い。使い古された機械のさびた匂い。子どもの頃から慣れ親しんできたそれらに、ホッと息をつく。
『楠井(くすい)製紙工場』と名はついているが、規模は小さく、工房と呼ぶほうが近い。
昔ながらの手すき和紙を中心に製造していて、一枚一枚、丁寧に作業を進めている。竹枠の中で和紙の繊維が水の上で踊るように漂い、静かな時間が流れている。
一方で、裁断や乾燥などの部分は、古びた機械が音を立てて動き、職人の手仕事と機械の調和がそこにあった。
合宿の話をすると、父はすぐに承諾した。
「朝陽のためにできることをしてやれ。こっちは、もうすぐ隆幸も戻ってくるし大丈夫だ」
完成した和紙を配送用のケースに入れながら父は言った。
心は揺れる。泊まりで香澄さんたちと過ごせば、夜は悪口大会になる。
断るつもりだったけれど、朝陽のことを思うと決断ができない。小三になっても、家に帰ると私のあとをついて回るほどの甘えん坊だから。
――お前、自分に正直じゃないな。
さっきの声がまた聞こえた気がして、思わずギュッと目をつむった。
「なんだ?」
不思議そうな父に、首を横にふる。
「隆幸さんが出向から戻ってきたら、お父さんはどうするの?」
「俺は職人の仕事に専念する。経営は隆幸のほうが向いている。任せておけばうちは安泰だ」
「機械化を進めてもいいの?」
「構わんよ。俺が口出しすることじゃない。むしろ、会社を大きくしてビルでも建ててもらいたいくらいだ」
母が病に臥せたのが三年前。同じタイミングで、父は隆幸さんに代を譲ることを宣言した。闘病の末、母が亡くなって以降は身なりにも気を遣わなくなり、一層老けたように見える。
「しかし、隆幸が志保と結婚するなんてな。弟子と娘が結ばれるなんて想像もしてなかった。さらに婿養子にまでなってくれた。これで楠井製紙工場も安泰だ」
同じ話ばかりするようにもなった。
「いつの話してんのよ。お父さんもそろそろのんびりしてもいいんじゃない?」
それには答えず、父は発注書とにらめっこをはじめてしまった。
職人気質である父は、隆幸さんに代を譲ってもあれこれ口出しするのだろう。隆幸さんもそれを望んでいるようだし、仕事は断るほどある。
ふと、見慣れぬ朱色の和紙が乾燥棚に載せてあることに気づいた。
「珍しい色だね。こんなの作ってたっけ?」
「ずいぶん前に断った会社のやつだ。まだ諦めてないらしく、どうしてもうちで作ってほしいと社長自ら頭を下げに来てな。しょうがないから試作品を作ってる」
私の視線に気づいた父が、誇らしげに紙を手にした。
「機械じゃ出せない風合いに惚れたらしい。数は多いが、納品はまだ先だからなんとかなるだろ」
父の指先が、まだ湿った薄い紙の端をそっとなでる。
母の闘病中、父はお得意様以外の仕事をすべて断ってきた。亡くなって一年、少しずつ父も立ち直ってきたのだろう。
「無理しないでよ。佐川(さがわ)さんだって全然休めてないじゃない」
奥で作業をする佐川さんは今年七十歳になる。無口でほとんど笑った顔を見たことがないけれど、父とは馬が合うらしく、子どもの頃から接してきた。
「ここも新しい職人を入れないとな。もしくは、機械化するか。……まあ、お前らの代になったら好きにすればいい」
そう言うと父は乾燥機のボタンをいじくりだした。まるで機械と会話するようにうなずきながら、風量を調整している。
昔はたくさんの職人がいて、父がいて母がいた。そして隆幸さんも。
三十歳で長くつき合った人から別れを切り出されてから数年、結婚を諦めた時にいきなり隆幸さんから告白された。しかも、両親の前で。
寝耳に水だった。私の返事よりも先に、両親に承諾を得る姿に思わず逃げ出してしまった。改めて告白された時も秒で断ったけれど、彼を知るたびに気持ちが傾いていった。
今では結婚してよかったと思っているし、家庭に大きな問題はない。
私を悩ませているのは、ママ友とのつき合い方だけ。
たいした問題じゃない、と言い聞かせているうちにどんどんヒビが大きくなり、今にも割れてしまいそうだ。
――そう、私は自分に正直じゃない。
そんなこと、猫に言われなくてもわかっている。
事務仕事を済ませ、買い物をしてから帰ることに。
都会とは言えないこの地に、スーパーの数は多くない。必然的に仕事関係の人と会い、話し込むことも多いので時間には余裕をみるようにしている。
今日は少し遠回りをして、別のスーパーへ向かった。顔見知りに会わずに済むという、ただそれだけの理由で。
ひとりになれる時間は宝物。けれどその静けさは、駐車場に入ってきた赤いBMWにより、あっさり終わりを告げられた。
私の車の横に滑り込むと、運転席の窓が開き、香澄さんが笑顔で手をふった。
「やっぱり志保さんだと思った。前を走ってたから、追いかけてきちゃった」
追いかけて――?
一瞬、背筋に冷たいものが這い上がるが、悟られないように笑顔を作った。
車から降りると、香澄さんが優雅にやってくる。
「せっかくだから一緒に買い物しよ。って迷惑かな?」
「そんなことないよ。さっきは途中で仕事に行っちゃったし」
額ににじむ汗は、蒸し暑いせいだけじゃない。
店内に入ると、クーラーの冷気にホッと息をつく。
「一緒のカートでいいよね。下のカゴが志保さんのぶんね」
そう言い、香澄さんは選別することなくレタスをカゴに入れた。次は鮮魚コーナーに行きたいらしく、さっさと進んでいくのでついていく。
「さっきのこと気にしてたから会えてよかった。よく考えたら、レンタカーのこと、押しつけちゃうなんて失礼だったなって」
思ってもいなかった言葉に「え」と驚く。
「そんなことないよ。帰ったら予約してみる」
「ううん、大丈夫。レンタカーはあたしが借りておくよ」
この記事の詳細データや読者のコメントはこちら


