【第3話】「やさしさの輪郭」楠井志保3
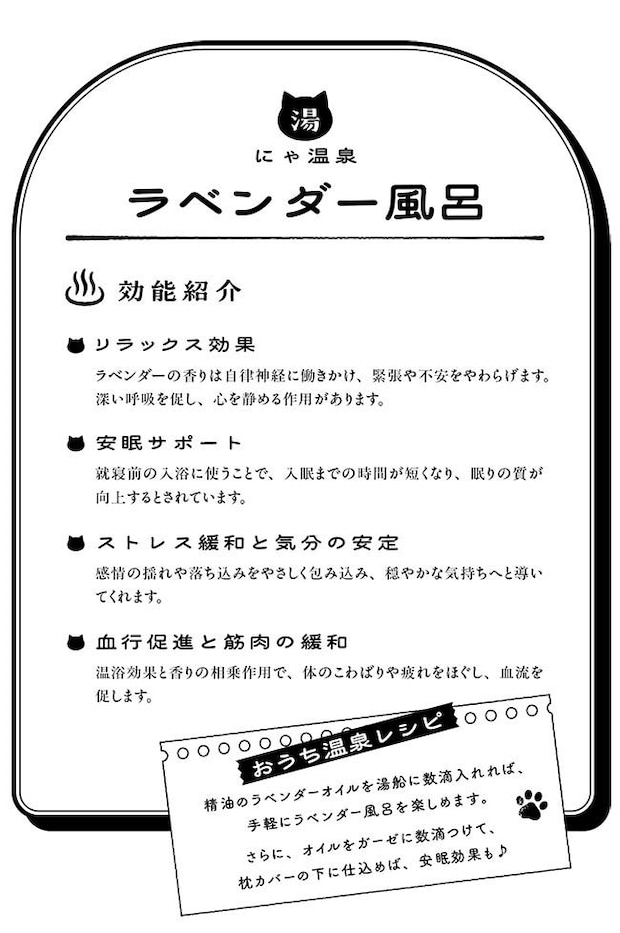
「では、案内しますわ。ムギちゃん」
ルナさんが『湯』と書かれたのれんの向こうに声をかけるが、誰も来ない。
「ごめんなさいね。あの子、人間が苦手なのですわ。辛抱強く待ってればそのうち来ますから」
そう言うとルナさんは畳部屋でごろんと横になった。
「おい、ずるいぞ」
プレジがあとを追い、ルナさんのそばで丸くなった。
「ちょっと、プレじい、暑いから近づかないでよ」
「そのあだ名はやめろ!」
言い合うふたりを眺めていると、
「あの」
蚊の鳴くような声がかすかに聞こえた。
入浴場に続く扉のすき間から、茶色の猫がおずおずと顔だけ出している。
「こちらです。どうぞ」
かわいらしい声をしているので、きっと若い女の子だろう。
近づくと「ひゃ」と悲鳴を上げて逃げてしまった。
脱衣所はそれほど広くなく、棚にカゴがふたつ置いてあり、あとは鏡のついた洗面台とトイレ、自動販売機があるだけだった。
姿を探すが、どこにも見当たらない。
「そこのカゴで服を脱いでお入りください。すみません」
上のほうから聞こえる声。見ると、自動販売機の上に茶トラの猫が乗っている。目が合うとサッと逸らされてしまった。
「ムギさんですか?」
体の大きさはプレジの半分もない。
「……そう、です」
ささやくような小さな返事が聞こえた。
「ムギさんは案内係をしているのですか?」
「いえ、あの……お湯番なんです。本当はお体を流したりもするんですけど、わたし、まだ新人で……」
オドオドした口調で、体をすぼめている。
「ムギちゃんって呼んでもいい?」
「あ、はい」
ムギちゃんは今にも逃げてしまいそう。私もこれから香澄さんといる時は、こんな感じで怯えるのだろう。
「不思議な日帰り温泉ですね。復讐屋もしているなんて驚きました。回数券は買いましたけど、やっぱり復讐なんてよくないことですよね……」
返事は、ない。いなくなったのかと視線を戻すと、ムギちゃんはうつむいてしまっていた。
あまり話しかけるのも悪いので、服を脱いで浴場に続くガラス扉を開けた。
浴場に入った瞬間、ふわりと鼻先にひのきの香りが届いた。
床も壁も天井も、すべて木でできている。古びて見えるのに、手入れが行き届いていて、どこかぬくもりを感じる空間だった。
湯船はそれほど大きくはなく、四人も入ればいっぱいになってしまいそう。
だからこそ、ひっそりと隠れた秘密の場所のようにも思えた。
白濁したお湯が、ゆるやかに波打っている。湯けむりがやさしく空気を包み、壁に反射した明かりが、まるで水の精が踊っているかのように揺れていた。
天井から吊るされた電球のやわらかな光と、湯の蒸気が溶け合って、夢を見ている気分。
奥にはガラス戸があり、向こうにちらりと庭のようなものが見えた。そこが露天風呂だろう。外はまだ明るいはずなのにどこか薄暗く、湯けむりが漂っているせいか、異世界に続いているみたい。
人の気配も、話し声も、まったくない。控えめな湯音だけが、静かに、やさしく響いている。
そっと湯に足を入れた。
やわらかい――それが最初の感覚だった。
温度はぬるめで、けれど肌に絡むようなとろみがあり、足先から心臓に向かって、じんわりと温かさが広がっていく。
ふう、と息を吐いて、肩まで湯に沈んだ。湯けむりの向こうで、ひのきの壁が少し揺れているように見える。
香澄さんの顔が、ふいに脳裏に浮かんだ。
何度も笑い合ったあの時間、そして――私を傷つけたあの目。
思い出しても、なぜか心が静かなまま。まるで湯が、いったんその感情を預かってくれているような、そんな気がする。
「この温泉は……」
ムギちゃんの声が聞こえた。いつの間にかそばに来ていたようだ。ふり返るとまた逃げてしまうかもしれないので、そのまま「はい」と答えた。
「不思議な効能があります。浸かっていると、心の奥にしまった感情が浮かび上がってきます。それをお湯に溶かすことで、心が元気になれます」
「じゃあ、このモヤモヤした気持ちを溶かしたい。やっぱり復讐なんてしてはいけないことだと思うから」
ちゃぽんと、天井からお湯が落ちる音がした。
「わかります」
ムギちゃんの声がやさしく耳に届いた。
「わたしも復讐したい人間がいたんです。でも、ここで働くようになって、その気持ちは消えました」
「ムギちゃんも?」
思わずふり向くと、ムギちゃんは「ひゃ」と悲鳴を上げてあとずさった。
「あ、ごめんなさい」
慌てて前を向く。
「いえ……わたしのほうこそごめんなさい。どうぞごゆっくりお入りください」
それを最後に声が聞こえなくなった。
白い湯気の中にいると、体の緊張が解けていくのがわかる。
けれど、しばらくすると、胸の奥から沸々となにかが込み上げてきた。香澄さんのこと。グループLINEの空気。自分が黙って我慢してきたこと。
ムギちゃんが言うように、湯底から嫌な感情が込み上げてくる。
こんな黒い感情、お湯に溶けてしまえばいい。
目を閉じ、そう願った。
畳部屋に戻ると、プレジは仰向けの格好でぐっすり寝ていた。
「ぐふう、ぐふう」と寝息を立て、大きなお腹も上下している。
ルナさんがお盆に載せた冷たいお茶を器用に運んできた。
「ミルクもありますけど、猫用のしかないんですわ。お湯加減はいかがでした?」
「ありがとうございます。とてもよいお湯でした。久しぶりにのんびりできた気がします」
お茶が冷たくておいしい。
「わたくしたちも営業後は温泉に浸かるんですのよ。もちろん、そのあとはきれいに掃除し、お湯を張り替えておりますの」
「不思議な場所ですね」
私の言葉に、ルナさんが「ええ」と黒目を三日月の形に細めた。
「わたくしも、なぜ人間語を話せるのか、二足歩行ができるのかはわかりませんの。プレジも、社長といっても雇われた身ですから、同じだと思いますわ」
「気にならないんですか?」
「さあ」とルナさんは尻尾を揺らした。
「わたくしからすれば、人間のほうがいろんなことを気にしすぎに思えますの。わたくしたちは人間に恩返しをして、あとは食べて寝てるだけの日々ですわ」
「恩返しってなんのことですか?」
「ほら、また気にしてますの」
う、と口を閉じると、ルナさんがクスクス笑ったあと、上目遣いになった。
「では、わたくしも気になっていることを伺いますわ。ムギちゃん、ちゃんと対応できましたの?」
「とても丁寧に話してくれました。でも……人間が怖いみたいですね」
ルナさんが正座をした。正座したりあぐらをかいたり、そして人の言葉を話したり。ありえないこともすっかり受け入れることができている。
「あの子、人間に復讐したい一心で、ここで働きはじめたんですの」
「そうなんですね……」
「温泉の効能でしょうか、お湯に復讐心を溶かしたようですが、人嫌いはあいかわらずで。まだ子猫ですので温かく見守ってあげてくださいませ」
深々と頭を下げるルナさんの向こうで、プレジが猫らしく背伸びをした。
ふああ、と大きなあくびをしてから、半分寝ぼけた目でこっちを見てくる。
「なんだよ。とっくに帰ったと思ってた。俺も湯に浸かりたいから、さっさと帰れ」
「お客様に失礼ですのよ。志保さんは回数券を買ってくれたVIPなお客様。プレじいも、もっと丁寧に接してくださいなの」
「プレじいって呼ぶな!」
言い合いをするふたり。ふと、頭をなでてみたくなり、プレジに手を伸ばした。
「うおおお!」
全身の気をぶわっと立てたプレジが、素早くあとずさる。
「びっくりした。気安く触るな!」
「ごめんなさい。昔飼ってた猫を思い出しちゃって」
慌てて謝る私の前に、ルナさんがちょこんと座った。頭を上げ、じっと私を見つめている。
これは……なでていいってこと?
おそるおそる頭に触れると、ゴロゴロと気持ちよさそうな音を出した。頭、喉のあたり、背中。なでるたびに、ユキのことを思い出す。
離れた場所で横になったプレジが、「で?」と問うた。
「温泉に入って少しは復讐心が消えたのか?」
「少しは。でも、まだ見返してやりたい気持ちも残っています」
ふん、と鼻から息を吐くプレジ。
「気楽に考えろ。回数券がなくなるまでに決めればいい、くらいに思っていれば、生きるのもラクになるぞ」
「わかりました。お茶、ごちそうさまでした」
立ち上がり、下駄箱へ向かう。ルナさんがついてきてくれた。
靴を履いた私に、ルナさんが白い布を渡してくれた。
「回数券を購入していただいたお礼ですの」
それは、手ぬぐいだった。猫の顔のシルエットが小さく印刷されてある。
「ありがとうございます。今日は、ここに来てよかったです」
「お気をつけてお帰りくださいですの」
ルナさんがそう言い、私も頭を下げる。
視界の端に、カウンターに隠れるように立つムギちゃんが見えた。勇気をふり絞って見送ってくれていることがうれしかった。
チリン。引き戸を開けると、夏の音がした。熱い風が頬に当たり、目が覚めたような気分になる。
それでも、今日あったことは夢じゃない。
車に戻り財布を確認すると、たしかに回数券がちょこんと収まっていた。
八月初旬の月曜日、事件が起きた。
朝陽の部屋の掃除をしていたところ、ベッドの下からビリビリに破かれた紙の切れ端がいくつも出てきたのだ。拾い上げると、色とりどりのイラストが印刷されている。すぐに、朗読コンテストで使う英語の絵本だとわかった。
胸がざわついた。数日前まで、リビングで練習していたはずだ。ページを破くなんて、よほどのことがあったに違いない。
絵本を抱えてリビングへ向かうと、私の手に絵本があるのを見た朝陽が、サッと目を逸らした。
「これ……どうしたの?」
問いかけると、朝陽はぷうと頬を膨らませた。怒った時にする仕草だ。
「僕、コンテストには出ないから」
「え? どうして?」
「出たくないから」
返ってきた言葉があまりにも短くて、逆に重たく感じた。
その場にしゃがみ込み、朝陽の目の高さに合わせた。
「出たくない理由、教えて?」
「ない」
「本当に?」
うつむいたまま、指先をもじもじと動かしている。嘘をついていると、すぐにわかった。合宿では練習できないからと、夜遅くまで音読していたのを知っている。むしろ、出たくてたまらない様子だった。
静かな時間が流れた。セミの声だけが、窓の向こうでけたたましく響いている。
「なにか、スクールであったの?」
そのひと言で、朝陽のまぶたがかすかに震えた。ごまかすのを諦めたように、唇が動いた。
「……仲間外れにされるから」
「え?」
「出たら、また言われる。だから出たくない」
「誰に言われるの?」
朝陽はしばらく黙って、ぽつりと答えた。
「みんな。全員」
その言葉を残して、彼は立ち上がり、自分の部屋に駆け込んだ。ドアが勢いよく閉まる音が、胸の奥に突き刺さる。
「朝陽、話そう。ママ、怒ってないから」
ドア越しに声をかけるが、返事はない。
しばらく待つと、カチャリと音がして、意外にもドアが開いた。朝陽は涙をこらえたような顔になっている。
「スクールの先生に言わないで。もっと意地悪されるから」
その言葉を聞いた時、ふと胸の奥に引っかかりを覚えた。
――ああ、そうだ。利津子さんが言っていた。
「ひょっとしてだけど、意地悪をしてるのは涼太くん?」
やさしく尋ねると、朝陽はうなずいてから、すぐに首を横にふった。
「健治とか夏央も。コンテストに出るなんて生意気だ、って。でも僕、知ってるんだ。全部、涼太が言わせてるんだよ」
「だから、絵本を破いたの?」
つい責めるような口調になってしまった。言い直そうとする前に、朝陽がドアを閉めた。
「あとはパパとお話する。もうすぐ帰ってくるんでしょ」
「そうだけど……」
「誰にも言わないで。約束だからね」
ベッドに横になったのだろう、スプリングがきしむ音がした。
これ以上聞いても話してはくれないだろう。
呆然としたままリビングに戻った。
朝陽が仲間外れにされている。意地悪をされている。息が吸えないほどの衝撃が、何度も波のように襲ってくる。
「ただいま」
隆幸さんが帰ってきた。
今日は半休を取り、朝陽とコンテスト会場の下見に出かける約束をしていた。
さっきあったことを話すと、隆幸さんは珍しく真剣な顔になった。
「俺が聞き出すから、志保は普通にしてて」
父の職場に復帰してからの隆幸さんは、精力的に仕事をしているだけじゃなく、私や朝陽のこともこれまで以上に気にかけてくれるようになった。
「私も一緒に行こうか?」
「男同士のほうがいいだろう。志保もちょっと気持ちを落ち着けたほうがいい。最近行ってる温泉にでも浸かってくれば?」
そう言うと、隆幸さんは朝陽を部屋から連れ出した。
この一ヶ月間、何度も日帰り温泉を訪れている。あの温泉の効果は本物らしく、香澄さんのインスタを開くことはなくなった。復讐心もお湯に溶けたらしく、鳴りを潜めている。
だけど、こんな時に温泉に行く気にはなれない。
「ママ、さっきの約束守ってね」
朝陽はそう言い残し、隆幸さんと出かけていった。会場の下見はやめ、公園でキャッチボールをするそうだ。
しばらくは家で悶々と時間を過ごしたけれど、どうにも落ち着かない。約束した手前、スクールに問い合わせることもできないし、香澄さんに聞く勇気もない。
仕方なくスーパーへ買い物に行き、気分を紛らわせることにした。カゴを持つ手に力が入らない。徘徊するように店内を歩く。
プレジは言っていた。『大切な人がターゲットにならないうちに、自分の言動を改めたほうがいい』と。
私のせいかもしれない。自分に正直にならなかったから、朝陽が仲間外れに……。
悔しさに視界が潤んだ時だった。アイスクリームの冷凍庫の前ですねた顔でうつむいている男の子が目に入った。
――健治くん。
そう思った瞬間、急ブレーキで足を止めていた。
話しかけるべきか、見なかったフリをするべきか――。
迷っていると、健治くんの向こうから歩いてきた梨沙さんと目が合ってしまった。授業参観にでも行くような紺のスーツを着ている。
「あ、こんにちは」
呑気に挨拶をしている場合じゃないのに、取り繕った笑みまで浮かべてしまう。
梨沙さんは私だとわかると、慌てた様子で駆け寄ってきた。
「あっ、ちょうど今! あの……!」
言葉に詰まったまま、梨沙さんが深々と頭を下げた。
「すみません……! 健治のこと、本当に……! あの、今ちょうど、謝りに伺おうとしてたの」
言葉を選びながらも、早口でそう告げる梨沙さんの目元には、焦りと申し訳なさがにじんでいた。
「うちに?」
「健治から話を聞いて……。健治が、朝陽くんにひどいことをしたみたいで」
梨沙さんの目尻が少し赤い。その表情から彼女が重く受け止めているのは伝わってきた。脇に置いた買い物かごの中に、贈答用のお菓子が入っている。
「それって……仲間外れにしたこと?」
そう尋ねると、梨沙さんは首を横にふった。
「健治。こっちに来て」
梨沙さんに呼ばれ、健治くんがおずおずと近づいてきた。床を見つめるように目を伏せている。
「朝陽くんのお母さんだよ。ちゃんと自分がやったことを言って」
健治くんはギュッと唇を噛んでいたが、
「違うもん」
ぽつりとそう言った。
「俺はやってないもん。見てただけ」
「健治!」人目もはばからず梨沙さんが怒鳴った。
「見てただけってなに? それも同じくらい悪いことだって言ったでしょう!?」
話の内容が読めず、朝陽にするように床にしゃがみ、健治くんと視線の高さを合わせた。
「健治くん、スクールでなにがあったの?」
私の声は、自分でも驚くほど穏やかだった。怒鳴る気も、責める気もなかった。ただ、知りたかった。
「……いじめようぜ、って涼太が言った。最初はおもしろがってやってたけど、怖くなった。だからママに言った」
「朝陽が朗読コンテストに出ることが嫌だったの?」
「違う。ううん、違わない。涼太が『生意気だ』って怒ってるだけ。あいつ……絵本を破ったんだ」
ああ、そうだったんだ……。朝陽が自分で破ったとばかり思っていた。
「ごめんなさい。この子に今日聞いて、本当にショックで……。本当に申し訳ありませんでした。朝陽くんにも直接謝罪をさせてください」
梨沙さんがハンカチで目元を押さえながら言った。
迷いながら、もう一度健治くんに目を合わせた。
「これからは気をつけようね。でも、健治くん、ママにちゃんと話をしてくれてありがとう」
ふいに健治くんが表情を暗くした。
「朝陽、泣いたんだ」
……泣いた? あの子が、人前で?
「俺たち、ずっと涼太に我慢してたんだ。なのに、俺があっち側に回ったから。だから、ちゃんとごめんなさいって言いたい」
――それから私は、どうしたのだろう。
ああ、そうだ。隆幸さんに連絡を入れ、ふたりを見送ってから車に戻ったんだ。
エンジンで震える車内。クーラーをかけても、汗が止まらない。
スマホのアドレスから香澄さんの名前を呼び出し、しばらく見つめる。
帰る前に、香澄さんに真実をたしかめたい。ううん、たしかめなくちゃいけない。
震える指を抑えながら、通話ボタンを押した。
『もしもし? 志保さん?』
軽い声。こちらの空気を読まない、飄々とした調子。
「ちょっといいかな。朝陽のことで、少し話したいんだけど」
『あー……あの話だよね? 絵本のこと』
軽い笑い声が聞こえた。
『ふざけてたら破れちゃったんだって。新しいの買って返すよ』
なんでもないことのような口調がざらりと耳に届いた。
この記事の詳細データや読者のコメントはこちら


