【第4話】夢叶う野菜スープ 水瀬瑠璃
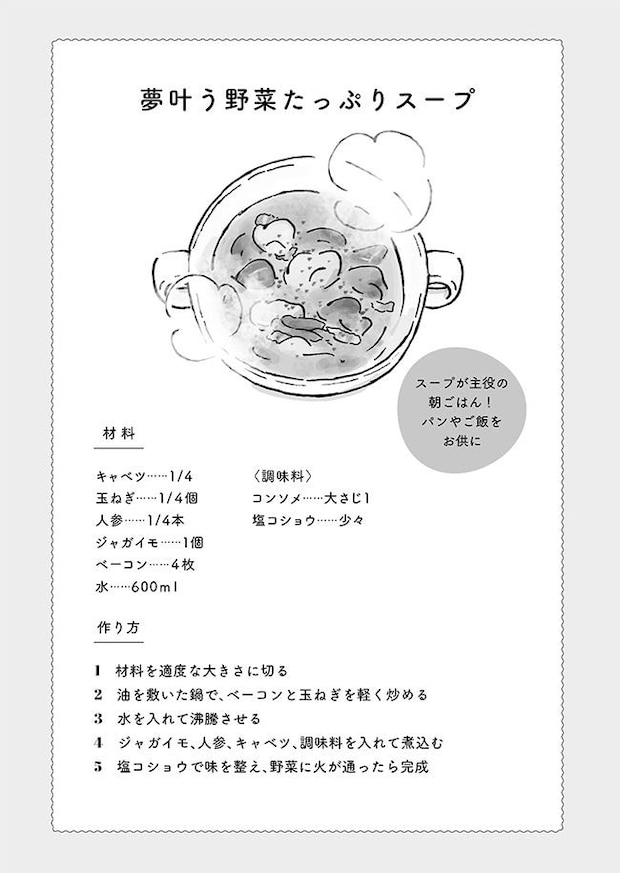
(C)サトウユカ/スターツ出版 無断転載禁止
私、水瀬瑠璃(みなせるり)の幼少期の夢は、お母さんのように素敵なママになることだった。
母は専業主婦で、誰よりも早く起きて、毎日朝ごはんを作ってくれていた。
眠たい目を擦りながら起きると、迎えてくれるのはキッチンから聞こえるおいしそうな音。まな板の上でトントントンと響く包丁のリズムや、フライパンでなにかがじゅわっと弾ける音。そして、今でも思い出せるのは、部屋中に広がるおいしそうな匂いに心が弾んでいたこと。
私は母親の鏡のようなお母さんの背中を見て育ったおかげで、いつの日からか「お母さんみたいな素敵なママになりたい。結婚して家族に素敵な朝ごはんを作ろう」と思うようになっていた。その夢がどれだけ難しいか知らずに……。
自分に結婚は向いていないと気づいたのは、いつ頃だろう。
三十代。いや、それよりもっと早くから、結婚願望は消えていたのかもしれない。
二十代、就職した会社はいわゆる大手といわれる飲料メーカーだった。最初に配属されたのは、今とは違うマーケティング部。販売戦略を考えたり、商品が売れる仕組みを作る、そんな仕事に全力投球していた。戦略通りにキャンペーンが当たれば、売上に直結する。頑張れば頑張るほど、結果が出る仕事は私に向いていると思った。
三十代、仕事に対して若い世代との温度差を少しずつ感じはじめた。
今の子は、熱量よりコスパが大切らしい。平成育ちの精神論は、もう通用しなかった。
気がつけば三十歳を過ぎても独身で、結婚願望は余計に薄れていくばかり。
いよいよ結婚を諦めたのは三十五歳を過ぎた頃。
私は生涯独身で生きていこうと決意も固めた。
……その頃からだったかな。
一生ものの財産として、自分のために終の住処が欲しいと思い始めたのは。
実際に不動産会社をめぐり、行動に移したのは四十歳を目前にした頃だった。
働き詰めで積み上げた貯金を頭金にし、足りない分は住宅ローンで賄った。
そうして、ついに手に入れた念願のマイホーム。私にとって終の住処。
四十歳を迎えた今、当初の計画にはなかった暮らしをしている。友人とルームシェアだ。
歳を取れば取るほど、目新しいことなんて、なかなか経験できないと思っていた。
だけど、今の生活は当初の人生設計とは、ガラリと変わっている。
よく聞く言葉だけど、人生はなにが起きるか本当にわからない。
子供の頃に描いた理想の大人像とは、きっとかけ離れてしまったと思う。
それでも今の私は、なんとか日々を生きている。
カーテンの隙間から差すやわらかな日差しが、テーブルの上に置いたマグカップや読みかけの本を照らしている。
この家を買ったばかりの頃は、綺麗すぎてがらんとしていた。
けれど今は、ソファに投げ出されたクッションや、新しく加わった三人分の食器。
物が増えていくたびに、生活感がにじみ出てきたな、としみじみ思う。
そして、その変化がたまらなく嬉しかった。
「今日の朝ごはんは私が担当か……なににしようかな」
朝食を一緒に食べようと決めたあと、交替制で作ることも後付けされた。これが案外正解だった。
自分以外の担当の時は、ゆっくり起きても、朝ごはんが準備されていて。
こうして自分が担当の時は、なにを作ったら喜んでくれるかな……。とちょっとわくわくする。それに加えて、作った人が片付けも担当することも決まった。そうやって事前に決めることで、誰か一人の負担にならなくて済む。共同生活をするうえでも、ルールを決めたのは良かったと思う。
「……あ、結構時間ないじゃん」
時計を見ると、翠と朱音が起きる時間が迫っていた。料理に時間はかけられないので、すぐに作業に取り掛かる。
本日作るのは野菜たっぷりスープ。
メインはスープにして、ごはんかトーストを選んでもらおうと思う。
材料は全部冷蔵庫に残っていたあまりもの。
キャベツ、玉ねぎ。ジャガイモ、人参。味の深さを出すためにベーコン。
栄養を考えて、野菜はあるもの全て使ってしまいたいくらい。まずは、キャベツを洗って、小さめに切っていく。
そして、玉ねぎ、ジャガイモ、人参は皮をむいて、適当な大きさにカットする。
ゴロゴロと大きめの具材にしたいところだけど……。
今日は全体的に小さめに切ることにした。
具材が大きくなると、火が通る時間がかかってしまうからだ。
食材を切っている間に、鍋に張っていた水が沸騰したみたい。本当は煮えにくい材料から、投入していくところだけど……。
えーい。この際全部入れてしまえ。
順番を気にすることなく、全ての材料を鍋に入れた。
几帳面な翠が見ていたら「全部一緒に入れるの!?」なんて驚かれてしまいそうだ。そんな姿を想像したら、思わずふっと笑みがこぼれる。
しばらくコトコト煮込みながら、待っている間に、白いごはんを炊く準備を済ませた。
料理も仕事と同じで、要領の良さが大事だ。同時進行でうまく回せていることに満足して、一人なのに得意げな顔になってしまう。
竹串を用意し、ジャガイモと人参に中まで火が通っているか確認する。人参はすっと竹串が通った。ジャガイモは煮込みすぎたようで、竹串を通す前にほろりと崩れた。まあ、特に問題はない。これもご愛嬌というものだ。
次に味付けをしていく。使うのはコンソメと塩胡椒だけ。シンプルだけど、私は一番好きな味なんだ。
これ以上ジャガイモが崩れないように、全体をそっとかき混ぜた。
「よしっ、味見は大事だから……」
そう口にしながら、心の中ではしめしめと笑っていた。要するに、味見という名の一口を楽しみにしていたのだ。
小皿に少量のスープを注ぎ、口に運ぶ。
「はあ~~」
おいしいという感想よりも先に出たのはため息だった。
これで朝ごはんにぴったりのあたたかいスープは完了っと。
味見の一口だけでは足りず、もっと食べたくなった。
けれど、グッと唾を呑み込み我慢する。
そうしている間に、リビングのドアが開く音が聞こえた。
「……おはよ」
「るりぃ、おはよお。あれ、すごくいい匂いがする~」
翠と朱音がタイミング良く起きてきた。
寝ぼけて目を擦っていた朱音は、匂いをかぎ取ったのか、一目散にキッチンへとやってきた。
「この匂いの正体、今日の朝ごはんなにー?」
まるでごはんが待ちきれない小学生のようだ。
その様子に、思わず笑ってしまう。
「今日の朝ごはんのメインは、野菜たっぷりスープです」
「わぁ、野菜たっぷりはありがたいわ」
私たちはいい歳である。もちろん、健康のこともしっかり考慮済み。
「ごはんと、トーストどっちにする?」
「選択制なの? ふふっ、なんだか楽しくなっちゃうね。わたしは白いごはんもらおうかな」
そう言って翠はやわらかい笑みを浮かべた。
「あたしはね、パン派だからトーストにする」
朱音からトーストの要望を受けて、パントリーに余っていた食パンをトースター―に入れた。
その時、炊飯器から炊きあがりの音楽が鳴り響く。ちょうどよくごはんも炊きあがったみたいだ。
「これで準備は終わり。朝ごはんにしよ!」
私は意気揚々と声をあげた。熱が冷めないようにと、できあがった料理を素早く運んでいく。
野菜たっぷりあたたかいスープ。白いごはん、付け合わせに納豆。こんがり焼けたトーストが食卓に並んだ。出来立ての料理を眺めると、我ながらいい朝ごはんになったな。と誇らしくなる。
「お腹ぺこぺこだったの。いただきます」
「いただきます」
「瑠璃、作ってくれてありがとう! いただきまーす」
朱音は手を合わせると、挨拶と共にお礼も添えた。まだ起きたてだというのに、声は弾んでいる。
そういえば、食べる前にいつもお礼を伝えてくれる。それが妙に心地良い。
「ねえ、朱音っていつもお礼言ってくれるよね?」
トーストにかじりつく寸前だった朱音は、大きな口を開けたままぴたりと止まる。
「……そう? 自分では意識してなかったけど、言ってるかな?」
朱音は少し考えてから、思い出したように顔を上げる。
「あ、わかった。たぶんね、今まであたしが料理をしても、旦那も息子もお礼の一言がなかったんだ。毎日作っても、当たり前みたいな顔されてさ。あれ、ほんっとうに腹立つんだよね」
そう言った朱音は、わかりやすく顔をしかめてみせた。
「なるほど、それで今は忘れずに言ってくれるんだ」
「特別意識はしてなかったけどね。その経験があるから、今は自然と口に出ちゃうんだと思う」
朱音は眉間のしわがなくなって、照れくさそうに笑う。
「朱音に『ありがとう』って言われると嬉しい気持ちになるんだ」
「わたしもそうだった。お礼を言われると嬉しくなって、おいしいと嬉しいで気持ちが二倍になる」
翠も頬張りながら、穏やかに笑った。
『ありがとう』を交わすだけで、食卓がもっとあたたかくなる。なんとも不思議で、素敵な言葉だ。
「瑠璃、作ってくれてありがとね」
急に改まって翠が軽く頭を下げた。くすぐったいけど、やっぱり嬉しい。みんなで顔を見合わせてまた笑った。
「……ねえ、そろそろ食べていいかな? ずっとお預け喰らってるみたいになってるよ」
そう言った朱音は、右手にトーストを持ったまま。
「ははっ、本当だ。食べよ!」
私と翠が最初に手を付けたのは、野菜スープだった。湯気を冷ましながら、ごくんと流し込む音が重なる。
「あったか~い」
「おいしいー」
こぼれ落ちたような感想に嬉しくなる。
朱音は焼き立てのトーストにかじりつき、満足そうな表情になった。私は翠と同じごはんを選んだ。付け合わせの納豆のパックを開ける。付属のからしを入れて、箸でくるくると混ぜた。それから納豆を熱々のごはんに乗せていく。パクッと頬張ると、納豆のねばり気とごはんの粒が絡み合う。
「納豆っていいよね。おいしいし、健康にもいいなんて」
噛み締めながらしみじみと思う。
「わかる。何度食べても飽きがこないんだよね」
隣で同じく納豆を食べていた翠は深く頷いた。
「そういえばさ、小さい頃二人は将来の夢ってあった?」
朱音はサクッとトーストをかじりながら、思い出したように質問を投げかけた。
「朝から深めの話?」
「朱音らしくない。突然どうしたの?」
唐突すぎる質問に聞き返すと、朱音は真剣な顔で答える。
「あたし仕事を探してるんだ。第二の人生。どうせなら、本当にやりたい仕事に就きたいなあって思ったの」
「それで将来の夢ね。わたしはみんなが知っての通り、子供の頃から小説家です」
スープとごはんを頬張りながら、翠は答えた。
翠は子供の頃からの夢を叶えている。真面目で努力家の翠だからこそ、成し得たことだ。
「子供の頃の夢を叶えるのってすごいよねー」
「ふふっ、遅咲きだけどね」
朱音は口を動かしながら、今度は私に投げかける。
「瑠璃は?」
「えっと、私は……」
朱音に話を振られて、すぐに答えることができなかった。
私が子供の頃に抱いていた将来の夢。それは、すぐに思い至った。
〝お母さんみたいに家族においしい朝ごはんを作ること〟。
すぐに頭に浮かんだけど、なんとなく言い出しにくい。
だって、叶わなかったことになるし、私のキャラではないような気がした。
「うーん、なんだったっけなあ。そういう朱音は?」
うまい誤魔化し方が出てこなくて、あやふやに答えて朱音に話を振る。
「あたしはね、実はカフェとか小さなお店を開きたかったの」
それは私も初めて聞いた話でちょっと驚いた。
「初めて聞いたよ」
「そうでしょ? 初めて言ったもん」
「朱音、料理上手だし気が利くし、向いてるんじゃない?」
朱音は主婦をしていたこともあってか、料理が上手だった。
私や翠が作らないような、ちょっと洒落た料理をいつも作ってくれる。
「嬉しいー。本気でそっち方面で探そうかなぁ?」
話しながらも、朝ごはんを口に運ぶ動作は欠かさない。スープを一口すすって、ごくりと喉を鳴らす。そんな風に食べていると、いつのまにかテーブルの上の食器は、どれも空になっていた。
おいしいで満たされた体は、ぽかぽかと体温があ上がる。
「瑠璃のスープの味、優しくておいしかったー」
「あたたかいスープっていいね。体があたたまるよ」
「お粗末さまでした」
照れ隠しに両手を合わせて会釈をする。あたたかい言葉は、たしかに私の心に染沁みて、自然と口角があがった。
みんなが食べ終えたので、テーブルの上を片付けようとした時だった。
ふと思考が停止して、古い記憶が蘇る。
そういえば、お母さんも私が「おいしかった」って言ったら、嬉しそうに笑ってたなあ。
にこりと優しく笑うお母さんの姿が鮮明に浮かんだ。
「ある意味……叶ったかもしれない」
私はぼそりと呟いた。
「え、なにが?」
翠と朱音は、同じタイミングで片付けていた手を止める。そして、不思議そうに首を傾げた。
「私の将来の夢さ……叶ってた」
再度はっきり繰り返す。今度はしっかりと声を張った。
「私の将来の夢は〝お母さんみたいに家族においしい朝ごはんを作ること〟だったの」
言い終えた瞬間、顔が一気に赤くなる。笑われるんじゃないか。とすぐに後悔した。思った通り、翠と朱音は顔を見合わせている。
「あ、でも違うよね」
慌てて取り繕おうとすると……。
「それは、叶ってるって言っていいんじゃない?」
「ある意味じゃなくて叶ってるよ」
間髪容れずに、肯定の声が返ってきた。途端に嬉しくなって目頭が熱くなる。
二人に言われて、ようやく腑に落ちた。
昔、心に描いていたようなお母さんにはなれなかった。
だけど、今こうして大切な人のために朝ごはんを作って、同じ食卓でごはんを食べている。
それだけで、あの頃の夢はもう叶っている気がした。照れくささを超えて、自然と笑みがこぼれる。
誰かと食卓を囲むこと。
誰かのために料理を作ること。
そして、誰かが自分のために料理を作ってくれること。
それは日常の延長線上にあるものだけれど、実はとても幸せなことなのかもしれない。
あまりに、近すぎて見えていなかった。
……誰かのために朝ごはんを作って、一緒に笑って食べる。
そんな夢だった日常が、今こうして目の前にあった。
「瑠璃の夢が、こういう形で叶うのってなんだか嬉しい」
「これからも、楽しく朝ごはん食べようね」
二人の笑顔のおかげで、子供の頃に抱いた夢が、ようやく報われた気がした。
昔憧れていた夢の形とはちょっと違うけれど。
現状も、案外悪くない。……いや、はっきりと言いきれる。
友人とルームシェアをして、おいしいごはんを食べる。
この生活が、私にとって最高の日常だ。
この記事の詳細データや読者のコメントはこちら


