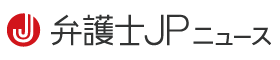9月に日本で公開された映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、全米では興行収入第1位となるヒットを飛ばし、日本でも話題になった。一方、同作は「Qアノン」と呼ばれる陰謀論との関係が指摘されており、注釈がなく配給・宣伝されたことが問題視されている。女優の板野友美氏が感想を投稿した際にも、SNSで物議をかもした。
“サウンドオブフリーダム”観てきました。
全米興業収入第1位
児童人身売買の実話を基に制作された映画。
アメリカで公開に5年、更に日本公開まで1年もかかっての公開だそうです。たくさんの方に今すぐ
見てほしいなと私は感じました。
特に、小さな子どもがいる親は必ず観るべき。。… pic.twitter.com/mqfN8KT2bV— 板野友美 (@tomo_coco73) September 29, 2024
同作に限らず、アメリカ発の映画やドラマは「陰謀論」と関連していることも多い。背景には、アメリカという国の成り立ちそのものが、“幻想”を“現実”にする陰謀論と親和性が高いという点がある。映画やアメリカ文化、そして陰謀論にも造詣の深い、映画ライターの伊藤聡氏が解説する。
アメリカ本国で大ヒットした『サウンド・オブ・フリーダム』
今年の9月末に公開され、映画ファンのあいだで話題になった『サウンド・オブ・フリーダム』という映画をご存じだろうか。
子どもを誘拐して人身売買する悪の組織と、それに立ち向かう主人公を描いた本作は、「実話に基づく」としつつも創作的誇張が多く、陰謀論的な想像力で描かれた、かなり信頼性に欠く作品であった。
また、作品はこれといった注意書きや注釈がないまま劇場公開されているため、多くの映画ファンが「知らずに見てしまった」「うっかり信じるところだった」と困惑する事態になった。私自身、公開予定の一覧表でこの作品を見かけたとき、おもしろそうだなと気になっていたし、まさかこうした怪しげな映画が大手のシネコンで公開されるような事態は起こるまいと信じ切っていた部分があった。
同作は、1450万ドルの制作費に対して、2億5000万ドル以上の収益が上がっており、その話題性の高さから日本での公開に至ったようである。
「実話に基づく」とは言うものの…
本作の監督と主演俳優は「Qアノン」と呼ばれる米国発の陰謀論に傾倒しており、主人公のモデルとなったティム・バラードは確かに米国元政府職員ではあるものの、法的・倫理的な過ちを多数指摘される人物である。
映画そのものも、どこまでが事実でどこからが創作なのか判別がつかず、人身売買について誤った印象を与えてしまいかねない。完全なフィクションとして楽しむならいいが、製作者自身がその境界線を見誤っているような印象がある。
また主演のジム・カヴィーセルは、Qアノンの集会に参加して「人身売買組織が子どもの血液から若返りの特効薬を抽出しており、ハリウッド俳優がその薬を使用している」などと出来の悪いホラー漫画のような話もしている。こうした怪しげな発言をする人物が関与した映画を額面通りに受け取ることはできないだろう。
作中では、誘拐された子どもを助けるためにコロンビアにある反政府組織のアジトへ潜入する主人公が描かれるが、かかる描写が事実であるかどうかも不明だという。
人身売買にまつわる陰謀論と「Q アノン」
劇場で販売されているパンフレットを読むと、「本作で描かれていることが真実であるか否かについては議論の余地がある」「(過去にカヴィーゼルが)陰謀論を吹聴した」と記載されてはいるが(レビューを依頼された映画ライターの方の葛藤が想像できる)、映画を見た観客のうち、パンフレットを購入して目を通す人の割合は少ないと思われる。
現実における子どもの誘拐や人身売買は、親が子を売るといった、身内や知人による犯行が多いという専門家の指摘もある。個人的にも、こうした映画が大手のシネコンで普通に公開される状況が意外だった。
また、もっとも驚いたのはエンドクレジットである。主演俳優が「大手のスタジオとは違って、自分たちには資金がない。カンパしてほしい」と観客に頼み込むと、画面に寄付用のQRコードが出るという掟破りの展開に、こんなになりふり構わない映画は初めてだと感じた。エンドクレジットは物語の余韻を楽しむものだと思っていたので、主演俳優が真剣な表情で寄付を求めてくる姿に、かつてない斬新さを覚えたのであった。
エンドクレジットでスクリーンから観客に向かって寄付を求めるような映画を公開するのであれば、シネコンや配給会社には、その映画が信頼に足るものかをチェックする役割があってもいいのではないかとも思うのだが……。
「ピザ・ゲート」「地球平面説」…さまざまな陰謀論
本作のテーマでもある「子どもの人身売買」は、陰謀論者のQアノンが好む題材だ。よく知られたデマのひとつに「ピザ・ゲート」がある。
米政治家ヒラリー・クリントンが人身売買に関与しており、ワシントンD.C.にあるピザ店(コメット・ピンポン)がその本拠地になっているという荒唐無稽な空想は、インターネットで拡散されていくうちに真実であると信じられるようになり、ついには店内にライフル銃を持った男が押し入って発砲する事件にまで発展した。
なんの変哲もないピザ店が、いつの間にか悪の巣窟であると信じられているのだから恐ろしい。一度その妄想に火がついてしまえば、どれだけ否定しても疑いを晴らすことができない陰謀論は、アメリカが抱える大きな問題のひとつである。
「そんなことはあり得ない」と否定すればするほど、「だからこそ怪しい」「必死に否定するのが逆に疑わしい」と妄想は深まってしまう。根拠などなくとも、多数の人びとが繰り返し取り上げるうちに、それは謎に包まれた悪の象徴になるのだ。こうなれば陰謀論の拡散を止める方法はない。
私の好きなドキュメンタリー作品に、『ビハインド・ザ・カーブ -地球平面説-』(2018)がある。これは、地球は丸いのではなく、料理を載せて運ぶトレイのように平面である、と信じる人びとを追った映像作品だ。この途方もない想像力には感動すら覚えてしまうが、実際に地球平面説を唱える人を取材すると、周囲から冷たい目で見られたり、コミュニティから孤立してしまったりするそうである。
平面説を信じる方にはやや気の毒な忠告となるが、やはり地球は丸いと思う。いまからでも正気を取り戻してほしいと願うばかりだ。
アメリカ映画における陰謀論の想像力
これまでアメリカ映画は、陰謀論を作品の題材として多く活用してきた。
たとえば1997年から始まった『メン・イン・ブラック』シリーズは、アメリカでこれまで語られてきた無数の陰謀論を詰め込んだショーケースのような作品となっており、これまで合計で4作の映画が発表されている。
『メン・イン・ブラック』のベースとなるのは「UFOを目撃した人のところへ黒ずくめの服装の男がやってきて、『決して口外するな』と脅す」というアメリカの都市伝説だ。こうしたうわさ話をベースにした同作では、地球外生命体がすでに地球で数多く暮らしており、政府はその事実を隠蔽している、といった陰謀論がコミカルに描かれる。
『メン・イン・ブラック』のでたらめな想像力は観客を大いに楽しませる。陰謀論は、それを娯楽と割り切って分別を持って眺めるぶんには、実に愉快なエンターテイメントである。だからこそ困ってしまうのだ。
陰謀論の厄介なところは、その無類の楽しさである。現実と虚構の区別をしっかりとつけ、用法・用量を守って楽しむぶんにはいいのだが、こうした虚構が行きすぎてしまうと、やがて「バラク・オバマを護衛するセキュリティは爬虫類型宇宙人(レプティリアン)だ」などとまじめな顔で語りだすことになる。こうなると、「陰謀論は適度に楽しむ遊びです」と駅前に貼り紙でもしておいた方がいいと思う。
90年代に大ヒットした『Xファイル』も…
こうした陰謀論を大きく取り上げた映像作品のなかでもっとも重要なのは、テレビドラマシリーズ『Xファイル』(1993〜2002)だろう。
UFOに妹を誘拐された過去を持つ主人公のFBI捜査官モルダー(デイヴィッド・ドゥカヴニー)が、相棒のスカリー(ジリアン・アンダーソン)とともに、超常現象やUMA、オカルト、政府の陰謀、宇宙人などについて調査を続けていくというあらすじだ。
私は『Xファイル』の大ファンで、当時レンタルビデオ店へ足しげく通っては、ビデオを借りて家で見ていた。
このシリーズで取り上げられるテーマは、実際にアメリカで流布している陰謀論を下敷きにしたものが多く、本作さえ見ていれば、アメリカの陰謀論はほぼ網羅できるという百科事典のような内容になっている。エリア51やブラック・ヘリコプターといった有名な陰謀論を知ったのもこのドラマだった。
もちろん同作はフィクションだが、作品としてはいま見ても充分におもしろい。この記事のために一部見直したが、そのふしぎな雰囲気にぐっと引き込まれてしまった。
物語が現実を侵食する
私は純粋なドラマ、エンタメとしてワクワクしながら『Xファイル』を見ていたが、アメリカ本国では思わぬ影響を与えてしまっていたようである。『Xファイル』は90年代を通して、アメリカ人に陰謀論教育を施してしまっていたのだ。
ドラマを通じて陰謀論や超常現象、地球外生命体に関する長期の履修を終えたアメリカ人は、2001年にはすでに数多くのUFOの目撃情報を届け出ていたが、2015年にはその数が2001年の241パーセントにまで増えていた。
過去にも、人種差別団体KKKを描いた映画『国民の創生』(1915)が大ヒットし、活動が下火だったKKKを実際に復活させてしまう、といったできごとはあったが、『Xファイル』も同様に、テレビドラマが現実に侵食してしまった例だといえる。
それから数十年後のコロナ禍では、ワクチンに関する根拠のないデマがずいぶんと広まったが、『Xファイル』は90年代の段階で「政府が操る影の組織が、異星人の地球入植に備えてワクチンを開発していた」というエピソードを放送しており、その先見の明(と言っていいのだろうか?)には驚いてしまう。
ワクチンに関するデマの想像力も、あるいは『Xファイル』あたりに起源があるのではないかと思いたくなるほどだ。
アメリカは建国当時から「陰謀論」と共にあった
なぜ、アメリカではこのように陰謀論が広く唱えられ、信じられるのか。
昨今、日本でも陰謀論を口にする人は増えてきたが、さすがにアメリカほどではない。アメリカには長い陰謀論の歴史があるのだ。
ではなぜアメリカなのか。アメリカの陰謀論を研究する著述家のカート・アンダーセンは、著書『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』(2019年、山田明美・山田文 訳、東洋経済新報社)で、アメリカが陰謀論の温床となる理由をこう説明している。
「アメリカの歴史は、知的自由という啓蒙主義的概念を初めて具体化する実験の歴史でもあった。誰にでも、好きなことを信じる自由がある。だが、その考え方が手に負えなくなるほど力を持ってしまった。
わが国が奉じる超個人主義は最初から、壮大な夢、あるいは壮大な幻想と結びついていた。アメリカ人はみな、自分たちにふさわしいユートピアを建設するべく神に選ばれた人間であり、それぞれが想像力と意志とで自由に自分を作り変えられるという幻想である。
つまり、啓蒙主義の刺激的な部分が、合理的で経験主義的な部分を打ち負かしてしまったのだ」
「この国は、一攫千金やユートピアや永遠の命などの幻想を入れる空っぽの容器として始まった。新たな幻想を無限に生み出しても収められるほどの大きな容器である。こんなことは以前にはなかった。
また、ごく普通の人々が主導して荒野から国を造り上げ、その世界を作り変えていった。こんなことも以前にはなかった。
たった1世紀の間に、(白人)アメリカ人の人口は数千人から100万人に増え、それから20〜30年ごとに倍増を続けた。これまでにない特異な国は、繁栄の一途をたどっていく。共存する幻想は、わずかな数から数十、やがて数百に増えた。それらの夢は実現しつつあるかに見えた」
「幻想を入れるうつわ」
このようにカート・アンダーセンは、アメリカという国は「幻想を入れるうつわ」として大きくなったと指摘している。なるほどと納得する解釈だ。
たしかにアメリカは「なんでも叶う」「ありとあらゆることが起こり得る」という可能性に満ちている。アメリカ史を読むと、本当になにもない荒れ地にやってきて、ここに国を作ろうとゼロからスタートする人びとの異様な熱気が感じられて本当に驚くのだ。
そしてアメリカはまたたく間に巨大化し、世界の中心となった。世界の歴史を見ても、このような大成功はあまりない。こうなれば、アメリカではあらゆることが起こり得ると信じたくなる気持ちもよくわかる。
かつてイギリスから渡ってきた移民は、信教の自由、すなわち「自分の信じたいことを信じる」自由を得るために新大陸へやってきた。そうした国で陰謀論が生まれるのは、ある意味で必然なのかもしれない。なにしろアメリカという国は、どんな幻想でも入ってしまう、とても大きなうつわなのだから。
2021年にはトランプが議会襲撃を煽動
アメリカの原動力は、あらゆる幻想を飲み込んで巨大化する、そのうつわの大きさにあるのかもしれない。
『Xファイル』には「I want to believe(私は信じたい)」という有名な言葉がある。「誰にでも、好きなことを信じる自由がある」というアメリカの特性から考えても、陰謀論はアメリカ国家の成り立ちにかかわる問題なのではないか。
たしかにアメリカには、あらゆる願いが叶う場所、いかなる夢でも現実になる土地という雰囲気がある。そしてそれは、19世紀のカリフォルニアで起きたゴールドラッシュのように、一夜にして途方もない成功が起こり、信じられないような夢が本当に叶ってしまう場合もある。こうしたアメリカらしさと陰謀論とは、切っても切り離せないものであり、表裏一体となっているのではないか。
しかし同時に、陰謀論的な想像力は危険に満ちている。2021年1月、前年の大統領選挙で敗退したドナルド・トランプは「不正選挙だ」「選挙は盗まれた」と民衆にけしかけたが、その煽動によって議事堂に乱入し、暴動を起こした人びとは、「不正選挙」という陰謀論によって結束していたといえる。
トランプはまた、映画『サウンド・オブ・フリーダム』の予告編リンクをSNSに投稿しており、ここにも厄介な陰謀論との関連性が見てとれる。
やはりアメリカは、その成り立ちから陰謀論とともにある国なのだろう。