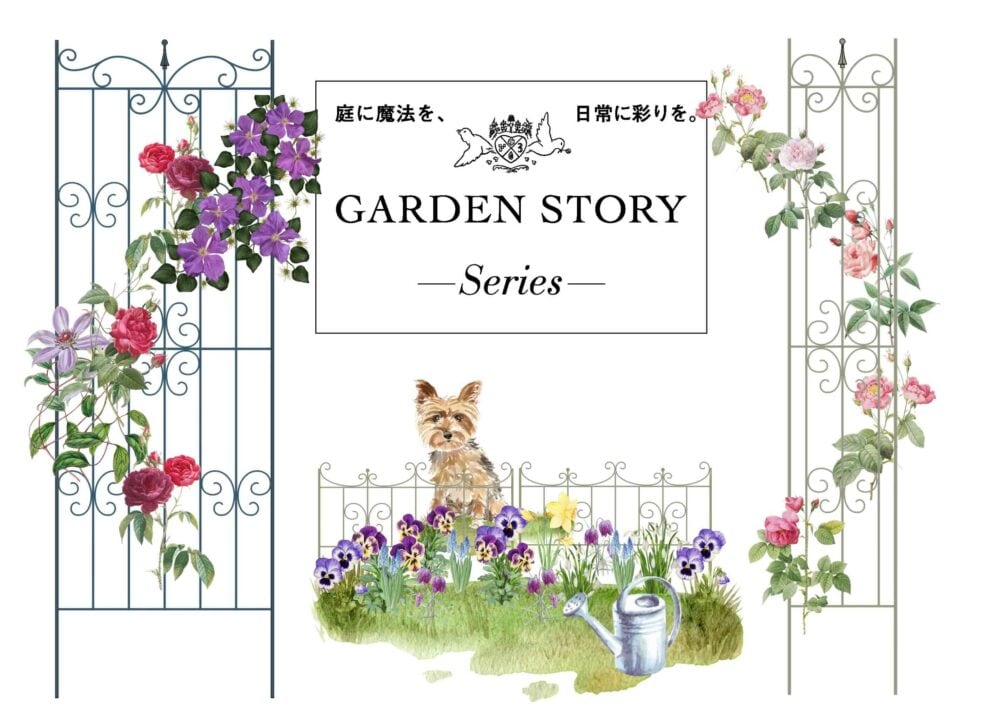完熟した美味しい果実を収穫できるのは、家庭で果樹を栽培することの最大のメリット。昔から日本に自生してきたビワは環境に馴染みやすく、育てやすい果樹です。この記事では、オレンジ色の実が楽しめるビワの基本情報や特徴、名前の由来や花言葉、品種、育て方について、詳しく解説します。
ビワの基本情報

ibrahim kavus/Shutterstock.com
植物名:ビワ
学名:Eriobotrya japonica
英名:loquat、Japanese plum、Chinese plum
和名:ビワ(枇杷)
科名:バラ科
属名:ビワ属
原産地:中国
形態:常緑性高木
ビワはバラ科ビワ属の常緑果樹です。原産地は中国で、古い時代に日本に伝わったと考えられています。放任してもよく育ちますが、開花期が冬のため寒さに当たると実つきが悪くなります。氷点下まで下がる地域では鉢植えにして、冬は暖かい場所で管理するとよいでしょう。自然樹形では2〜5mになりますが、毎年の剪定によって2m前後の樹高をキープすることができます。日本では昔から馴染みのある果樹で、奈良時代の文献にも登場しており、江戸時代頃から栽培されるようになりました。ビワは自家受粉するので、受粉樹を植える必要がなく、1本植えれば結実します。
(広告の後にも続きます)
ビワの花や実、葉の特徴

Olga Ilinich/Shutterstock.com
園芸分類:果樹
開花時期:11〜1月
樹高:2〜5m
耐寒性:やや弱い
耐暑性:強い
花色:白
ビワは11~1月にかけて、クリーム色がかった白い花を咲かせます。円錐花序にまとまって咲く花は地味な見た目ですが、甘い香りがあります。主に果実の収穫のために栽培されますが、葉もお茶に利用でき、また葉が濃く茂るため目隠しや庭木としても栽培されます。
ビワの果実

Subbotina Anna/Shutterstock.com
ビワの果実は熟すとオレンジ色になり、サイズは3〜4cmほどです。旬は5〜6月。柔らかい白い産毛で覆われた果実の中には、大きな種子があります。房州ビワや茂木ビワや甘香など一部の品種は、高級フルーツとしても知られています。産地は長崎、千葉、鹿児島などが有名です。
ビワの葉

Alicia97/Shutterstock.com
ビワは常緑樹で、一年を通してみずみずしい葉を保ちます。葉はやや厚みがあり、楕円形で長さは15〜20cm。このビワの葉は昔からお茶にも利用されてきました。ほのかに甘みがあり、くせがなく飲みやすい風味です。