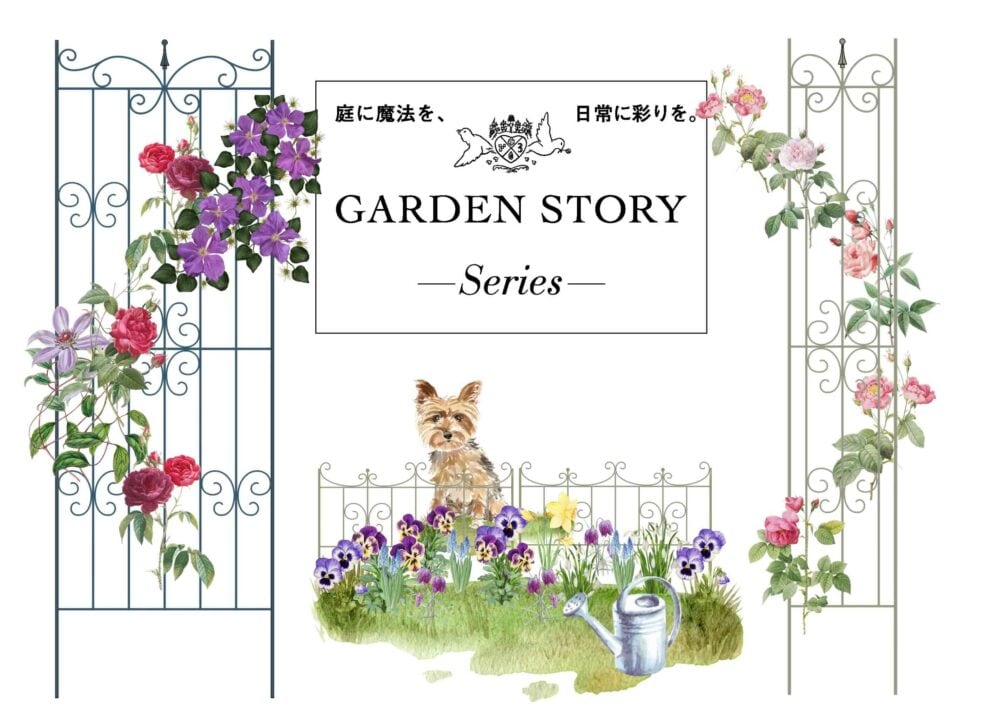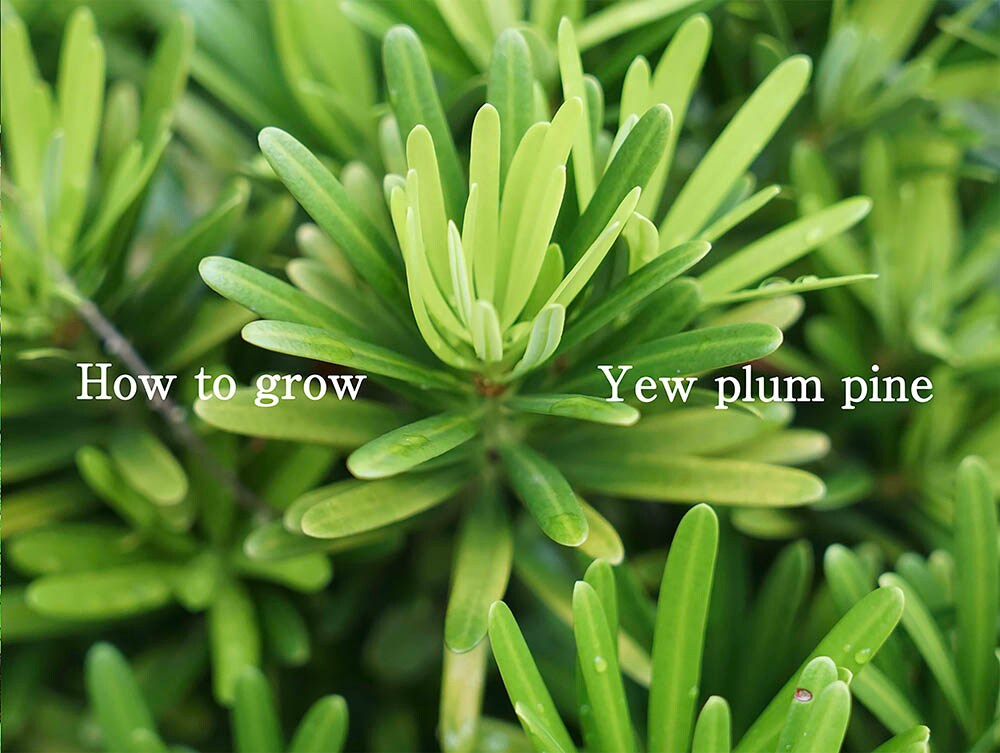
イヌマキは昔から和風庭園で重宝されてきた、日本人にとって親しみのある庭木です。常緑で冬もみずみずしい葉姿を保ち、密に茂るので生け垣などにもよく利用されてきました。日本の気候に合って育てやすいので初心者にもおすすめ。この記事では、イヌマキの基本情報や特徴、名前の由来や花言葉、種類、育て方などについて詳しくご紹介します。
イヌマキの基本情報

MTN2705/Shutterstock.com
植物名:イヌマキ
学名:Podocarpus macrophyllus
英名:Yew plum pine、Buddhist pine、Fern pine、Japanese yew
和名:イヌマキ(犬槇)
その他の名前:クサマキ、マキ、ホンマキ
科名:マキ科
属名:マキ属
原産地:日本、中国、台湾
形態:常緑性高木
イヌマキの学名は、Podocarpus macrophyllus(ポドカルプス・マクロフィラス)。マキ科マキ属の常緑針葉樹です。原産地は房総半島以西の本州、四国、九州、沖縄、台湾、中国南部。昔から日本の山野に自生してきたことから、丈夫で放任してもよく育ちます。比較的寒さにも強いほうですが、暖地を好む傾向にあります。樹高は20mに達する高木に分類されていますが、刈り込みによく耐え、毎年の剪定によって樹高をコントロールすることが可能です。
(広告の後にも続きます)
イヌマキの葉や花の特徴

Marinodenisenko/Shutterstock.com
園芸分類:庭木
開花時期:5〜6月
樹高:20m
耐寒性:強い
耐暑性:強い
イヌマキは針葉樹に分類されていますが、マツやコニフアーなどのような針状の葉ではなく、細長い線形をしています。葉の長さは10~15cm、幅は最大で1cmほど。葉裏はやや黄緑色がかります。幹は灰白色で、樹皮が縦に裂けて剥がれます。
イヌマキは雌雄異株の植物で雄木と雌木があり、5〜6月にそれぞれ葉のわきに花を咲かせます。雄花は穂状で花粉をびっしりとまとっているのが特徴です。雌花はボール状で、やがて赤い花托と白く粉をふいた緑の種子がつきます。花托とは花を支える部分のことです。赤黒く熟した花托は生食できますが、種子には毒があるので口にしないようにしてください。

左が雄花、右が花托をつけた実。tamu1500、KPG-Payless2/Shutterstock.com
和風庭園に映える主木

asharkyu/Shutterstock.com
イヌマキは葉が密に茂るので、玉仕立てにも利用できます。玉仕立てとは、幹から出ている側枝を刈り込んで、大小の玉を作る剪定の方法です。年月を経た古木を伝統的に仕立てた姿は、和庭に風格をもたらしてくれます。また、冬も葉を落とさない常緑樹なので、道路側や隣家との境界線などに目隠しを兼ねた生け垣にすることも可能です。年に数回刈り込むことで、枝葉が細かく密になり、美しい生け垣を保つことができます。