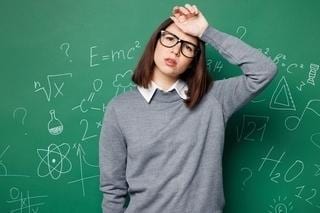ニュースや報道番組で目にする数字やデータは、必ずしも真実を正確に伝えているとは限りません。特にグラフは、その見せ方によって私たちの印象を大きく左右します本記事では、西岡壱誠氏の著書『東大視点 ものごとの本質を見抜くための31の疑問』より一部を抜粋・再編集して、情報を読み解く際に注意すべきポイントを解説します。
数字・データの理解度を上げる
数字やデータというのは、とても難しいものです。数字自体は変わらなくても、その数字の解釈は、比較対象やグラフの見方によって変わってきます。
例えば、「身長180cm」と聞いたら、みなさんは「高い」と感じますか? 「低い」と感じますか? おそらく多くの日本人からしたら「高い」と感じると思いますが、アメリカのフットボールチームに行ったら180cmでも身長が「低い」方かもしれません。同じように、「身長150cm」と聞いたら、パッと聞くと「低い」イメージですが、日本の10歳の男の子なのであれば150cmでも身長が「高い」方かもしれませんよね。
また、「過去との比較」をすると、180cmにも別の解釈が生まれます。例えば、180cmの人が3年前には160cmだった、と言われたら、どうでしょう? 「160cmの人が、3年で180cmになった」という変化を聞くと、「180cmってことは、すごく身長が高くなったんだな」と感じられますよね。変化する前の数字があると、その数字に違った意味合いが出てくるわけです。
英語では、楽観的なことを「glasshalffull」、悲観的なことを「glasshalfempty」と言います。これは、とある心理学の実験がもとになっているものです。グラスの中に、水を半分入れて、これを被験者に見せて、「グラスの中の水を、あなたは『半分も』入っていると思いますか? それとも『半分しか』入っていないと思いますか?」という質問をしたのです。
そして、「半分も」と答えた人は普段から楽観的な考えをする人で、「半分しか」と答えた人は悲観的な考えをする人だったのだそうです。半分の水は、ある人にとっては「いっぱいに入っている(full)」のと同じに見えて、ある人にとっては「入っていない(empty)」のと同じに見えるわけですね。
これと同じように、数字自体は変わらなくても、その数字の比較対象をどこに置くのか、どんなグラフでその数字を見るのか、ということによって、解釈は変わっていくわけです。
データの見方や比較検証のやり方は、非常に重要です。数字は噓を吐きませんが、噓吐きは数字を使ってこちらを騙そうとしてきます。情報を、ふわっとしたイメージのまま受け取らないようにするために、しっかりと数字やグラフを見る意識を持っておかなければならないのです。
本記事では、そんなふうに数字やグラフの見方についてみなさんに考えてもらいたいと思っています。
(広告の後にも続きます)
「グラフ」を用いた印象操作に注意!
「数字は噓をつかないが、噓つきは数字を使う」という格言は、アメリカの作家の言葉だと言われています。確かに、データとしての数字は、改ざんなどされない限り、間違いはありません。
しかし、「そのデータを用いて何かを主張しよう」と考えたとき、数字の使い方には人間の意図が入り込む余地がたくさんあります。代表的な例が「グラフ」です。その値を「どういうグラフで表現するか」に製作者の意図や悪意が含まれることがあります。
例として、図表1をご覧ください。こちらは2020年9月17日、福島テレビの番組「テレポートプラス」内で使用されたグラフです。
このグラフで示したかったのは、「調査内で『新型コロナに感染した人がいたら本人のせいだと思うか』という問いに対し『そう思う』と答えた人の割合が、日本はイギリス・アメリカの3〜4倍である」ということでしょう。確かに、調査結果の数字を見れば、イギリスの3.48%、アメリカの4.75%に比べると日本の15.25%は3〜4倍であると言えます。
しかし、ここで注意しなければならないのは、それでも約15%しかいないということです。残りの約85%は「そう思わない」と回答しており、どちらかというと「そう思う」は少数派の意見であることがわかります。
ところが、このグラフをもう一度見てみると、イギリスとアメリカでは少数派だった「そう思う」が、日本では多数派になっているような印象を受けます。その理由は、グラフの目盛の一番左の数字が「80%」となっており、その左側にあるはずの0〜80%の「そう思わない」の部分が省略されているからです。試しに、軸の一番左を「0%」にすると、[図表2]になります。
こちらは、2020年9月21日に同番組内で改めて放送されたグラフです。こうすると、確かにイギリスとアメリカに比べると日本では「そう思う」の割合が高いことがわかりますが、依然として少数派であることが正しく表現されています。この例からもわかるように、棒グラフというのはグラフ全体の大きさが非常に重要な形式なので、必ず「0%」から始めることが求められます。
もうひとつの例をご覧ください。[図表3]は、「NewsPicks」というネットメディアにて2015年2月9日の記事に掲載された、コミック誌と電子コミックの市場推移のグラフです。
このグラフで示したかったのは、「コミック誌の売り上げは年々減少していて、新興の電子コミックは売り上げを伸ばしている」ということです。確かに、グラフの形だけを見るとそのように読み取ることができます。
しかし、このグラフ、左右に2つの軸があることにお気づきでしょうか。左の軸は1目盛あたり500億円、右の軸は1目盛あたり100億円と、グラフのスケール(縮尺)が違うのです。左の軸はコミック誌、右の軸は電子コミックに対応しているので、2012年の両者の値を比較すると、コミック誌は約1500億円、電子コミックは約550億〜600億円となります。値としてはコミック誌の方が3倍近く大きいのに、グラフからはまるで電子コミックがコミック誌を追い抜いたかのような印象を受けます。
そこで、両者のスケールを統一すると、[図表4]になります(著者作製)。
確かに「コミック誌の売り上げは年々減少していて、新興の電子コミックは売り上げを伸ばしている」のですが、最初のグラフのようにコミック誌を追い抜いているような印象はなくなりました。
このように、グラフというのは作り手の意図が入り込む余地があり、見かけの印象が操作されている可能性があるので要注意です。こうしたグラフに騙されないためにも、グラフはあくまで表現手段であることを前提に値に注目しようと意識することや、適切なグラフとそうでないグラフを見分けるリテラシーを磨くことが大切です。
Point
・数字自体は変えられなくても、数字の使い方は変えることができ、悪用されやすい
・日頃から正しいグラフの条件を意識して、リテラシーを磨こう