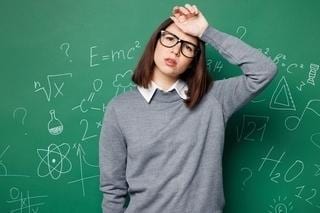イタリアの貴族制度は1948年に廃止されました。しかし、貴族の称号や家系は現在も存在しており、一部の人々はそれらを保持していますが、称号自体は法的な意味を持ちません。元貴族の子孫の中には、家系の伝統や文化、歴史的遺産を大切にしている人々もいます。彼らは、社会の中で様々な役割を担いながら、自分たちのルーツを尊重し、社会貢献活動などを行うこともあります。ただし、現代のイタリア社会において、貴族出身であることは特別な意味を持たず、一般の人々と同様に生活しています。本稿では、イタリアに20年以上住む中山久美子氏の著書『イタリア流。: 世界一、人生を楽しそうに生きている人たちの流儀』(大和出版)を一部抜粋・再編集し、イタリア生活の実態を紹介します。
身近にゴロゴロ?貴族の格を持つ人々
私が住む村には、オリーブオイルの搾油所があります。庭に1本だけある木から5キロほどの実が採れるようになり、隣人に相談すると「マルケジーナが自分とこのオリーブに混ぜて搾油して、重量比でオイルを分けてくれるよ」と教えてくれました。このマルケジーナは名前かと思いきや、マルケーゼ=侯爵の称号を持っていた家系の女性の愛称でした。
こ、侯爵? かつて貴族という階級があったのは知っていましたが、自分とは遠い世界の話かと思いきや、こんなに身近に存在するなんて! マルケジーナはグレーのおかっぱヘアに、毛玉のついたセーターとムートンを着た、いかにも農家のおばあちゃんでした。勝手に高貴な妄想をしていた私は拍子抜け。しかし、彼女の自宅は村の中心広場にある大きなお屋敷。そして、高齢なのに鋭さと温かさを持つまなざしで仕事に励む様子に、そこはかとない風格を感じたのです。
次に会った元貴族はバロネッサ=女爵。トスカーナの建築関連の連載記事の取材に行った、歴史的建造物をリノベーションしたモダンなホテルのオーナーです。日本の華族同様、イタリアの貴族制度も戦後に廃止されているものの、所有不動産を活用してホテルやワイナリーを経営しているために、裕福な貴族のイメージにかなり近い彼女。それでも私を温かくもてなし、気さくに話を聞かせてくれました。
そして元貴族は、友達のなかにも存在しました。モデナで伝統的バルサミコ酢の醸造を行う、日本人としては唯一のバルサミコ酢A級鑑定士です。初めてのモデナ郊外のお宅を訪問すると、立派なお屋敷には家紋まで。もしかして元貴族? それもそのはず、かつてモデナでのバルサミコ酢の醸造というのは、貴族の趣味だったのですから!
コンテ=伯爵の称号を持っていた家の長男に嫁ぎ、バルサミコ酢作りをご主人と継承することを決めた彼女。お屋敷も大きいし、そんなストーリーを聞くだけでまた勝手な妄想をしてしまうのですが、お抱えの使用人がいた昔とは訳が違います。作業着でブドウ絞りをする姿、輸出するために自家用車で輸送会社倉庫まで奔走する姿、理不尽で難解な制度や事務作業に嘆く姿。そこに華やかな「貴族」の面影はありません。
近年、旅の仕事で知り合ったアンナマリアもその一人。家族代々の邸宅を宿泊施設にし、宿泊客に邸宅ツアーを行っています。貴族だったの?と私が尋ねると、
「それはね、口で言うことではなくて、ふるまいに表れるものなのよ」
貴族の格があろうがなかろうが、一人の人間として素敵な人たちばかりです。
(広告の後にも続きます)
コロナ禍で生まれた自分だけの楽園
コロナから4年。今まで経験したことがないような非常事態に、人生や価値観が変わった人も少なくないのではないでしょうか? イタリアでは住居する市内で必要最低限の外出しか許されない、いわゆるロックダウンが2か月も続きました。
私もかつてないほど毎日24時間家族と一緒に過ごし、またリアル仕事はゼロになり、いろいろと考える日々を過ごしました。その裏で、人口1,800人でほとんどが顔見知りというこの村で、ある一人の女性が面白い方向へ人生の舵を切っていたとは、当時は知る由もありませんでした。
アンナはフィレンツェ出身。今彼女が住んでいる家は、司教区管理だった元教会と付属の建物でした。彼女の両親が結婚前にここに魅せられ、買い取ってリフォームして別荘に。アンナも幼少からここに慣れ親しんできました。しかし彼女が結婚して海外生活をしていた間、リタイアしてここに住んでいた両親が、その不便さからフィレンツェに引っ越すため、この家を売りに出そうと決めてしまいました。
するとアンナは、この家を手放したくない!と単身でここに戻ってきます。その後まもなく、コロナ禍に突入。まだ住民登録をしていなかった彼女には市からマスクが支給されず、マスクなしでは村に買物にも行けない状況になりました。しかし、ここからの彼女の頭の切り替えと行動がすごいのです。
「なければ、自分で作ればいいんじゃない?」
元々やっていた畑に加え、庭にあるもので何かできるんじゃない?と足りないものをオンラインショッピングで買い足し、体を洗うソープや掃除のための洗剤まで手作りを始めます。その知識は前から持っていたの?と聞くと、自分で調べまくってやっていくうちにどんどんハマっちゃったの!と嬉しそうに答えます。
そんな彼女が実践するのは、1970年代にオーストラリアの大学教授により提唱された「パーマカルチャー」。パーマネント(永続性)、アグリカルチャー(農業)、カルチャー(文化)を組み合わせた造語で、3つの原理と12の原則から成り立ちます。実際にやっていることを聞くと、自然にあるものだけを使って生態系を壊さずに土壌を作る。雨水を貯め、それを使い切るまたは循環させる。それぞれの植物の特性を生かし、生態系に負荷をかけずに良い循環を生み出す、などなど。
「乾燥に弱い植物の周りには、繁殖力の強いミントを茂らせて影を作るのよ」
彼女に案内されて庭を歩いてみると、どこが雑草でどこが植えたものなのか素人の私にはわかりません。ここはトライ&エラーを繰り返し、最適解を見出しながら作った、彼女だけの唯一無二の楽園です。
夏に満開を迎えるラベンダーは収穫して精油や芳香蒸留水に。秋のオリーブからとれるオイルは、食用で余った前年度分をソープやクリームの原料に。彼女の本業は、パリの研究機関でのリモートワークですが、「まだまだ時間が足りないの!」と、それ以外の時間はすべて、敷地内のケアや製品づくりに没頭しているそう。
数か国語を操る彼女は、WWOOF(有機ファームステイ)のホストでもあり、国際交流も楽しんでいます。日本人が来ると私をお茶に誘ってくれるのですが、私たちが日本語を話すと口元を見ながら同じ言葉を繰り返し、「今のどういう意味? 発音が可愛い!」と子どものように目をキラキラさせるアンナ。好奇心とほんの少しの行動力で人生はいつからでも変えられる。彼女を見るたび、いつもそう思わされます。
中山久美子
日伊通訳
コーディネーター