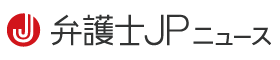「区役所の職員がコンビニの前でソフトクリームを食べている」。
そんなクレームがある区役所に入った。通報者は職員の顔を把握していたのだろう。コンビニ前でアイスを食べている姿が怠慢、あるいは不謹慎とでも言いたかったのか…。
ある美容室では女性がカラーをしてもらったが仕上がりが気に入らなかった。そこで泣きながら「時間を元に戻して!!」と美容師に無理な要求をし続け、長時間店内に居座った。
これら実際のカスハラ事例を明かしてくれたのは、日本ハラスメント協会代表理事の村嵜要氏。
潮目が変わったカスハラへの対応
「顧客がサービス提供側に不平・不満をぶつける点ではクレームもカスハラと同類と思われるかもしれません。しかし、両者は明確に違います。
クレームは商品やサービスに不備がある場合に事実を指摘し、あくまで原状回復を目指すもの。一方、カスハラは自分勝手な解釈でサービスの範囲を超えた不当な要求をすることです。
ただし、内容的には正当なクレームでも、言い方が乱暴であったり、侮辱する言葉が入るなどプラスアルファの言動でカスハラに変化してしまいますので注意が必要です」
これまでは顧客からの理不尽な対応は、サービスを提供する側が甘受せざるを得ないものとして黙認されてきたが、ようやく潮目が変わった。11日には「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策を企業へ義務付けることなどを柱とした労働施策総合推進法など関連法の改正案を閣議決定し、カスハラ予防が義務化される。
ここ数年、各企業は深刻化するカスハラを問題視し、対策を打ち出すなど、客であっても不当な要求は悪との捉え方が浸透しつつある。
旅行大手のJTBグループは6日、独自に策定した「カスタマーハラスメントの基本指針」を公開。厚労省のマニュアルを参照しつつ、企業としての毅然とした対応を示し、場合によってはサービス提供を断る可能性も明記した。
「カスハラ防止が義務化されれば、法律を根拠に正当なクレームとカスハラをはっきり区別した対応が可能になります。今後は多くの企業で従業員個人の責任ではなく、企業組織としてカスハラ対策をしていくので、客を怒らせた従業員個人が悪いと責められなくなります。そのため、従業員の精神的負担は大幅に軽減されるでしょう。
これまではフォーカスされづらかったですが、カスハラ被害を受けた従業員への安全配慮義務も企業は守りやすくなります。義務化によって、顧客側がカスハラしないよう気をつけるきっかけにもなり、サービス提供側が客を甘やかしすぎていた部分も今後、改善に向かっていく意義は大きいと思います」(村嵜氏)
冒頭のような事例が発生した時、これまでなら顧客への対応をSNSでさらされ、風評被害につながるケースも珍しくなかった。カスハラ対策の義務化はこうした行為への抑止力としても期待されると村嵜氏は展望する。
「カスハラが問題行為であることが社会に浸透していけば、顧客へのきつい対応をSNSでさらされても、世間の人は今後、当該の従業員や企業側をむしろ支持する方へシフトしていくのではないでしょうか」
カスハラが発生したらどう対処すればいいのか
そのうえで村嵜氏は企業のカスハラ対策として次のように助言する。
「昨今は多くの企業が導入を始めていますが、まずはカスハラ対応方針を定め、ホームページで公開したり、店内ポスター等に明記しておくことです。そうすることで、いざ現場でカスハラが発生した際に、それを根拠に毅然とした対応も可能になります。
ただし、カスハラをする顧客の中には、これに対して態度を硬化させ、すごんでくる者もいます。その場合は警察に通報し、対応を委ねることを推奨しています」
もっとも、当初は顧客側に不備がなかったものの、従業員の接客や対応が不十分でコミュニケーションが険悪になり、カスハラに発展するケースもある。こうした場合は、どのように対処すべきなのか。
「従業員の対応が不十分でトラブルにつながるような場合は、カスハラとは分けて考える必要があります。企業側は問題を迅速に精査し、ミス等が発覚したなら必要に応じて謝罪や商品交換をする。ここまでは正当なクレームへの対応です。
万一、そこからカスハラにまで状況が悪化した場合は、たとえば暴言については真に受ける必要はありませんので、『クレームに対する対応は先ほど完了いたしました』と明確な対応をとるのがベターです。
予防策としては、企業が社内研修等で上記の区別を現場従業員の共通認識となるよう指導することが挙げられます。共通認識を持って仕事ができれば、過剰な要求であるカスハラに余計な時間を取られたり、従業員が精神的苦痛を感じたりする機会が少しでも削減できます」
今後、カスハラ対策はどこへ向かうのか
日本のサービス業は過剰ともいえる接客で‟おもてなし文化”を醸成した。その結果、顧客の要求がエスカレートし、カスハラを誘発する余地ができた側面もある。今後、サービス業を疲弊させてきたカスハラ対応はどうなっていくのか。
「たとえば、パワハラ等の対応における予算の確保は企業や自治体で年々増加しています。こうしたことから、当協会が提供しているカスハラ対応窓口のように、外部に任せる企業も今後、増えていくのではないでしょうか」(村嵜氏)
カスハラ対策関連の施策に積極的に取り組む東京都では、企業・団体それぞれを対象に、49億円の予算を組み、カスハラ防止対策に40万円(団体は最大100万円)を支給する助成金を創設。カスハラ撲滅を後押ししており、対応をプロに外注する流れも加速しそうだ。
冒頭の「コンビニでアイスを」といったカスハラは言いがかりともいえ、業務を止めるだけでなく、職員の心身をすり減らす悪質な妨害行為でしかない。こうした行為への対応を、各企業が毅然と行うことがスタンダードになれば、ゆがみが生じていた企業と顧客との関係性も修復の方向へ向かっていきそうだ。